|
18.8.15 | �����R��i�L�c�O�B�j/��R�O�Y/�V������ |
 �@���U�P�N���o�߂������N���܂�������������ɂ��āA�e���r���͂��߂Ƃ���}�X�R�~����������i�����j�藧�ĂĂ��܂��B���̃e���r�ԑg�̈�����Ă���܂�����A�`����ƂƂ���i��Y�ɂ��ꂽ�L�c�O�B���̂����������_�Ђւ̍L�c���̍��J�i�������j�ɂ��āA�u�������玖�O�ɍ��J�̘A���͂Ȃ������B������Ă���Βf�����v�܂��u�����͌R�l���v�҂��Ղ�Ƃ���v�ł���A���O�ɍ��J��Őf����Ă���u�c���͌R�l�ł���v�҂ł��Ȃ��B�����⊙�q�̂�������Q�肷��Ώ\���������߂Ă��������A�ƒf�������낤�v�ƌ���Ă����܂����B
�@���U�P�N���o�߂������N���܂�������������ɂ��āA�e���r���͂��߂Ƃ���}�X�R�~����������i�����j�藧�ĂĂ��܂��B���̃e���r�ԑg�̈�����Ă���܂�����A�`����ƂƂ���i��Y�ɂ��ꂽ�L�c�O�B���̂����������_�Ђւ̍L�c���̍��J�i�������j�ɂ��āA�u�������玖�O�ɍ��J�̘A���͂Ȃ������B������Ă���Βf�����v�܂��u�����͌R�l���v�҂��Ղ�Ƃ���v�ł���A���O�ɍ��J��Őf����Ă���u�c���͌R�l�ł���v�҂ł��Ȃ��B�����⊙�q�̂�������Q�肷��Ώ\���������߂Ă��������A�ƒf�������낤�v�ƌ���Ă����܂����B
�@���̂�������������肽�����Ƃ́A�u���̐푈�͌R�l���N�������푈�ł����ĕ����ł���L�c�O�B�͑j�~���悤�Ƃ����̂��B�L�c�O�B�͂���Δ�Q�҂��B�v�u�R�l�͌������A������ꏏ�ɂ��ė~�����Ȃ��B�v�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��Ǝv���܂����B�������A���͂���ɑ�ψ�a�����o���܂����B
�@�ŏ��Ɏv���܂����̂́A����͂����܂ł��⑰�̌����ł����čL�c�O�B�{�l�̍l�����ǂ��ł������̂��͉���Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B�Ђ���Ƃ�����A�L�c�O�B�́A�R�l�̂��Ƃ𑽏��͋C�ɐH��Ȃ�������������Ȃ����A���ɐ�������Ԃł���A���ɖ��O�̎����}�������u�Ȃ̂ł�����A���ɉp��Ƃ����J���Ă��炢����������������Ȃ��̂ł��B�{�l�̋C�����͂킩��܂���B���Ȃ��Ƃ��A��̎���̉��l�ς������āA���ꂪ���⑰�ł����Ă��{�l�ȊO�̐l���A�Ƃ₩���������Ƃł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv�����̂ł��B
�@�����������������Ƃ��������悤�ɂȂ�A���̐�X�F�X�Ȏq�������J����Ƃ�������č��J����Ƃ�������A��������ɍ������邾���ł��B
�@���������w�i�̉��ɁA�L�c�O�B�́A�����ɍ��J����邱�Ƃ��ǂ��l�����ł��낤���A�Ƃ������Ƃ�O���ɂ����Ă��̖{��ǂ�ł݂܂����B�ȉ��A�����ł��B�i�L�c�O�B���ȉ��L�c�ƋL���܂��B�j
�@�L�c�͐Ή��̘�Ƃ��Đ��܂�A�����閼��̏o�ł͂���܂���B�O����������ꍑ�̍ɑ��ɂ܂ŏ��l�߂܂����A�������g���u�������v�ł���ƈʒu�Â��A�u�w�L�̎v�Ƃ��ĒW�X�Ɣ�펞�ɂ������ςɍ���ȐE���𐋍s���Ă����̂ł��B�����I�����ւ̑Ή����j�ɂ��ẮA�O��w�͂�D�悵���͖̂ܘ_�̂��Ƃł����A���ȂɊւ��邱�Ƃɂ��ẮA�u����v���ʁv�����E�̖��Ƃ��A����������M����̂ł͂Ȃ����邪�܂܂̐�����������Ƃ������Ƃł������A�Ǝ��͗������܂����B���́u����v���ʁv�Ƃ������t�́A��i�����x���o�Ă��܂��B�@���āA���J���ꂽ���ƂɊւ��čL�c���ǂ��l���邾�낤���Ƃ����_�ł����A���́u����v���ʁv�Ƃ������Ƃł͂Ȃ����Ǝ��ɂ͎v���܂��B�܂�A���邪�܂܂�����邾�낤�A�Ƃ������̂ł��B�����A���ۖ��Ƃ��čL�c�{�l�̐S���s���ł�����A���ɂ͂��⑰�̐S�d���Ȃ���Ȃ�Ȃ��͓̂��R�ł����A�ȉ��q�ׂ�悤�ɁA���⑰�̂��l����f���Ɏ~�߂��Ȃ�����������܂��B �@���̖{�ł́A�哌���푈�J�풼�O�̒i�K����s��E���́E�����ٔ��̒i�K�܂ŁA������푈�w���҂����̓������L�c�����Ƃ��ĕ`����Ă���܂��B���R�A�����ɂ͌R���w���҂��吨�`����Ă���̂ł����A��҂̏�R�O�Y�́A�Ȃ�Ƃ��̑S�Ă��u���v�Ƃ��ĕ`���Ă���̂ł��B�R�l�B�͂����ɂ���łŒZ���I�ōD��I�ŁA�푈���~�߂悤�Ƃ���L�c�̓w�͂����Ƃ��Ƃ��ׂ��A����Ȉ��l�ɕ`���Ă���̂ł��B�����ׂ����ƂɁA�قƂ�ǑS�Ă̋L�q�������Ȃ̂ł��B
�@�����āA����I�Ȃ̂��u�i�قڂ��̎����͖��������ƍl�����Ă���j�싞��s�E�v���������Ƃ��āA����ɑΉ����鐭�{�̓����Ȃǂ����A���ɕ`���Ă��镔���ł��B�i�قږ���������ł�����A���������Νs���ł��B�j����́A���炩�ɓ����ٔ��̌��ʂ��A���邢�͓��x�Y�Ƃ����Ό�������Ƃ́u�싞�����v�����̂܂܉��p���Ă��邱�Ƃɂ�錋�ʂȂ̂ł��B���̖{�i�����R��j���㈲���ꂽ���a�S�X�N���_�ł́A���݂̂悤�Ɏ����̉𖾂��i��ł��Ȃ��������Ƃ�����ł��傤���A��ɋL�����悤�ɌR��������ׂ����Ƃ��鎋�_��������̂ł�����A�ɂ߂ăC�[�W�[�Ȏ����̎�舵���������Ă���Ƃ����Ă悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�����Ȃ�A��R�O�Y�́i���Ȃ��Ƃ����̎��_�ł́j�����ٔ��j�ςɊ��S�ɐ��܂��Ă����Ƃ����Ă悢�ł��傤�B�����āA�s�K�Ȃ��Ƃɂ��̖{�͏��a�S�X�N�̖����o�ŕ����܂Ƌg��p�����w�܂���܂��Ă��܂��܂����B���R�A�L�c�O�B�̂��⑰�����̖{��ǂ܂�A�傫�ȉe�����Ă�����v���܂��B���������āA�`���̂悤�Ȕ����Ɏ����Ă���Ǝv���̂ł��B �@���āA���̖{�́A�i�C�����̈������炢�j�L�c��ڈ�t�Ɏ����グ�����e�ɂȂ��Ă���̂ł����A�ʂ����Ă���������̂ł��傤���B���҂����x�����グ�Ă���u����v���ʁv�Ƃ����̂��A����Ȃɑf���炵�����ƂȂ̂ł��傤���B
�@�Ƃ����̂��A�L�c�͓����ٔ��ɂ����āA�Ō�܂ŐϋɓI�ȍs����S�����Ȃ��̂ł��B�������g�ɂ͐푈�ɂ��Ă̐ӔC������Ƃ��āA��������J�����Ƃ����܂���ł����B�u����v��킸�v�Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���A���̍ٔ��͍L�c�O�B�l���ق����Ƃ݂̂Ȃ炸�A���{���ق����Ƃ�ړI�Ƃ������̂ł��邱�Ƃ��ނ̔O�����甲���Ă���܂����B�ꍑ�̍ɑ��߂�قǂ̌����������Ȃ���A�܂��A���ۂ̍ٔ��̉Q���ɐg��u���Ȃ���A���̏d�v�Ȃ��ƂɎv��������Ȃ������̂ł��傤���B�����p�@�Ȃǂ����X���X���Ƃٌ̕���s�Ȃ��Ă�����ނ͂ǂ̂悤�Ɍ��Ă����̂ł��傤���B�Ђ���Ƃ����琏���g����Ȑl�Ԑ��ł������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�L�c�ɂ́A�ނ̂��Ƃ������l�ɂ����������������Ă��܂��i�\�͂̒Ⴂ���Ƃ����������̂������Ǝv���܂����A���m�ɂ͎��O�j�B������������A�ނ͂��̖{�ŏ�����Ă���悤�ȁu�X�[�p�[�v�ł͂Ȃ��A�����I�Ɍ���ƁA�ނ��날�����̕��ɋ߂������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�i���������߂���������܂��A�����I�Ɍ���ƁA�ł��B�j
�@�{�̋L�q�̒��Ɏ��̂悤�Ȃ��̂�����܂��B
�����p�J�n��
�i�A���͑��i�ߒ����R�{�\�Z����̗t�������Ȃ���B���̗t���̒��ɂ́A�j
�Z�����������̈��A�̌�A
�u�ԂȂ�A����������v�Ƃ������B
�u���ł������Ⴀ��܂����v
�L�c�́A�f���̂Ă�悤�Ɍ������B
�u�R�{�͂���ł�����������A���͂ǂ��Ȃ�B���ƂƂ������̂́A�i���������Ƃ��厖�ȂB�N����ɂ��A������̊ނƂȂ�đۂ̂ނ��܂łƂ��邶��Ȃ����B����Ȃ̂Ɂc�B�v
�����p�I�聄
�i�{���ɂ��̂Ƃ���̌��t�����������ǂ����A���p����������Ă���܂��A�����ł�����ڂ�����𗧂Ă�قǂł͂Ȃ��Ǝv���܂����j�R�{�����́u��܂��߂��v�ƍL�c�O�B�́u�܂��߂��A�Ђ̂Ȃ��v�����ɂ͊������܂��B�܂��A�������̔����������ł������̂Ȃ�A�����ٔ��ł͓����ƕ���ō��Ƃٌ̕�ɓw�͂��ׂ��ł������͂��ł��B
�@
�@�ȏ�̂悤�ɁA�`���̍L�c�O�B�̂�������̂��ӌ��ɂ��ẮA��͂莄�͓��ӂł��܂���B�܂��A�S�̂Ƃ��ď�R�O�Y�̕M�v�ɋ^�₪����܂����A�L�c�l�ɂ��^��������܂����B �@�ł��l���Ă݂�A���̖{�͗��j�����ł��B
�@�����āA���̗��j�����ɂ��Z�W�F�X�����āA����Ȃǂ͗��j�I�������班�����ꂽ�A�X�ɂ͏����Ԃ��F�����������Ƃ����Ă悢�ł��傤�B�������A�i�n�ɑ��Y�̖���u��̏�̉_�v�̂悤�ɁA�����S�̂ɑ傫�ȉe����^����ꍇ������킯�ł��̂ŁA���ӂ��ď����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���������ӂ��ēǂޕK�v������Ǝv���܂��ˁB �@���̍�i�͑�������ƁA�����ٔ��j�ς������ĕ`���ꂽ��i�ŁA�������P�A�R�i�l�j�����ɐF�����̔Z���A��ςɃo�����X�����������j�������̏����Ƃ�����Ǝv���܂��B���̕]���͂S�T�_�ł��B
�@ |
|
| 18.7.20 | �l�ԋ�����V/���嗘�t/����ި��ޮ� |
 �@�ŏ��Ɏʐ^�̏Љ�ł��B���̎ʐ^�͏o���O�A���̎}����Ɏ����āA������ɓ����Ă��镗�i�ł��B�݂������܂��B �@�ŏ��Ɏʐ^�̏Љ�ł��B���̎ʐ^�͏o���O�A���̎}����Ɏ����āA������ɓ����Ă��镗�i�ł��B�݂������܂��B |
�@���̎d����̏�i�ɂ�����c���������A�L�������s����a�~���[�W�A�������w�����ۂɁA�����̂��܂肻���Ŕ����Ă������̖{���w�����A�E���ł��鎄�ɂ��������݂��Ă��ꂽ���̂ł��B
�@���̖{�́A�S����V��̉�i�C��72���A��V�������i�ҋ@���ɏI��j�j�ق��̊W�҂̕��X�̊ďC�ɂ���č쐬���ꂽ��V�Ɋւ���ʐ^�L�^�W�ł��B
�@���e�̍\���́A��V���̂��̂̉���A��n�y�ьP���A�U�������Ƃ̐퓬�A�⏑�A�P�l�ЂƂ�̓�����̊�ʐ^�ƂȂ��Ă��܂��B
�@��V�͊ȒP�Ɍ����A�X�R�������i�y��1.5�d�j���x�[�X�ɂ��āA����ɐl�ԂƂ����U�����u�𓋍ڂ��邽�߂̑��c�Ȃ����t�������̂ł��B�U���͊�{�I�Ɏ������c�ŁA����Ɏ蓮�ɂ�鑀�c���I�[�o�[���C�h�ł���Ƃ������̂̂悤�ł��B�j�H�́A�W���C���ɂ���Ē��₳�ꂽ���ʂ��ێ�����A�[�x�����₳�ꂽ�[�x�Ɏ����Ő��䂳���悤�ł��B
�@
�@��{�I�ȉ^�p�́A���̂悤�ł��B
�@�����͂Ɏ��t����ꂽ��Ԃō��C��ɐi�o���A�����͊͒����U�������S������A��������A�ڂ��ꂽ�ʘH�i��ʓ��j��ʂ��ĉ�V�Ɉڏ悵�܂��B���v�̋����ɂȂ����Ƃ���ŁA�G���W���n���A�W���C������i����͂����Ƒ���������������Ȃ��j�A�Œ�o���h�̊J���A���̒���A����܂łɘA���p�Ɏg�p���Ă����d�b��������������Ȃ��甭�i���Ă����܂��B
�@�r���A�ڕW������̐��]���Ŋm�F���āA�ŏI�̓˓��ƂȂ�܂��B�G�͂ɏՓ˂��钼�O�ɁA������͐M�ǂɌq�������n���h���Ɏ��Y���A�Փ˂̏Ռ��ő̏d������Ɋ|����悤�Ȏp�����Ƃ�܂��B�����āA�c�B
�@�Ō�́A���炪�M�ǂƂȂ�̂ł��ˁB
�@
�@�P���́A������ɂ߂��悤�ł��B��V�͂��Ƃ��Ƃ������ł�����A����g�p���Ȃ����Ƃ�O��ɐv���Ă���܂��B�G���W���Ȃǂ��A�����肫����Ɠ����悢��ł��B�Ƃ��낪�A�P�����s�Ȃ��ɍۂ��ẮA�J��Ԃ��g�p���Ȃ���Ȃ�܂���B���̂��߂ɖ���A�������Č����E�������s�Ȃ��������ł��B���݂̂悤�ȕi���Ǘ����\���łȂ����������A�����S���̏����̋�J�͑����Ȃ��̂ł������悤�ł��B�����āA���̂ɂ��}�E�����N�����Ă��܂��B����͂������̂��ƌP���������ł������킯�ł��B
�@�G���W���͏��_�f�ƃP���V���i�������j��R���Ƃ��A���҂�R�Ď��ň�C�ɔR�Ă����A�����ɊC�������A�c��ȍ����������C�������A����łQ�C���s�X�g���G���W�����쓮����Ƃ������̂ł��B�r�K�X�͏��C�ł�����A�q�Ղ��o�ɂ����Ƃ�����ł��B
�@���̑��ɂ���X�̍H�v���{����Ă���A�Ȃ��Ȃ��̂��̂ł������悤�ł��B�[����ɂ��Ă������ł����A������������̋Z�p�͂͂����������̂ł����B
�@��n�͎��h����͂ނ悤�ɂ��ĉ��ӏ����݂��Ă���܂����B�P���Ɏ�Ⴊ�����ꂽ�̂ł��傤�B
�@��V���i�X�����j�Ő�v���ꂽ�����͂P�Q�Q�X���B���̂�����V������P�O�U���A��V�𓋍ڂ��ďo���̐����͏��g���W�P�Q���A���̑���n�W�����X�A�ł��B�����͏�g���̐펀�҂���ԑ��������̂ł��ˁB
�@
�@�����̋傪�������Љ�Ă���܂��B
�@���̂Ȃ��Ŏ��̐S�Ɏc������B
�@�u�G�̑O�\�ł��܂��݂₪��Ɓ@�����̐������������v
�@�C�R���с@��������i�Q�T�j�@1944.11.20�@�E���V�[�C��ɂē˓��@�c���o�g�\���w��
�@���ɍڂ����ʐ^������f����̂ł����A���ɂ����Ƃ��Ă��܂��B�����Ɏ���܂łɂ́A���邢�͂��̌�ł��A��ςȋ�Y�𖡂�����͂��ł��B�����āA�����B�Ȃ�ɋC�����̐��������āA�S�̂ق������߂���ł��B
�@�ȉ��A�ʐ^���ڂ��܂��B��������A��i�Ȃǂ��������A�������܂����L�O�ʐ^�ł͂���܂���B���ԂŎB�����L�O�ʐ^�ł��B�F�A���ɂɂ��₩�Ȋ�ł��B�m���̓��U�L�O�قł����l�Ȏʐ^������܂����B
�@�����̂��ς��Ȃ��A�N�����̒ꔲ���̖��邳���������܂��B
�@�����m��Ă���̂ł����A�������Ăӂ��������Ƃ������ƂȂ̂ł��ˁB
�@������悤�ȕ�����Ȃ��悤�ȁA����ȋC�����ł��B



�@���B�́A���������l�����������̂��Ƃ������Ƃ����Ȃ��Ƃ��m���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���킹�Ċ��ӂ̋C�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B
�@ |
|
| 18.7.4 | ���������̖ʉe/�n�Ӌ���/���}�Ѓ��C�u�����[ |
�@�ȑO�A�C�U�x���o�[�h�́u���N�I�s�v�Ƃ����{���ϋ����[���ǂ݂܂����B��ϗD�ꂽ�h�L�������^���[�ł���ƂƂ��ɁA���{�l�̗D�ꂽ�������x�ߒ��N�Ƃ̔�r�ɂ����Ċ��ʂ���Ă���_�ɋ������o�����̂ł����B
�@���́u���������̖ʉe�v���A�W�������I�ɂ͂��́u���N�I�s�v�Ɠ��l�̖{�ł���܂��āA�����̔��ɑ����̊O���l�ɂ����{�ɂ��ẴR�����g�W�Ƃ����Ă悢�Ǝv���܂��B
�@�ȉ��ɋL���܂����A�����āu�L���ȃo���F�̓��{�v�͊m���ɂ������̂ł��B���B�́A���{�l�ɂ����Ǝ��M�����ׂ��ł��B�����āA��������߂��Ȃ���Ȃ�܂���B
|
 �@�y���[�̉Y�ꗈ�q�ȗ��A�����̐��m�l�����{�ɂ���Ă��܂����B
�@�y���[�̉Y�ꗈ�q�ȗ��A�����̐��m�l�����{�ɂ���Ă��܂����B
�@�]�˖������疾���ɂ����āA��g�A���̉Ƒ��A���s�ƁA�D���A�R�l�A�����A�w�ҁA��ƁE�E�E���X���傢�Ȃ�D��S�������āA���{�ɏ㗤���Ă����̂ł��B�����āA���������l�������A���{�ɂ��Ă̏㎿�̋L�^���ʂɎc���Ă��܂��āA���҂͂��̖c��Ȏ������x�[�X�ɂ��Ă��̍��̓��{�̎p���Č����Ă���Ă���̂ł��B
�@���̖{�ɌJ��L�����Ă���̂́A�������̂���c�l�����̐������A�l�����ł��āA�P�Ȃ�ʐ^�W�Ȃǂ���͉���Ȃ��A��i�[�����e�Ȃ̂ł��B�@���āA���̍��̓��{�̎p�Ȃ̂ł����A�����Ĉꌾ�Ō����Α�ρu�L���Ȑ��E�v�ł������̂ł��B
�@���́u�L�����v�Ƃ́A�P�Ȃ郂�m�₨���ł͂Ȃ��A�X�l�̐S�̂Ȃ��ɂ���[�����A�K�����̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂ł��B���̓_�ŁA�����͑�ϖL���������Ǝv���܂��B�e���q���E���A�q���e���E���Ƃ������Ƃ��p�����Ă��錻��B����́A�����ĖL���Ƃ͂����܂���B���́u�L�����v���������͎����Ă��܂��܂����B������A���҂́u���������v�ƁA�������Â�ł���̂ł��B
�@���̖{�͕��ɖ{�ł����A�����͖�R�p�A��600�ŁA�w�p�������Ƃ����Ă��ǂ����e�ɂȂ��Ă��܂��B�����āA���̕������{�̂Ȃ��ɂ́A���m�l�������₵�����X�̕����ɂ���āA���̖L���������ׂ��ɗ����Ă���̂ł��B
�@���̖ڎ����炴���Ǝ��グ�܂��Ă��A�u�z�C�Ȑl�X�v�u�ȑf�Ƃ䂽�����v�u�e�a�Ɨ�߁v�u�G���Ə[��v�u�q�ǂ��̊y���v�u���i�ƃR�X���X�v�c���X�A�u�L���Ȑ��E�v�ł��������Ƃ��f���܂��B �@�������̓��e�ɐG��Ă݂����Ǝv���܂��B�i�ȉ��A�u���L�^�ҁi���̐l�̏Љ�j�G���e�v�̏��ɂȂ��Ă��܂��B�j
���I���t�@���g�i1858�A���p�C�D�ʏ��������̂��߂ɗ��������G���M�����i�g�ߒc�j�̌l�鏑�j�B�ނ́A����܂łɁA�Z�C�����A�G�W�v�g�A�l�p�[���A���V�A�A�����ɂ��Ă̌����������A���s�L�������Ă��܂��B���̔ނ��u�o���F�̓��{�v���������܂��B
�G�u�l�������̂̋]���ɂȂ���{�ŁA�e�l���܂������K���Ŗ������Ă���悤�Ɍ����邱�Ƃ́A�����ׂ����Ƃł���B�v�u�c�������������A����ꂪ���̒��ɂ��������́A�F�D�I�Ŋ��e�Ȑ��i�̑N�₩�ȏ؋���^���Ă��ꂽ�B�c�v�u���{�l�͎�������܂ʼn�������ŁA�ł��D���̂��Ă鍑���ŁA���{�͕n�����╨��̂܂������Ȃ��B��̍��ł��v(39p)
���I�Y�{�[���i���A�g�ߒc�̎g�p�����D�̑D���j�̋L�q�B���{�l�̐F�ʊ��o�ɂ��ď����Ă��܂��B�����āA�����͑S�Ă̊O���l�ώ@�҂����ʂɔF�߂����Ƃł���A�ƒ��҂͕t�������Ă��܂��B
�G�u������K���̕��i���̐F�͍����_�[�N�u���[�Ŗ͗l�͑��l���B�������͓K���ɑ�ڂɌ����Ă���A�������A���̓������s�g���āA�����Ɩ��邢�F�̈ߕ��𒅂Ă���B����ł��ޏ���͎���ǂ��̂ŁA���������F�͈�ʂɔ�������B�v(44p)
���S���`�����t�i1853�A�v�[�`���[�`���g�ߒc�̈���j�̋L�q�B
�G���ڂ̖�l�����̕������݂āA�u���̒��ɂǂ����N���ȐF���ȁv���u���F�̂܂܂̂͂ЂƂ������v�u�S�Ă����a�F�̘a�₩�ȓ�F���ł���v�B�܂��u�ЂƂ��Ƃł����Ɓi���[���b�p�́j�ŐV�̗��s�F���S�������Ă����v�B(46p)
���I�[���R�b�N�i���㒓���p�����g�j
�u���{�l�͂��낢��Ȍ��_�������Ă���Ƃ͂����A�K���ŋC�����ȁA�s���̂Ȃ������ł���悤�Ɏv����v
���y���[�G�u�l�X�͍K���Ŗ��������v(74p)
���e�B���[�i1859�A���V�A�͑��̈���Ƃ��ĖK�������p���l�j
�G���ق̈�ۂƂ��āu���N�Ɩ����͒j���Ƃ��ǂ��̊�ɏ����Ă���v(74p)
���C�U�x���E�o�[�h�i�����������j
�G���k�n����n�ŏc�f���̐X�����Łu�i�D�œh��ł߂��悤�ȁj�Z���̑O�ō��܂ŗ��Ő�����Ă���l�X�̕\��w�݂ȗ��������������x�������Ă����v�Ə����Ƃǂ߂Ă��܂��B(76p)
�������_�E�i�X�C�X�ʏ������c���A�����X�C�X�̎��j
�G�u���̖����͏���˂ł���v�u���{�l�قǖ����ɂȂ�Ղ��l��͂قƂ�ǂ���܂��B�ǂ��ɂ��戫���ɂ���A�ǂ�ȏ�k�ł���������B�����Ďq�ǂ��̂悤�ɁA���n�߂�ƁA���R���Ȃ����n�߂�̂ł���B�v(76p)
���x���N�i�I�C�����u���N�g�ߒc�j
�G�ނ�́u�b�������Ƃ��ɂ͏�k�Ə�������Y����B���{�l�͐��܂�����������C��������̂ł���B�v(77p)
�����[�`�j�R�t�i1874�A�����O��w�Z�A���V�A�ꋳ�t�j
�G�u�ׂ̂܂��Ȃ��ɏ�k���Ƃ��Ă͏��]����킪�l�������v�Ɍ��Ƃꂸ�ɂ͂����Ȃ������B(77p)
���{�[�{���[��
�G���B�A�W�����A�^�C�A�����̗�K��u���{�́A���̗��s�S�̂�ʂ��A�����܂�������̒��ň�ԑf���炵���v�B�Ȃ��ł��u�{���̌����́v�͔��p�ł������ł����R�ł��Ȃ��A�u���X���X�̌��i�A�c�v�B���{�l�́u����͂��������Ƃ��Ĉ��z�ǂ��A�ˑ�������������A����͍ŏ��̈�ڂł҂�Ɨ����v�B�������́u�ɂ��₩�ŏ��ӋC�A�z�C�ō��F�v�����Ă���B
���A���x�[���i1863�A�X�C�X�����g�ߒc���j
�G�_�����������Ă���ƁA�l�X�͔_�Ƃɏ�������A��̈�Ԕ������Ԃ�����Ď������Ă���A��������ɑ�������Ȃ��̂������B
���C�U�x���o�[�h�i�O�o�j
�G���̓��̗������I���ďh�ɒ������Ƃ��A�n�̊v�т��ЂƂ����Ȃ��Ă����B�u�����Â��Ȃ��Ă����̂ɁA���̒j�͂����{���ɂP���������Ԃ��A�������K���������悤�Ƃ����̂��A�ړI�n�܂őS�Ă̂��̂�������Ɠ͂���̂������̐ӔC���ƌ����ċ��B�v�u���[���b�p�̍��̑�����A�Ƃ���ɂ���Ă͂������ɉ䂪���ł��A�������O���̈ߑ��łЂƂ藷������Ό����̊댯�͂Ȃ��Ƃ��Ă��A����╎�J�ɂ�������A�����ڂ�ꂽ�肷�����̂����A���͈�x����Ɩ���Ȗڂɉ��Ȃ��������A�@�O�ȗ������ӂ�������ꂽ���Ƃ��Ȃ��B�v
���u�X�P�i1872�A�i�@�Ȍږ�j
�G�������s�̍ۂ̉�U�����ɂ��āu�ނ�͂��܂�~���Ȃ��A�����������Ċ��ł�������A�c�A���̂悤�ȏ����K���Ɏ���܂ŁA�s�V�͐\�����Ȃ��B�v
���A���x�[���i1863�A�X�C�X�����g�ߒc���j
�G�u�]�ˏ����̓����v�Ƃ��āA�u�Ќ��D���Ȗ{�\�A��@���ȑf���A���ӑ����̍ˁv�������A����ɂ́u���{�l�̓����K���̐l�����̒����������v�Ƃ��āA�u�z�C�Ȃ��ƁB�C���������ς�Ƃ��ĕ��ɍS�D���Ȃ����ƁA�q�ǂ��̂悤�ɂ����ɂ��V�^ࣖ��ł��邱�Ɓv��������B �c���肪�Ȃ��̂ŁA�ЂƂ܂���͂����܂��B
�@������ɂ���A���̖{�ł͂��̒��q�����X�Ƃ��đ����̂ł��B�������A��O���������͂��ł����A���|�I�ȗʂ̂����̍D�ӓI�ȏ،����炷��A�܂������Ȃ��o���F�̓��{���������Ƃ�����ł��傤�B
�@�_������O�ł͂Ȃ��A�K���ň��y�ȕ\��Ŗ����Ă����A�Ƃ����L�q�����Ă��܂��B
�@���̂��Ƃ́A�u���쎞��̔_�������͍����̋ɂ݂ł������B�v�Ƃ��������Ƃ������ɔ����Ă��܂��B���ہA�_�����o���F�ł������Ƃ����ؖ����g�}�X�E�X�~�X�i�u���쎞��̔N�v�v����o��1965�j�ɂ���ĂȂ���Ă��܂��B
���v����p��
�@����܂łɗ��j�Ƃ́A���n�ɂ���č��肳�ꂽ���ɑ���N�v�̔䗦�i�܌��ܖ��j�̍�������A�ߍ��Ȏ��D���������Ƃ��Ă���B�������A��ʂɌ��n��1700�N�ȗ��قƂ�Ǎs��ꂸ�A19���I�̒�����ɂ͔N�v��100�N����150�N�O�̍������b�Ƃ��Ă����̂��B���̂悤�ɍ�������Œ肵�Ă�������Ŕ_�Ɛ��Y���͐₦�����サ�A�앨�̎��ʂ����������B���Y���̌���́A�H���̗A���Ȃ��ɁA���̎�����ʂ��ēs�s�l���������ɑ��債�����Ƃ�������炩�ł���B���̈���Őŗ��͒ቺ���Ă���킯������A�_�����ɗ]�肪����ɒ~�ς���Ă��������Ƃ͋^���悤���Ȃ��B���Ȃ킿�A�]�ˎ������ɂ����ẮA�ېł͖v���I�ɂ͂Ȃ��A���ƂƂ��Ɍy���Ȃ����̂ł���B
�����p�I��
�@�_�������͑�������D���Ă����A�Ƃ����̂́A�}���N�X���[�j���́u�K�������j�ρv�̎Y���ł��āA���B�͂����������荞�݂��Ă���̂ł��B�i������A���T�̃e���r�ԑg�u���ˉ���v���������Ă��܂��ˁB�j �ĂсA��������B
���A�[�m���h
�u���{�ɂ́A��߂ɂ���Đ������y�������̂ɂ���Ƃ����A���ՓI�ȎЉ�_���݂���B�N���������ꏭ�Ȃ���炿���悢���A�w�₩�܂����x�l�A���Ȃ킿���X��������@��������A������ɂȂɂ��v������悤�Ȑl���́A�j�ł����ł�������v
�����A���[�E�t���[�U�[�i1889�A�V�C�p�����g�v�l�j
�u���̍��̉��w�̐l�X�́A�V���n�������������܂��܂ȉ��w�̐l�Ԃ̂Ȃ��ŁA�����Ƃ����������Ƃ��Ė����Ȑl�X�ł���v
���x���N
�喼�s��ւ̕����ɂ��āA�������ɐ�G��́u���ɂ���v�Ƌ��Ԃ��A�ނ́A���ۂ̕����V�[���͈�x�����Ȃ������Ƃ����Ă���B�Ƃ����̂́A���O���s�������邩��ŁA�ނ̌���Ƃ���ł͔ނ�́u���̌��͎҂����قNjC�ɂ��Ă��Ȃ��̂���v�ł���A�u�啔���̂��͕̂��R�Ǝd�������Ă����v�B
�܂��X�~�X�勳�̂����Ƃ���ł́A������̍s�_�ސ�h��ʉ߂���̂�2���Ԃ����������A���O���Ђ��܂Â����͔̂�����{�l�Ƃ���ɑ����l�A�ܑ�̏�蕨�ɑ��Ă����ŁA���ꂪ�ʂ�߂�����ł́u�Ђ��܂Â��K�v����������ꂽ���̂Ƃ݂Ȃ��āB�����オ���Ďc��̍s������Ă����v�Ƃ̂��Ƃł���B
�������[�h���t�ق�
�u���{�̏����͈�ʂɁA���N�ł͂�Ƃ����l�q�����Ă����B�v
���c�̖��B�́u�������U�镑���͑傢�Ɋ����ł���A����I�ł���B�v�Ƃ����B�܂�A���{�̏��B�́A���Ȃ��Ƃ������̏������́A�ώ@�҂����ɂ������ė}�����ꂽ��ۂ�^���͂��Ȃ������̂��B
�@���҂́A���̂悤�ɂ����B
������̏����͂��Ă܂��Ƃ��Ă͎O�]�̋�����u����w�v�ȂǂŔ����A�j�ɗꑮ�����ʂ���������������Ȃ����A�����͈ȊO�Ɏ��R�ŁA�j���ɑ��Ă�����������I�ł������悤���B�c������̏��̈ꐶ�͕��Ə����̕ʂ��킸�A���������Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�l�Ɛ��܂�ĉ߂����ɒl����ꐶ�ł������悤���B�ߎS�ȋǖʂ��������悤�Ɍ�����Ƃ���A����͌���l�̖ڂ��炻�������邾���ŁA��������̒m�I�����ł���̂�������Ȃ��B�v �@�c�����A���̒m�I�����Ȃ̂ł��B���̎������̊��o�ŗ��j�f���Ă���̂ł��ˁB�_�����A�������A�����Ђǂ���������Ⴂ�n�ʂ��Ȃ߂��Ă����Ƃ����̂́A�ԈႢ�̂悤�ł��B���̖{�̂ق��̍��ڂɂłĂ��邱�Ƃł����A�q�������ɑ�ɂ���Ă���A����������l�Ɠ����ɂ݂Ȃ���Ă���l�q���`����Ă��܂��B�܂��A�����܂��A����Β��ԂƂ��Ĉ����Ă���i������������قNj����悤�ł��j�̂ł��B����́A���{�l�̕����ӎ��̌���ꂾ�Ǝv���܂��B�i���̖{�ɏ����Ă������̂ł����j���{�l�̕����ӎ��Ƃ����͓̂O�ꂵ�Ă���܂��āA���������܂߂ĕ������Ƃ����̂ł��B�]���āA����q���������ł���͓̂��R�ł����āA���A�_���c�A���ׂĕ����Ȃ̂ł��ˁB �@�܂��A�喼�s��Ȃǂ����ꂪ�I���łȂ���Ύ��ۂ͂��܂��������Ă����悤�ł��B�����āA�喼�����u���傤���˂��Ȃ��v�Ƃ����������ł�����Ƃ₩���͌���Ȃ������̂ł��傤�B�Ȃ�ƂȂ��A�������̍��̊��o�ƍ����Ă���Ǝv���܂��H�����ł��B���N�ɂ킽���č��グ���ċC�����A����ȂɊȒP�ɕς��͂��͂���܂���B���B�́A���[���ƌq�����Ă���̂ł��B
|
 �@�����ƁA�����L���������Ƃ���������̂ł����A�Ō�́A�]�ˊ��̕��i�ł��B �@�����ƁA�����L���������Ƃ���������̂ł����A�Ō�́A�]�ˊ��̕��i�ł��B
�@���̑}�G�́A�u�]�ˋߍx�̒����v�ł��B�O���l�̖ڂɂ͂��ꂪ�A�܂��Ɉꕝ�̊G�̂悤�Ɍ�����̂ł��ˁB������̎��B�̖ڂɂ��A���������܂��B���̕��͋C���A�]�˂𒆐S�ɂ��ăO���W���G�[�V�����ŁA�x�O�܂ōL�����Ă����Ƃ������Ƃł��B
�@�����A�r�b�N�����܂����̂́A�����̈�ԍ����Ƃ���ɂɌ�����G���̂悤�ȕ����ł����A����́u�����͂v�Ƃ����ԂȂ̂ł��B���Ƃ̉������Ԃŏ����Ă���̂ł��B�X��ɂ͓��I�������܂����A���ɂ��A�����݂�����悤�ł��B�����āA����Ƃ̊֘A�t�����ȂǁA�����̏���t�����Ȃ���Ă���̂ł����A���̑��ɁA���̉����̏���B�������A���炭�������ł͂Ȃ�����������Ă���̂ł��ˁB�������X�ɂ킽���āA�ł��B
�@������m�ł͂Ȃ��A�Ⴄ�L��������Ǝv���̂́A�����Ȃ̂ł��ˁB
|
 �@���̑}�G�́A�u�]�ˍx�O�̔_�Ɓv�ł��B �@���̑}�G�́A�u�]�ˍx�O�̔_�Ɓv�ł��B
�@�V�b�h���A�Ƃ����l������ȋL�q���c���Ă��܂��B
�@�u���̓��H�ɖʂ����S���Ƃ͊G�̂悤�ɔ������A�ƂĂ�������_����̗p�r�������̂Ƃ͎v���Ȃ��B�����̂��݂��Ƃ������́A�ނ��덡�܂��Ɋ����ĕЕt���悤�Ƃ��镑�䑕�u�̊G�̂悤�Ȃ̂��B�v
�@���̂悤�ɁA���䑕�u�̂悤���A�Ƃ����������͍]�˂̊X���̕`�ʂ̒��ɂ����������܂��B�����ɂ́A���ƈႤ���_�I�Ȃ�Ƃ�̂悤�Ȃ��̂��������A�Ǝv�킹�܂��B
�@�Ȃ��A�A���̑}�G�̉����ɂ��u�����͂v���A�����Ă��܂��B
�@�����ɉԂ��A�����Ă��āA���ꂪ��r�I��ʓI�ł���Ƃ����������ɂ���ł��傤���B
�@�E�́u�����͂v�̉ԁB |
|
|
18.6.23 | �����ٔ��̎��/���x�j��Y/�o�g�o |
 �@���x�搶�̖{�́A�{���ɒ��g���Z���Ǝv���܂��B���e���̂��̂��Z���Ƃ������Ƃ͂������ł����A���͂ɖ��ʂ��Ȃ��܂����ɓK�ȗp�ꂪ��g����Ă���܂��āA���̈Ӗ��ł��Z�����̂ɂȂ��Ă��܂��B �@���x�搶�̖{�́A�{���ɒ��g���Z���Ǝv���܂��B���e���̂��̂��Z���Ƃ������Ƃ͂������ł����A���͂ɖ��ʂ��Ȃ��܂����ɓK�ȗp�ꂪ��g����Ă���܂��āA���̈Ӗ��ł��Z�����̂ɂȂ��Ă��܂��B
�@�]���āA�ǂލۂɂ͂��̈������ߖ����Ȃ���ǂݐi��ł����Ȃ���Ȃ�Ȃ���ł����A���͍\������ϕ�����₷�����̂ɂȂ��Ă���܂��̂ł��炷��Ɨ������邱�Ƃ��ł��܂��B����ɁA�搶�̕��͂͋����������ŏ����Ă���̂ł����A���ꂪ�s�v�c�Ȃ��炢�ɋ�ɂȂ炸�ɓǂ߂�̂ł��B
�@���āA���̖{�A������Ƃ���ŕG��@���悤�ȓ��e�ɂȂ��Ă���̂ł����A�R�_�قNJ������Ƃ�����L�������Ǝv���܂��B
�P�@�u�푈�Ӎ߁v�Ƃ����A���E�j���O�ɂ��Đ��̒��z
�@�����V�N�A���R�A�y�䂽���q�O�c�@�c���Ƃ����j��ň��R���r�̎��Ɂu����ɂ�������T�O�N�Ӎߌ��c�v�Ȃ���̂��̌����ꂽ�B������Ă̏��x�搶�̘_�ł���B
�@���a�P�U�N�P�Q���W���A���{�͑Εĉp�ɑ��Đ��z�������A�푈��Ԃɓ������B�ĉp�͗����Γ����z���A�����i�d�c���{�j�ƃI�����_�͊��ɑΓ����z�������Ă����B�i���̂悤�ɑ��݂ɐ��z�����邱�Ǝ��̂́A���͏d�v�ł͂Ȃ��A�j���ۖ@�I�ɂ́A���鍑�͐��z���ɂ���đ��荑�Ƃ̊Ԃɐ푈�Ƃ����@�I�ȏ�Ԃ���蓾��B���Ȃ킿����I�Ȑ��z���ɂ���āA���ݓI�ȊW�Ƃ��Ă̐푈��Ԃ��o�������̂ł���B�Ȃ��Ƃ������Ƃ͂��肦���A����͐퓬�O�̍~�����Ӗ�����B
�@�����ŏd�v�Ȃ��Ƃ͑��݂ɔ[���Â��Ő�����̂��Ƃ������Ƃł���B���������ŁA������~���̈ӎv�\�������A������������ɕ��͂��s�g�����Ƃ���A�����ɏ��߂Ĉ���I�ȊW��������̂ł����āA������Ȃ����̂�����ɂ�����\�A�ł���̂��B�푈�Ƃ́A���S�ȑ��݊W�ł���B����̃\�A�͂���ɊY�������A����I�Ȃ��̂ł��邩��푈�@�K�ᔽ�ł���B
�@���̂悤�ȏꍇ�����A��Q�҂Ɍ����Ă̎Ӎ߂Ƃ��⏞���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A���{�̏ꍇ���������܂߂āA���݊W�ɂ���푈�Ɋւ��āA���̏I����Ɉ���������ɑ��ĎӍ߂���ȂǂƂ����K�R���͂��������S���Ȃ��̂ł���B
�@�܂��āA���{�̓T���t�����V�X�R���a���y�т��̌�̌ʋ���ɂ��@�I�Ɋ��S�ɐ��Z���I���Ă���̂ł���B
�@���Ȃ킿�A����c�͂Q�d�̉߂���Ƃ��Ă���̂��B
�@�i���j��̖��𐭎��I�ɕ]������Ƃ����߂���������R�d�̉߂��ł���B�j
�@�Ȃ��A���̂悤�ȋ������Ȃ������B
�@���x�搶�́A��O�̂��镔���i�����̔��̐����q�G�������}�j�ɑ���}���̏�ɁA�����B�̎������~�A�}���}���̗~�]�������Ƃ������ʂł���A�ƒf����B�����āA���̂��ƂŐ�����R�Q�����q�ׂĂ�����B�i�ו��ȗ��j
�@�E�����l�S�̓Ƃ����Ђ��B
�@�E���E�̗��j�ɑS�����{�Ǝ��̉��߂�����ʼn����Ƃ����p�𐢊E�ɂ��炷�Ƃ������B
�@�E�O��I�s�k�B
�Q�@�哌���푈�̊J��Ɋւ�铌���p�@�̕]��
�@�����p�@�ɑ���]���́A�N�ɕ����Ă������Ⴂ�B�ɒ[�ɂ́A�u������ƕ�������Ă���푈���n�߂������v�Ƃ܂Ō����l��������B�������A�푈�ɕ��������w����̐ӔC�͂����Ă��A�J��̐ӔC�͂Ȃ��Ƃ����Ă悢�B�푈�͎Љ�ۂł��邪�A���̂Ƃ��Ă͂��̕��G���䂦�Ɉ��̎��R���ۓI�Ȏ��ۂł��邩�炾�B����ɁA���̐푈�́A���l�D�ʂ̐l��Ό������̊�ቹ�Ƃ��āA���������A�����J���d�|���Ă����푈�ł��邵�A������ŖS�����悤�Ƃ��āA������悤�ȁu������ƕ������Ă���v�푈���n�߂�ȂǂƂ������ƂȂǂ��蓾�Ȃ�����ł���B�����ɂ́A�ԈႢ�Ȃ��u���ɂ̑I���v���J��Ԃ��Ȃ���A���̂��߂ɗǂ���Ɣ��f���Ďn�߂��푈�ł������͂��ł���B
�@�{���Ɏ��̋L�q�B
�@�����p�J�n�������͌R�l�Ƃ��āA�c�A�قƂ�ǒ��ϓI�ɁA�A�����J�̗v�������ăV�i�嗤�S�y������{���R���P�ނ�����ǂ�Ȃ��ƂɂȂ邩�Ƃ������ʂɂ��Ă͍l���Ă����ł��낤�B�����̋��d�Ȉӌ��������w���āA�ނ��D��I�Ȑl�����ƌ���̂́A���̍��ۊW�̔w�i�ɂ��Ă̖��m���炭��Z���ł���B�����ȁu�b���v�ł����������́A�V�c�̕��a�����Ƃ����ӎv�Ɠ��{��ǂ��l�߂鍑�ۊW�̕s�𗝂Ƃ̃W�����}�ŔY�݁A�ꓬ����B
�@�������A����̓A�����J�̋����ȍ��ېL���ӎv�Ƃ͐�ɑ��e��Ȃ��A�k�J�ɏI��ق��Ȃ��ꓬ�������B�A�����J�͂Ƃɂ������{��嗤����r�����Ă��܂������B�������ƂȂ����o�Ă䂩�Ȃ��̂Ȃ�푈�ɑi����Ƃ����̂͊���̐헪�H���������B�����p�I��聄
�R�@�l�ς̕��Ր���ڎw�����u���璺��v
�@���璺��ɂ́A�ڎw���ׂ��l�ςɂ��ċɂ߂ĊȌ��ɏq�ׂ��Ă��܂��B����ւ̍F�{�A�Z��Ԃ̗F�r�A�v�w�̑����A���F�Ԃ̐M�`�A�������Ɣ����A�A�w�C�Ƃ̊��߁A�q�\�̌[���A����̐��A�i�����̗����j�����̓��e�ł��B�����́A�S�Ď������̐S�ɂ�������Ɠ����Ă��܂��B������A�q�ǂ������̓�������Ȃǂŏ��a���邾���Ő������̒����ς��Ǝv���܂��ˁB
�@���ɁA���̒���̉��l��▭�ȕ\���ŏ����Ă��镔����v�܂��B
�@���v�����ېV���Ȃ��ĂQ�O�N��A�ߑ㍑�ƂƂ��ď����x�̐�������i���������P�X�W�O�N�A�����V�c�̋��璺�ꂪ�����ɉ������ꂽ�B����́A���̂Q�O�N�Ɍ`���ꂽ�ڂɌ�����`�ɂ��A����Ό����I�Ȍ��ݍ�Ƃɂ͕K�R�I�Ɍ������Ă���A���_�E�����ʂł̑O�i�̂��߂̎w�j�ł������B���ꂾ���̑匚�ݎ��ƂɁA�{����s���ׂ����ĂȂ������Ă������O�̒A���̑傫�ȋ�₤�̂ɁA���̒��ꂪ�����Ă��镶���̒Z���A�Ȍ����͂���Ӗ��ŋ����ɑ���܂��B
�@����Ɉ˂��Ċς�ɁA���_�̍����Ƃ����̂́A���ʂ��Ȃ��Ă��Ă���ԓI�������Ȃ��Ă��Ă��v�����邱�Ƃ̏o���Ȃ������ȗ�̓����ł����āA���M�̈���ɓ�\�N�]�ɂ킽�鍑�y�E�s�s�E�����̏��{�݂̏[���Ƃ�������Ȏ��̂��ڂ��Ȃ���A�����̎M�ɂ͗B�ꖇ�̎��ЂɋL�������t�ŋύt��ۂ��Ă��܂��A���������s�v�c�ȍ�p�������̂����t�Ȃ̂��Ƃ������Ƃ��ǂ�������̂ł��B���v��I��聄
�@���x�搶�́A���̂��ƁA���̋��璺���V�����A�W�A�̓N�w�ƂȂ��ׂ��Ƃ̒�����Ă���܂��B�ŋ߁A���{�̔��_�𐢊E�Ɍ����čL����ׂ��A�Ƃ����������݂��܂����A����Ȃǂ����̍ʼnE���Ɉʒu�Â�������̂��Ǝv���܂��B�������A���{�����̊@�ɂȂ�Ȃ���Ȃ�܂��c�B
�@
|
|
|
18.6.13 | �����}�u���{�h�v�̑��/���R���Y/�}�K�� |
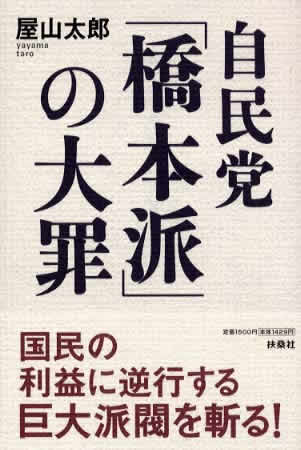 �@���{�������ɂ͓��{���Ȉ�t�A�������1���~�����^�f������A����Ȃ����ɋ߂���ۂ�����܂������A����͌��ǂ���ނ�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�������A���{�l�́i���R�̂��Ƃł����j�ꉞ�݂͂�����̂����f�Ő��E�������܂����B�������A���̂��Ƃ́A�u����1���~�̌��������̂��v�Ƃ������Ƃ��M���M���̌`�ł��F�߂ɂȂ����̂��Ǝ��͎v���Ă��܂��B �@���{�������ɂ͓��{���Ȉ�t�A�������1���~�����^�f������A����Ȃ����ɋ߂���ۂ�����܂������A����͌��ǂ���ނ�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�������A���{�l�́i���R�̂��Ƃł����j�ꉞ�݂͂�����̂����f�Ő��E�������܂����B�������A���̂��Ƃ́A�u����1���~�̌��������̂��v�Ƃ������Ƃ��M���M���̌`�ł��F�߂ɂȂ����̂��Ǝ��͎v���Ă��܂��B
�@���{�������Ƃ����ƁA����6�i�̘r�O�������Ă����邱�Ƃ�A��r�I�[���ȃ}�X�N�ł��邱�Ƃ�A���Č��A���I���Ȃǂ̊O��ʂł��^�t�l�S�V�G�[�^�ƕ]���ꂽ��A�Ƃ������Ƃ���D��ۂ���̂ł����A���ۂ͂��Ȃ�Ⴄ�悤�ł��B
�@������ЂƂ��ƂŌ����A�ꍑ�̑�����b�Ƃ��ĕK�{�̂��̂ł��鋭�łȍ��ƊρE���I���_�Ɍ����Ă���Ƃ������Ƃł���܂��B�i�����Ƃ��A�䂪���ł͂��̖ʂő��۔��������鍑��c����T�����Ƃ�����Ƃ����A�߂����ɂ����ł����E�E�E�B�j
�@
�@���̖{��ǂ݂܂��ƁA���{����͂��̓c���p�h�����[�c�Ƃ��������������������ƈ����p���ł���A�u���v��}��ɂ��āA���������̗���ǂ����߂�Ƃ����S�������邱�Ƃ����Ď�邱�Ƃ��o���܂��B
�@���������ϓ_�����㑍����b�̊�Ԃ���A�c���p�h�ȑO�ƈȌ�Ƃɕ����Č���ƁA���҂ɂ͑�ϑ傫�ȈႢ�����邱�Ƃ�������܂��B
�@�c���p�h�ȑO��k��ƁA�����h��A�r�c�E�l�A�ݐM��A���X�R�A���R��Y�A�g�c�E�E�E�ƂȂ�̂ł����A�����̕��ɂ́A���ꂼ��ɋ��̒��������̊o��������č��Ƃ̑ǎ��������Ƃ�����ۂ��܂��B�Ⴆ�A���Ĉ��ۏ��Ɋւ�����g�c�A�ݗ��̔��f�͂Ǝ��s�͂ɂ͐[�����h���o����قǂł��B
�@�Ƃ��낪�c���p�h�Ȍ������ƁA�O�A���c�A�啽�A��A���]���A�|���A�F��A�C���A�{��A�א�A�H�c�A���R�A���{�E�E�ƂȂ�̂ł����A�啽����������Ă��ꂼ��̌o���ɂ��čŏ��Ɏv�������Ԃ̂́A�܂����_�Ȃ̂ł��ˁB
�@���̗��҂̍��قƂ����̂́A���Ƃ̉^�c�ɋ��߂���u���v���ŗD��ɂ������f��̃Z���X�̗ǂ������ł���Ǝv���܂����A�c���p�h�Ȍ�̕��X�ɂ͂��ꂪ�����Ƃ������ɒ[�ɂ͌��@���Ă���Ƃ悤�Ɋ����܂��B
�@���{����ɂ��Č����A�ΒB���i�Ђ���܁j�ɂȂ��čs�������v�����Ƃ�����Ŕ������Ɏv���N�����܂����A���ǂ͋c���i�������܂ށj�⊯���̃G�S�ɕ����Ă��܂��ĉ����o���܂���ł����B�����Ƃ��A�������������܂�ɂ������ɂ܂݂�Ă��܂��Ă��邩��A���̑̎���ς��邱�ƂȂǏo����͂����Ȃ������ƌ����ėǂ��̂ł��傤�B
�@�܂��A�O���̖ʂł��i���̒[���ȊO���ɔ����āj�z�Ƃ����Ƃ���͂���܂���ł����B�y���[��g�ِl�������ł̓A���p�����^�Ԉʂ̂��Ƃ������Ȃ��������i�t�W�����哝�̂Ƃ̍��͌��Ƃ����ۂ�ł����j�A�����̏��������ɂ͗��߂Ƃ��Ă��܂����A���������Ɲ��������悤�ȎӍߊO�������o���Ȃ��������A�E�E�E�܂��������]�̌���ł��B
�@�������A���{����ЂƂ肪�����̂ł͂Ȃ��A���̊�ʂɕs�ލ����Ȍ��͂̍��ɂ��Ă��܂�������c���⊯���B����Ȃ闘�ȒNj��W�c�̑��݂����̌����ƌ�����ł��傤�B�i�������A������Ƃ����đ����Ƃ����n�ʂɂ����҂����̐ӔC�͂܂ʂ��꓾����̂ł͂���܂���B�j���̗��ȒNj��W�c�̒�����绂Ƃ����̂͂�͂�c���p�h��_�Ƃ��Đ����������{�̓T�^�I�Ȏp�Ȃ̂����m��܂���B
�@�e�X�̍K���̒Nj��͏����̃��x���ł���Ζ��͏������̂ł����A���Ɖ^�c�ɔC����l�����������ł���̂͐��Ɏc�O�Ȃ��Ƃł��B
�@�������F���������u�^�̃G���[�g�v�̏o�����{���ɖ]�܂�܂��B
�@�i���̓_�A�O��́u���F���Y�v�Ȃǂ͐^�̃G���[�g�Ƃ����ėǂ��ł��ˁB�j
|
|
|
18.6.6 | ���F���Y�@��̂�w�������j�^�k�N���^�u�k�� |
 �@���͂���܂ŁA���F���Y�Ƃ������O�Ɣނ̌��t�w�u���Ɍ��Ă���v�g�C�t�C���}���X�x�����m��܂���ł����B���̖{��ǂ�ŁA�������{�l�������Ƃ������ƁA��̊������̂f�g�p�̉��\�Ƃ���ɗ������������{�����������Ƃ�m��܂����B �@���͂���܂ŁA���F���Y�Ƃ������O�Ɣނ̌��t�w�u���Ɍ��Ă���v�g�C�t�C���}���X�x�����m��܂���ł����B���̖{��ǂ�ŁA�������{�l�������Ƃ������ƁA��̊������̂f�g�p�̉��\�Ƃ���ɗ������������{�����������Ƃ�m��܂����B
�@���F���Y�͖����R�T�N���݂̈����s�̑�x���̉Ƃɐ��܂�P�X�ŃP���u���b�W��w�ɗ��w�B��̊�������Ɋ|���ẮA�g�c�Ɍ����܂�āA�����A���{��w�����Ă̊�������܂����B�ǂݏI����āA���҂����Ƃ����ɋL���Ă���悤�ɁA���q���̉f������I������悤�Ȋ��o���c��܂��B����قǁA�D�u�Ƃ����~���̂Ȃ����ɔ����������������Ă���̂ł��B
�@��̊������A���{�̓G��GHQ�A�Ƃ�킯�����ǂł����B�i���Ȃ݂ɁA�u�����ǁv�͓��{�Ɠ��̎��ȋ\�Ԃ̖|��ł��āA�p��ł�Goverment
Section�ł�����u�����ǁv�����̂�ǂ�����킵�Ă��܂��B�j�@���̋ǒ��̓z�C�b�g�j�[�y���A�����̓P�[�f�B�X�卲�ł��āA�P�[�f�B�X�卲�Ɏ����Ă͖{���ł̃j���[�f�B������ɐ��܂��Ă���A���{�Ƃ����^�����ȃL�����p�X�ɂ��̃j���[�f�B����W�J���悤�ƒ�����ė��������l���ł��B���҂Ƃ��o�g�ٌ͕�m�ł��āA���{�Ƃ��Ă͑�ϖ��f�ȂQ�l�ł����B
�@���́u�����ǁv�̃J�E���^�[�p�[�g�Ɉʒu�����̂��I��A�������ǁi�I�A�j�ł��āA���{�Ƃf�g�p�̊Ԃ̐Ղ��s�Ȃ����߂ɐV�݂��ꂽ�����ł��B���̎Q�^�Ƃ��āA�g�c�Ɍ����܂�āA���Ԑl�ɉ߂��Ȃ����F���Y�����̏d�ӂ�S�����ƂɂȂ�����ł��B����������w���͂f�g�p���甭�������ł�����ɂ߂ďd�v�ȕ����ł�������ł��B
�@GHQ�͌��E�Ǖ��Ƃ������͂ȕڂ��g���Ȃ���A���{��U��Ɋ|�����Ă��܂��B����ɑ��āA���h�Ȃ̂́A�u�푈�ɕ����������ŁA�z��ɂȂ�����ł͂Ȃ��v�Ƃ������F���Y��̃X�^���X�ł��B���ۂɐg�ɍ~�肩�����Ă���̕����Ȃ���̂��̌��t�ł��B����Ƃ́A�����Ȃ̂ł��ˁB�Ȃ�ƂȂ��F�D����ꂾ����ƁA�����l�̌��t�����̂܂ܕ������A�Ƃ������̑����̐����ƂƂ͂܂������_�D�̍��ł��B
�@�`���́w�u���Ɍ��Ă���v�g�C�t�C���}���X�x�Ƃ������t�́A���@�����i�����t���j�̍ۂ̌��t�ł��B�����́A���{�Ǝ��ĂŌ��@����낤�Ƃ���̂ł����A�ČR�̎�ɂ���ēK���ɍ쐬���ꂽ���@���A�V�c�̂��g�����J�[�h�ɂ��Ĉ��܂���Ă��܂��̂ł��B
�@���̕ӂ�̌o�܂�m��A�ꕔ�w�҂Ȃǂ̈ӌ��ɂ���悤�ɁA���̌��@�͈�U�j�����Ă��܂��ׂ��ł��傤�B
�@�܂��A���̒��Ɍ��@�w�҂Ƃ����l���������݂��i���������Γy�䂽���q�Ƃ����l�����@�w�҂Ƃ����G�ꍞ�݂ł����j�A�T�ˌ쌛�������Ă����܂����A�܂��ƂɃP�b�^�C�Ȃ��Ƃł��B
�@�@�i�Ȃ��A���ڊW����܂��A���̌��@����v���W�F�N�g�����u�^��̎����v�Ƃ����̂͏��߂Ēm��܂����B�O�����~���[�̖��ȂƓ���ł����A����Ɠ��{�̖��Y�ł���^��Ƃ������|�����̂ł��傤���B���Ȃ݂Ɏ��̓O�����~���[�̃t�@���ł��B�j
�@���F���Y�́A�ʏ��Y�ƏȂ𗧂��グ�A�����̊�Ղ��m�����܂��B�Ȃ݂��鐭���Ƃ⊯�������������Ă̂��̐��ʂł�����A���̗͕͂����̂��̂ł͂���܂���B�����āA�ʎY�Ȃ��O���ɏ��ƁA�����Ɛg�������A���͓��k�d�͂̉�Ƃ��đ�����J���̎w�����Ƃ�A������ғ������܂��B���̂悤�ɂ��āA��̏����̐����I�����̌�́A�o�ς̖ʂł܂��ɓ��O�Ɍ����Ă̑Ԑ�����������̂ł��ˁB
�@�����āA�Ō�̃G�s�\�[�h�́A�g�c�̐��s�Ƃ��ĎQ�������T���t�����V�X�R�u�a��c�ł̂��Ƃł��B�O���Ȃ�GHQ�ɂ����˂��č쐬�����p���̋g�c�������e���������F���Y�́A�K���ɒ�R����O���Ȃ̔����������āA���̒��O�ɓ��{��ŏ����������̂ł��B�܂��ɉ����̒��O�ɍ�Ƃ����A�����ɏ������������܂��܂��ŁA���͂����炯�̌��e�ɂȂ����Ƃ����ł����B
�@�O���Ȃ́A�������ς��ʔڂ����S��Ƃ�����M���M���ŕς��������j�́u�v�����V�v���v�Ƃ̑Δ䂪�ۗ�������i�������ɂ���܂����B
�@���̂悤�Ȃ������悢�l���́A���ɂ͑S�����s�s�\�Ȃ��̂ł��B�������A�����͂܂˂������ł����A�����͋߂Â������Ǝv���܂��B
�@�����āA�����ЂƂB
�@���B�́A���̂悤�ȗ��j��傫�Ȗ�������������l�B�̂��Ƃ����Ȃ��Ƃ��m��ׂ��ł��B����Ȍ������ł����A���Ȃ��Ƃ��m���Ă���������ׂ����Ǝv���܂��B
|
|
|
18.4.1 | ��������������u��������ځv�A�u���j������ځv�^�����z���Y�^���v�� |
| 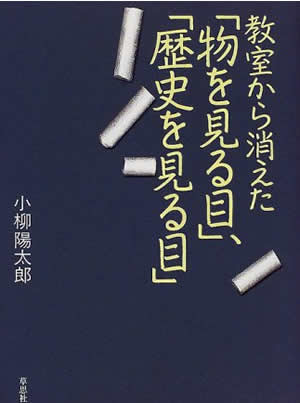 �@���҂͑吳�P�Q�N(1923)���܂�B �@���҂͑吳�P�Q�N(1923)���܂�B
�@���啶�w���|�w�k�o�w�|��啶�w���|�C�Q�ٍ��Z���@�|��B���`�Z����w�����E�E�E�Ƃ������o���ł��B��O�E�풆�E���ƁA��������Ɠ��{�����Ă��ė���ꂽ��ł��āA���̖{�ł͓��ɋ��番��̌�����ωs�����͂���Ă��܂��B�������������̂́A�u���E���ꂽ�����A�c�߂�ꂽ�ÓT�v�̍��ł���(24p)�B
�@�u�V�w�����n�܂��āA���㍑��̋��ȏ�����ɂ���ƁA�����S���ɂނ̂́A�����ɂ��\�L�̂��܂�ɂ��Ђǂ��������Ԃ�ł���B�v�Ɏn�܂�܂��B
�@�f���炵�����͂��ڂ��Ă��Ă��A�u�����ɗp����ꂽ�����́A��ɂ���đ啝�ɍ폜����āv����A���ՂɂЂ牼���ŕ\������Ă���A�Ƃ������Ƃł��B
�@���Ƃ��A�u�w��������x���w�����x�Ƃ������͎g���āv���炸�A���ꂪ���Ď�������Ƃ������Ƃ炵���̂ł����A�u�ނ��낱�̓��Ď��̒��ɂ�������ꂽ�������������k�̐S�ɍ��ނׂ���ȋ��ނł͂Ȃ����B�v�A�u�ق̂��炭���������Ă����[���̏�i�����݂������Ƃ炦���w�����x�Ƃ�������ɁA�w��������x�Ƃ�����܂ƌ��t�����Ă��@�ׂȂ���������A�����ł͂��������ʗp���Ȃ��B�v�Ƃ�������Ă��܂��B
�@���̑��ɂ������̗�������Đ���������A���̖��͒��ړI�ɂ́u���p�����A��p�����v�ɂ�鐧��Ƃ����_�ɂ���̂ł����A���̍��{�ɂ͋���E�ɂ���l�����̐S�ɂ���A�u�ُ�ȕ������o�A�����ƒ[�I�Ɍ����Ήߋ��̕�����Y�ɑ���O�ꂵ�����������v�Ƃ̎w�E�Ȃ̂ł��B
�@�{���́A���T�Ȃ�Ȃ��悤�Ɂu���S�̔z���v�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ɁA�u����I�z���̂��ƂɁv����y�ɕύX����A����̍����ł���ׂ��u�����̌p���v�����Ȃ��Ă��܂��Ă���̂ł��B
�@
�@�Ȃ��A�����Ȃ�̂��B
�@����́A�����炭�u����̂��߂ł���A�ߋ��̕����ɏ��X��������邮�炢�͋������B�v�Ƃ����A�{���Ƃ͋t�̋���ׂ��l�������������Ă��邩�炾�A�ƒ��҂͎w�E���܂��B
�@�ł́A���́u����I�z���v�Ƃ͉����B
�@�[�I�Ɍ����āA�q���ւ̂����˂�ł��B�����K���̕��S���y�����Ă��������E�E�E�ȂǂƂ����l���Ȃ̂ł��B����������u�����Ɏq����K��������̂ł͂Ȃ��A�q���ɕ�����K��������Ƃ�������ׂ��������o�v�Ȃ̂ł��B
�@���̂��Ƃ͍��ꋳ��ɂƂǂ܂炸�A���a����Ə̂��Đ푈��P�Ɉ��ł���Ƃ��A��l�B�̑����w�͂�Ɛт�ے肵����A���{�̗��j��A��ɏd�v�Ȗ������ʂ����Ă���ꂽ���V�c�̎��Ղ��������A�����v����ɁA�ߋ��̕���������̔��f�ō��E�ł���Ƃ�������ғƓ��̊��o�A�܂�͘����̕\��Ȃ̂ł��B
�@���҂́A����ɓ��l�̗�������A����̎S��������A�Ō�ɂ��̂悤�ɓZ�߂Ă����܂��B
�@�u�����ɋ��ʂ��Č����錾��ς́A���t�Ƃ��̌��t���Ӗ����鐸�_��ʂ��čl���悤�Ƃ��錩�����ƌ�����B�u�i�Ⴆ�A�\�������@�́j�a���Ȃ��đ����ƂȂ��v���u�������ɂȂ��悭����v�Ƌ��ȏ��ɏ����Ă��A�\���͕ʂł��������e�������Ƃ����l�������B�i�����̎�����߂��v�������S�ɍӂ��Ă��܂����A�����̂����t�̂���ׂɐe���ނƂ������Ƃ������Ȃ�B�j
�u������A�����w�Ȃ�x���w������x�Ə������Ƃ��A�����Â��Ȃ���������`����������悢�ł͂Ȃ����Ƃ������ƂɂȂ�B�v
�@�u���{�̒��������̓`���ł́A���t�Ɛ��_�A���Ȃ킿�A���Ǝ��Ƃ́w�R�g�x�Ƃ������t�ɂ���ĕs���̊W�ɗ����Ă���ƍl���Ă����B�]���Đ��_��b���邱�Ƃ́A���t��b���邱�Ƃł���A�l�X�͌��t���ƂƂ̂��邱�Ƃɂ���Đ��_��b���Ă����̂ł���B�����A���̂悤�Ȍ��t�ɑ��錵�l�ȑԓx��������A���t��P�Ȃ�ӎv�`�B�̋L���ƍl�����Ƃ��A�����ɐl�̐S�����サ�A�����ďd�݂������Ă��܂������B�v
�@�u���ُ̈�ȕ������o�A�����Ȃ������g���S�Ă��܂߂āA����Ɍg���҂̐S��I�݂���ߋ��ɑ���������A����ɍ��ꂩ�甽�Ȃ������Ȃ�����A����E�̐����͂Ƃ��Ă��]�ނׂ����Ȃ����Ƃ�m��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v
�@�u���t�v�Ƃ����̂́A�{���ɕs�v�c�ȑ��݂ł��B�܂��Ɂu����v�Ƃ������t��������҂�����\���Ă��܂��B
�@�p�X�J���́u�l�Ԃ͍l���鈯�ł���v�Ƃ����܂����B�����āA�u�l�������t���̂��́v�Ȃ̂ł�����A�u�l�ԂƂ͌��t�Ő��藧���݂ł���v�Ƃ����Ă��ǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@���̌��t���A��������o���オ�������̂ł͂���܂���B����N�̎��Ԃ�ςݏd�˂āA�s�K�Ȃ��͓̂�������A��������Ē��Ă���̂ł��B�@���҂̌����u�����v�Ȃ̂ł��B���̂��Ƃ𗝉��������ɁA�����݂̐ȍl���������ŕς��Ă��܂����Ƃ��Ă���̂��A����Ȃ̂ł��B
�@����́A���v�����Ԗ^�Ɏ��Ă��܂��B
�@�܂��ɁA������ʉߋ��Ɩ����̓��{�l�ɑ�������ł͂Ȃ����Ǝ��ɂ͎v���܂��B
�@���v�ƌ�������̂��A����ɂ���`���I�Ȃ��̂��m�ۂ�����ŁA�K�v�ȏC����������Ƃ����̂Ȃ�ǂ��B�������A���ɂ́A�����̎p���`���Ȃ��܂܁A�����P�ɂԂ��A�Ƃ����Ă���悤�Ɏv���܂��B
�@���҂������Ƃ���邱�ƂƓ����ł���A�Ǝv���܂����B
�@�c���̊ϔO�̌��@�̂Ȃ���ƂȂ̂ł��B �@�ȏ�̂ق��̕����ł��A��ϓ��e�̔Z���{�ł���܂����B
�@����ɁA���͂����������Ƃ��Ă���A���ʂ�����܂���B
�@�{���ɗǂ��{�ł����B
|
|
|
18.3.22 | �c���Ƃ͍����^�������F�^�u�k�� |
|  �@�����搶�̐��M�W�ł��B���x�X�g�Z���[�́u���Ƃ̕i�i�v�̌��^�ɂ�����{�̂悤�ł��B �@�����搶�̐��M�W�ł��B���x�X�g�Z���[�́u���Ƃ̕i�i�v�̌��^�ɂ�����{�̂悤�ł��B
�@���͂���ϓǂ݂₷���̂́A�䗼�e�̉e��������̂��낤�Ǝv���܂��B�䗼�e�́A��Ƃ̐V�c���Y�Ɠ����Ă��B���́A�����Ă���m��܂���ł������A���B�����グ�̍ۂ̑̌��k��{�ɂ���Ă���i�u����鐯�͐����Ă���v�j�A�x�X�g�X���[�ɂȂ��������ł��B
�@�����搶�́A���ꋳ��̏d�v���ɂ��ė͐�����Ă���܂����A���̌䗼�e�̌�O���A���g�̐��w�҂Ƃ��Ă̌o����ʂ��ē���ꂽ�䌋�_���낤�Ǝv���܂��B�����S���^�����܂��B�����搶��������u�v�l�v�Ɓu��v�ɕK�v�s���Ȃ̂��u����i���t�j�v�Ȃ̂ł��B
�@
�@�`���ɏ����܂����悤�ɁA���̖{�́u���Ƃ̕i�i�v�Ƃقړ��l�̓��e�ɂȂ��Ă��܂����A�S�̖̂�3���̂P�ɂ킽���ď����ꂽ�u���F�ĖK�L�v����ϖʔ��������B���ɁA�Q�O���I�O������́A���B��ɂ����A���E���E�I�E�Ă̍R���j�͔��ɕ�����₷���܂Ƃ߂��Ă���A�Q�l�ɂȂ�܂����B
�@�������A�c�O�Ȃ̂́A���F���ρE�x�ߎ��ς̍��̓��{�i�֓��R�ɑ�\�����R���j������I�ɁA���Ƃ��đ����Ă�����_�ł��B����́A���̖��F�����グ�Ƃ����̌������̔w�i�ɂ�����̂Ǝv���܂����A�����ٔ��j�ς̉e�����Ă����A���ꂪ�@�������Ă��Ȃ��悤�Ɏv���܂��B
�@�����v���܂��̂́A�������Ɍ��ʓI�ɂ͌����������낤���A���������悤�Ƃ����w�͂��������낤���A�܂������ł��Ȃ�����������������낤�A�Ƃ������Ƃł��B���������ʂɂ��ڂ������A����Ă��炢�����Ȃ��A�Ǝv���킯�ł��B
�@���������A�킪�����ɑ���u�M���v�������Ă��ǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���A�Ƃ������ƂȂ̂ł����A�������ł��傤���B
�@�u���Ƃ̕i�i�v�������ł������A�����搶�̂��l���ɂȂ��Ă���u���Ɓv�u�c���v���A���̍l�����Ƃǂ��������Ɍq�����Ă���̂��A�����^��Ɋ����Ă��܂��B
|
 �@�ŏ��Ɏʐ^�̏Љ�ł��B���̎ʐ^�͏o���O�A���̎}����Ɏ����āA������ɓ����Ă��镗�i�ł��B�݂������܂��B
�@�ŏ��Ɏʐ^�̏Љ�ł��B���̎ʐ^�͏o���O�A���̎}����Ɏ����āA������ɓ����Ă��镗�i�ł��B�݂������܂��B


 �@�y���[�̉Y�ꗈ�q�ȗ��A�����̐��m�l�����{�ɂ���Ă��܂����B
�@�y���[�̉Y�ꗈ�q�ȗ��A�����̐��m�l�����{�ɂ���Ă��܂����B �@�����ƁA�����L���������Ƃ���������̂ł����A�Ō�́A�]�ˊ��̕��i�ł��B
�@�����ƁA�����L���������Ƃ���������̂ł����A�Ō�́A�]�ˊ��̕��i�ł��B �@���̑}�G�́A�u�]�ˍx�O�̔_�Ɓv�ł��B
�@���̑}�G�́A�u�]�ˍx�O�̔_�Ɓv�ł��B
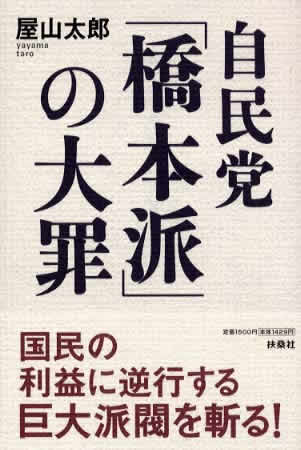 �@���{�������ɂ͓��{���Ȉ�t�A�������1���~�����^�f������A����Ȃ����ɋ߂���ۂ�����܂������A����͌��ǂ���ނ�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�������A���{�l�́i���R�̂��Ƃł����j�ꉞ�݂͂�����̂����f�Ő��E�������܂����B�������A���̂��Ƃ́A�u����1���~�̌��������̂��v�Ƃ������Ƃ��M���M���̌`�ł��F�߂ɂȂ����̂��Ǝ��͎v���Ă��܂��B
�@���{�������ɂ͓��{���Ȉ�t�A�������1���~�����^�f������A����Ȃ����ɋ߂���ۂ�����܂������A����͌��ǂ���ނ�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�������A���{�l�́i���R�̂��Ƃł����j�ꉞ�݂͂�����̂����f�Ő��E�������܂����B�������A���̂��Ƃ́A�u����1���~�̌��������̂��v�Ƃ������Ƃ��M���M���̌`�ł��F�߂ɂȂ����̂��Ǝ��͎v���Ă��܂��B �@���U�P�N���o�߂������N���܂�������������ɂ��āA�e���r���͂��߂Ƃ���}�X�R�~����������i�����j�藧�ĂĂ��܂��B���̃e���r�ԑg�̈�����Ă���܂�����A�`����ƂƂ���i��Y�ɂ��ꂽ�L�c�O�B���̂����������_�Ђւ̍L�c���̍��J�i�������j�ɂ��āA�u�������玖�O�ɍ��J�̘A���͂Ȃ������B������Ă���Βf�����v�܂��u�����͌R�l���v�҂��Ղ�Ƃ���v�ł���A���O�ɍ��J��Őf����Ă���u�c���͌R�l�ł���v�҂ł��Ȃ��B�����⊙�q�̂�������Q�肷��Ώ\���������߂Ă��������A�ƒf�������낤�v�ƌ���Ă����܂����B
�@���U�P�N���o�߂������N���܂�������������ɂ��āA�e���r���͂��߂Ƃ���}�X�R�~����������i�����j�藧�ĂĂ��܂��B���̃e���r�ԑg�̈�����Ă���܂�����A�`����ƂƂ���i��Y�ɂ��ꂽ�L�c�O�B���̂����������_�Ђւ̍L�c���̍��J�i�������j�ɂ��āA�u�������玖�O�ɍ��J�̘A���͂Ȃ������B������Ă���Βf�����v�܂��u�����͌R�l���v�҂��Ղ�Ƃ���v�ł���A���O�ɍ��J��Őf����Ă���u�c���͌R�l�ł���v�҂ł��Ȃ��B�����⊙�q�̂�������Q�肷��Ώ\���������߂Ă��������A�ƒf�������낤�v�ƌ���Ă����܂����B �@���x�搶�̖{�́A�{���ɒ��g���Z���Ǝv���܂��B���e���̂��̂��Z���Ƃ������Ƃ͂������ł����A���͂ɖ��ʂ��Ȃ��܂����ɓK�ȗp�ꂪ��g����Ă���܂��āA���̈Ӗ��ł��Z�����̂ɂȂ��Ă��܂��B
�@���x�搶�̖{�́A�{���ɒ��g���Z���Ǝv���܂��B���e���̂��̂��Z���Ƃ������Ƃ͂������ł����A���͂ɖ��ʂ��Ȃ��܂����ɓK�ȗp�ꂪ��g����Ă���܂��āA���̈Ӗ��ł��Z�����̂ɂȂ��Ă��܂��B �@���͂���܂ŁA���F���Y�Ƃ������O�Ɣނ̌��t�w�u���Ɍ��Ă���v�g�C�t�C���}���X�x�����m��܂���ł����B���̖{��ǂ�ŁA�������{�l�������Ƃ������ƁA��̊������̂f�g�p�̉��\�Ƃ���ɗ������������{�����������Ƃ�m��܂����B
�@���͂���܂ŁA���F���Y�Ƃ������O�Ɣނ̌��t�w�u���Ɍ��Ă���v�g�C�t�C���}���X�x�����m��܂���ł����B���̖{��ǂ�ŁA�������{�l�������Ƃ������ƁA��̊������̂f�g�p�̉��\�Ƃ���ɗ������������{�����������Ƃ�m��܂����B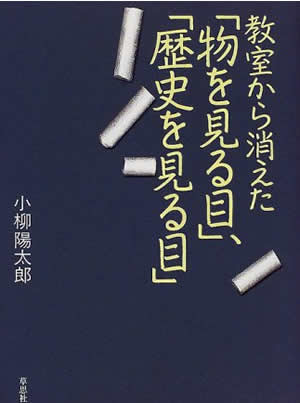 �@���҂͑吳�P�Q�N(1923)���܂�B
�@���҂͑吳�P�Q�N(1923)���܂�B �@�����搶�̐��M�W�ł��B���x�X�g�Z���[�́u���Ƃ̕i�i�v�̌��^�ɂ�����{�̂悤�ł��B
�@�����搶�̐��M�W�ł��B���x�X�g�Z���[�́u���Ƃ̕i�i�v�̌��^�ɂ�����{�̂悤�ł��B