 なにかの書評で、推薦されていたので読んでみました。 なにかの書評で、推薦されていたので読んでみました。
著者の保阪氏に対する、これまでの私の評価はどちらかというと低かったのですが、読み終わって、やっぱりねぇという印象が強まりました。再評価の結果は最低ラインです。それに文章があまり上手ではありません。今後、この人の本は読みません。
この本のテーマは、ひとことで言えば、「特攻とは、軍(=国家)という悪の機構が、学徒兵に死を強要したものである。」というものであろうと思われます。
特攻という「死」に直結した行為を命令する訳ですから、確かに「死を強要した」と言えるでしょう。しかし、それだからといって命令者側を責めることができるでしょうか。中には、不適当な指揮官がいたでしょうが、大方の指揮官は苦悩のなかでそういう命令を発したのであって、大西中将が言うように「特攻は統率の外道である」という認識はあったものと思います。(ただ、戦争という異常事態の中でそれが麻痺していったこともあるかもしれません。ただし、それをもって私達はそれを責めることはできないと思います。)
それなのにこの著者をはじめとする後世の多く人は、旧軍指揮官は人間性が非常に欠けており、人命のことなど考えないまさに外道の集団であった、とそういう感じ方をしています。
本当にそうでしょうか。
著者は、軍指揮官(=国家)を被告、特攻出撃者を原告として、自らは裁判官という高みに立って「第3者として」被告を断罪しています。物理的に高所に立っているというだけでなく、あの時代の情勢というものからも離れたところに立って判断をしているように見えるのです。さらに言うならば、自分自身も当事者の方々と血が繋がっており、考え方も繋がっているのだという自覚もないように思えます。「第3者として」と書いたのはそういう意味です。
特攻出撃者の遺書などを読んで涙したということを随所に書かれておりますが、その気持ちが指導者側にほとんど向けられていないのが、私には不思議な気がします。
以下気についた箇所についての感想です。
「彼らは国家のために、天皇のために、そして国民のためにその生を捧げたと説く人たちがいる。なんという非礼な解釈であろうか。なんという無責任な理解であろうか。(6p)」
→著者は、特攻隊員は実際のところ国家を批判しながら不本意のうちに死んでいった、ということを言いたいようです。その事例として特攻出撃者の遺稿に書かれたことなどを例示しています。しかし、私は、それらは「部分」に過ぎないのではないかと思うのです。中には、最後までそういう考えの方もいたでしょう。しかし、ほとんど特攻隊員は我々が安易に想像出来ないような非常な苦悩の中を自分なりの結論付け(価値付け)をして出撃して行った。多くの遺書からは、そう読み取れると思います。
ところが著者は、そういう制約の中に国家があるいは軍指揮官たちが、押し込めて行って死を強要したのだ、だから特攻隊員は涙して語るべき哀れな被害者なのだ、という言い方をしています。
著者には時代というものに思いが至っていないのではないかでしょうか。当時は死に対する考え方が今とは全然違うのです(よしあしを言っているのではありません)。武士道について書いた葉隠れという本があります。「武士道とは死ぬことと見つけたり。」というあれです。葉隠れでは、死よりも高い価値のものがある、死を恐れて無様(ぶざま)なことにならぬように、また、その覚悟で日々事に当たれ、というようなことが書かれています。今の私達日本人はこれと全く反対の価値観の中にあり、一方、特攻が行なわれたあの時代には、この考え方が、むしろ色濃くあったといえます。そういう価値観であった時代のことを、それと全く反対の今の価値観で評価するのは明らかに間違っています。
再び記しますが、特攻隊員は私達が経験したことのないような苦悩の中で自分達なりの決心をして命を捧げた方々なのです。著者は、そう考える私達を非礼であるとか、無理解であるとか言うのです。著者の方こそ非礼であると私は思います。 「特攻作戦は個人に対する国家の犯罪行為である。何のいわれも無く死刑を命じているからである。(133p)」
→なんと無情な言い方か。戦争は、運命共同体としての国家の存亡をかけて国民がこぞって戦ったものです。特攻の発想は必ずしも戦争指導部側にあったのではありません。回天という特攻兵器がありましたが、これについて言えば戦争末期、呉工廠に多量に保管してあった長魚雷を見ながら現場の(たしか)中佐くらいの者が発想したものであるといわれています。いずれにせよ、このように上下の阿吽(あうん)の呼吸で考えられていったという状況が当時はあったのだと考えるのが普通ではないでしょうか。あのような苦しい戦局の中、起死回生の戦法として、葉隠れの精神の流れを汲むあのときのほとんどの日本人は上下の配置、階級など関係なしにそれを発想したのだと私は思います。 「あのヒトラーでさえ体当たり攻撃の命令をくだしたことはないという。むろんヒトラーにはそれよりもはるかに重い非人間的な所業は多いが、人間特攻を命じることの罪の重さは自覚していたと言うべきだろう(174p)」
→ついにここまで言う。要するに、数百万の全く無辜の人々を惨殺した、あの非道のヒトラーよりも悪いというのです。おまけに、そういうことをしたヒトラーは人間特攻の罪の重さを自覚していたというのですね。笑止千万。著者は本一冊をかけて、「特攻」という非常に重い問題について「日本人」との関連を踏まえて思索を深めていたはずなのに、この軽さ。肩透かしを喰らったようです。 この本の最後の部分で再び暗然とした気持ちになります。書き起こすのも面倒ですが、こういうことが書いてあります。
「あえて結論とするが、次の三点を中軸に据えて、特攻隊員の真情を理解すべきと思う。
(1)特攻隊員は、特に学徒出身の特攻隊員は、こういう理不尽な作戦に当事者として反対であった。反対であったから、彼らは自らの肉体を爆弾としてアメリカ軍の艦艇に体当たりして行った。(もし賛成であったら、彼らはと週で特攻隊員としての訓練を積むことは出来なかっただろう。自分ではなく、他人にこの役を押し付けようと謀ったに違いない。)
(2)彼ら特攻隊員は戦争指導にあっている軍事指導者に心底からの怒りを持っていた。(そんなことは誰も書いていないという反論があるだろう。しかし彼らの遺書や手記に戦時指導者についての信頼も不信さえ書いていないということ自体が、信頼していないことのなによりの証なのである。‥略‥)
(3)特攻隊員は臣民から「神」と扱われることで、軍事指導者への怒りとともに臣民に対しても抜きがたい不信をもって体当たり攻撃をしていった。(彼らを特攻という狂気にも似た戦術の歯車に仕立て上げた臣民の責任もまた大きいことになる)」 私は、全く反対であったと思いますね。
もう、申しあげる言葉がありません。
| 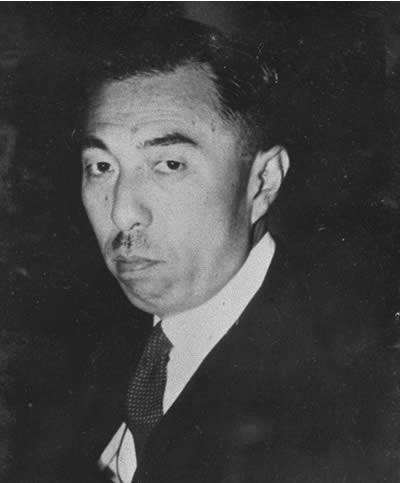 驚くべき内容の本でした。
驚くべき内容の本でした。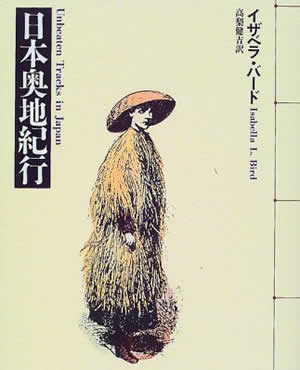 イザベラ・バードは1879年(明治11年)春、サンフランシスコから横浜に到着しました。
イザベラ・バードは1879年(明治11年)春、サンフランシスコから横浜に到着しました。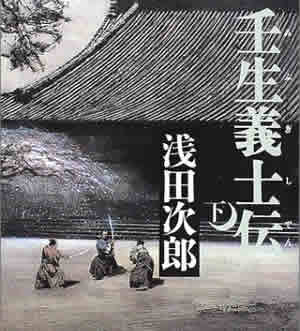 一言で言えば、大変面白い小説でした。
一言で言えば、大変面白い小説でした。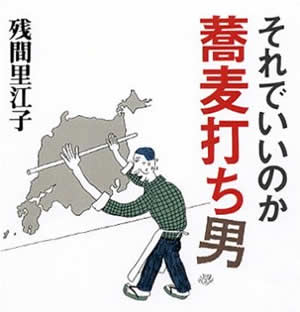 私も蕎麦打ち男の端くれですので、この題名に惹かれて読んでみました。 ここでいう蕎麦打ち男とは、団塊の世代を指しており、この世代の男たちが蕎麦打ちや陶芸やNPO活動に、いわば逃げ込んでいるということをおっしゃっているのですね。
私も蕎麦打ち男の端くれですので、この題名に惹かれて読んでみました。 ここでいう蕎麦打ち男とは、団塊の世代を指しており、この世代の男たちが蕎麦打ちや陶芸やNPO活動に、いわば逃げ込んでいるということをおっしゃっているのですね。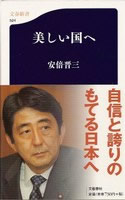 「美」について、本来日本人は大変敏感であると思います。であるのに、そこから目をそらして、美しくない言動をとる日本人が増えているように思われます。この本では、そのことについて「損得だけで判断してよいのか?」という問いかけが随所で読者に投げかけられております。
「美」について、本来日本人は大変敏感であると思います。であるのに、そこから目をそらして、美しくない言動をとる日本人が増えているように思われます。この本では、そのことについて「損得だけで判断してよいのか?」という問いかけが随所で読者に投げかけられております。 なにかの書評で、推薦されていたので読んでみました。
なにかの書評で、推薦されていたので読んでみました。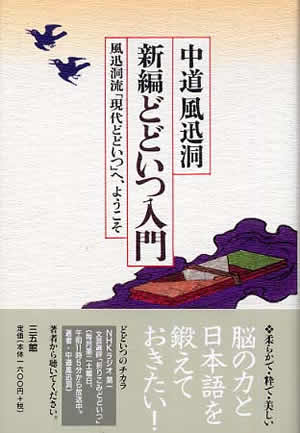 著者の中道風迅洞は八戸出身の方で、現代どどいつを確立した、どどいつの第1人者といってよい方のようです。NHKラジオなどで現在も活躍されております。
著者の中道風迅洞は八戸出身の方で、現代どどいつを確立した、どどいつの第1人者といってよい方のようです。NHKラジオなどで現在も活躍されております。