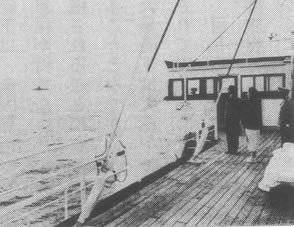最近読んだ本の感想です
読みたい本が多く、右(翼)系の本から先に読んでいます
| ←フレームを表示 ↑HOMEへ | ||
19.2.5 | 世界は腹黒い 異見自在/高山正之/高木書房 | |
中でも、面白いと思った部分を少し抜書きします。(要旨の抜書きです) | ||
19.1.19 | インテリジェンス武器なき戦争/手嶋龍一・佐藤優/幻灯社新書 | |
| ||
19.1.16 | テポドンを抱いた金正日/鈴木琢磨/文春新書 | |
| ||
19.1.9 | 南京事件 国民党極秘文書から読み解く/東中野修道/草志社 | |
| ||
18.12.31 | パチンコ「30兆円の闇」/溝口敦/小学館 | |
| ||
18.12.26 | 伽羅の香(きゃらのかおり)/宮尾登美子/中公文庫 | |
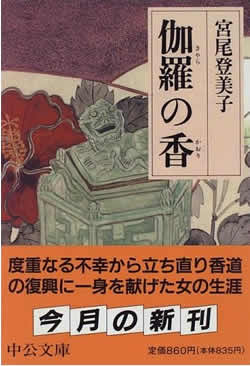 同僚に勧められまして、読みました。 同僚に勧められまして、読みました。普段、小説はあまり読みません。最近、人に勧められたものを読み始めています。 私の心の中では、「小説は作り事(うそ)、だからノンフィクションに劣る」という価値付けがありまして、読書に同じ時間を費やすのであればと、ノンフィクションの方に手が伸びるのです。しかし、その価値付けは誤りだということを恥ずかしながら最近実感じています。 小説は「作り事」ではあるのですが、そこに出てくる作者の見方であるとか考え方などは、我々が学ぶべき「真実」なのです。また、作品の環境、舞台装置なども「真実」であるといって良いのでしょう。この作品の大きな舞台装置になっている「香(こう)」なども、私など全く知らない事柄でありましたが、作者はこの「香」というものをより深く知るために弟子入りするなどして取材を重ね、そして、そのいわば調査の結果を私たちに見せてくれているのです。こう考えれば、こういう部分は「真実」といって良いと思います。また、あとがきや解説文を見てみますと、この本の主人公のモデルになった方も実際に居られたようでして、「小説など所詮は作り事だ」などとはとても言えません。 世の中には、人間と同じ数の人生があります。たいていの場合、小説で扱われる人生というのは多少特殊ではありますが、全くの作り事とはいえません。少なくともあり得る内容であると言って良いと思います。つまり、このような小説上の人物の人生を作り事とか真実とかいう区分をすることがナンセンスなことかも知れません。要は、その中に何を感じ、何を汲み取るかというようなことではないでしょうか。 そういうことで、「小説は作り事だから」という基準で、最初からこれを排除することは止めたいと思っています。 さて、この小説の中身ですが、読み終わって頭に浮かんだ言葉は「一大叙事詩」というものでした。 この本でへーっと感じたこと。
| ||
18.12.24 | 中国の核が世界を制す/伊藤 貫/PHP | |
| ||
18.12.9 | 日本とシナ/渡部昇一/PHP | |
| ||
18.11.30 | 日米開戦の真実/佐藤優/小学館 | |
東京裁判をさかのぼる約4年前の日米開戦のその直後、大川周明はラジオのマイクの前に立って国民に語り掛けます。その内容は、まさに米英による東亜(アジア)に対する侵略の歴史であり、それに立ち向かう日本の姿でありました。これを開戦直後に、全12回の連続放送として行なったのです。そして、この話の内容をそのまま本にしたのが「米英東亜侵略史」でした。当時、相当読まれたようです。 佐藤優。鈴木宗男と行動を共にしたことによって、執行猶予付き有罪判決を受け現在控訴中の身であることから自分自身の身分を「起訴休職外務事務官」と呼称しているあの佐藤優氏です。かれは「異能の外交官」「外務省のラスプーチン」などの異名をとる程の人材で、現在は著作活動を行っていますが、本書では、大川周明この著作を現代語訳にしてそのまま掲載し、これ対して彼の解説をつけて、日米戦争の実相を浮き彫りにさせていると思います。 いわゆる東京裁判史観でない、いうなれば大東亜戦争肯定論といってよいと思います。 現代の我々が強く認識すべき内容です。 | ||
18.11.01 | 昭和天皇の御巡幸/鈴木正男/展転社 | |
さて、ご巡幸を始めるにあたって、GHQはむしろこれを歓迎しました。 この御巡幸というのは、私は、敗戦に打ちひしがれた国民全体を激励されるということであったと漠然と思っていたのですが、実はそうではなく、まず遺族、引揚者、戦災者を激励するということを大前提に考えられたということでした。したがって、各地ではそれぞれの席が設けられており、陛下はそこにいる方々をまずお慰めになり、お励ましになりました。実際にそういう方々に細やかに言葉をお掛けになっています。 盲学校なども度々ご訪問になっています。 このようにして、昭和21年2月18日に神奈川県から始められた昭和天皇の全国御巡幸は、沖縄県を残し、昭和29年8月23日北海道を最後として完了しました。この間8年6ヶ月。長い巡礼のような旅でした。なお沖縄については、ご病気でお倒れになったときも最後まで気にかけておられました。沖縄の被災者に直接お声をお掛けになりたかったのです。 冒頭に書きましたように、陛下と国民が互いに親戚であるかのような感情をもっているという大変に幸せな国に我々は住んでいます。この感情が広く深く国民に行き渡っていれば、もっと住みやすい、もっと潤いのある国に、容易になるのではないかと思います。誠に惜しいことです。 以上の本旨とは直接関係がありませんが、興味ある記事がありました。 先だって現れたあの怪しげな富田メモなるものによって、陛下がいわゆるA級戦犯に不快の念を抱いておられるなどという憶測が広がりました。私は、そんなことはないと考えるものですが、このことに関して次のような記述があります。(236p) <引用開始> (昭和23年)11月12日午後、陛下は表御座所より御徒歩で御文庫に赴かれ、御自分でラジオのスイッチを入れられた。ラジオからは間もなく東京裁判の判決断罪の実況放送が流れてきた。この間、陛下は静かに眼を閉じて放送に聞き入っておられた。そして夕食後は、側近者も遠ざけられ、一人部屋にこもって、夜の更けるまでお過ごしになった由である。 この日から39日の12月23日、東条元首相以下七士の絞首刑が執行された。この似は皇太子殿下(当時)のお誕生日である。例年この日、皇室ご一家は夕食をともにされるのが常であったが、陛下は一切の行事を取り止め、終日、御文庫に御籠り遊ばされていた。陛下の御心中いかばかりであらせられたであろうか。 陛下はこの秋に次の三首の御製を詠まれている。 風さむき 霜夜の月を 見てぞ思ふ かへらぬ人の いかにあるかと (以下略) <引用終わり> もうひとつの興味ある記事。 | ||
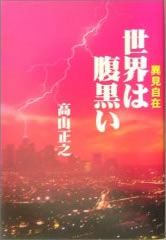 著者の高山氏は元産経新聞記者で現在帝京大学教授です。産経新聞勤務時、1998年から三年にわたって、新聞紙上に「異見自在」を連載されておりました。また、著者はテヘラン、ロサンジェルス支局長もされていることから、この本では、主として国際社会において国家が見せる腹黒さ、そして我が官僚の腹黒さなどを筆致鮮やかに書き記されております。概ね週一ペースで400字詰め6枚程度、中身の濃いやつを書き下ろしていく訳ですから、相当の知力体力です。
著者の高山氏は元産経新聞記者で現在帝京大学教授です。産経新聞勤務時、1998年から三年にわたって、新聞紙上に「異見自在」を連載されておりました。また、著者はテヘラン、ロサンジェルス支局長もされていることから、この本では、主として国際社会において国家が見せる腹黒さ、そして我が官僚の腹黒さなどを筆致鮮やかに書き記されております。概ね週一ペースで400字詰め6枚程度、中身の濃いやつを書き下ろしていく訳ですから、相当の知力体力です。 インターネットの巨大さを表す言葉に「地球と同じ大きさのものが地球の横に存在している。」というのがあります。つまり、インターネットの世界というのはもう一つの地球だというのです。
インターネットの巨大さを表す言葉に「地球と同じ大きさのものが地球の横に存在している。」というのがあります。つまり、インターネットの世界というのはもう一つの地球だというのです。 なにかの書評で推薦されていたので読んでみました。 著者は毎日新聞編集委員でTBSテレビのコメンテーターとしても時々顔を見る方。大阪外国語大学朝鮮語学科卒業で北朝鮮ウォッチャーということのようです。
なにかの書評で推薦されていたので読んでみました。 著者は毎日新聞編集委員でTBSテレビのコメンテーターとしても時々顔を見る方。大阪外国語大学朝鮮語学科卒業で北朝鮮ウォッチャーということのようです。 いわゆる「南京大虐殺」はありませんでした。それは、中国国民党中央宣伝部による一大プロパガンダであったのです。
いわゆる「南京大虐殺」はありませんでした。それは、中国国民党中央宣伝部による一大プロパガンダであったのです。 なにかのブログでこの本が推薦されていましたので読んでみました。
なにかのブログでこの本が推薦されていましたので読んでみました。 私はこの本を読み、日本も核武装をすべきだという確信を深めました。
私はこの本を読み、日本も核武装をすべきだという確信を深めました。 渡部節が冴える1冊です。
渡部節が冴える1冊です。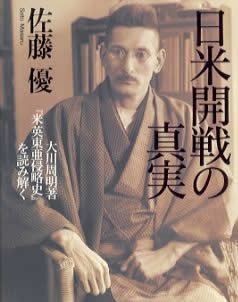 副題を「大川周明著『米英東亜侵略史』を読み解く」といいます。
副題を「大川周明著『米英東亜侵略史』を読み解く」といいます。 私は、日本というのは「天皇陛下をその総本家の長とする、一大親戚集団である」という捉え方をしております。他国のような統治する側と統治される側という関係ではありません。陛下(皇室)と国民はともにお互いを身内と感じているのです。そのひとつの証拠が、皇室の慶事に際しての私達の感情です。この度の悠仁親王殿下のご生誕に際して、街頭でマイクを向けられた国民はまるで自分の家に、または親戚の家に子供が生まれたような感想を心からの喜びの表情で語っております。
私は、日本というのは「天皇陛下をその総本家の長とする、一大親戚集団である」という捉え方をしております。他国のような統治する側と統治される側という関係ではありません。陛下(皇室)と国民はともにお互いを身内と感じているのです。そのひとつの証拠が、皇室の慶事に際しての私達の感情です。この度の悠仁親王殿下のご生誕に際して、街頭でマイクを向けられた国民はまるで自分の家に、または親戚の家に子供が生まれたような感想を心からの喜びの表情で語っております。