最近読んだ本の感想です
読みたい本が多く、右(翼系の)の本から先に読んでいます
| ←フレームを表示 ↑HOMEへ | ||
|
22.8.25 |
文化防衛論/三島由紀夫/ちくま文庫 | |
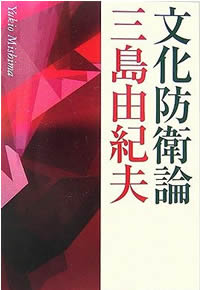 この本には論文数編と学生を対象にした講演会の模様が収録されています。前者については私にとってやや難解でしたが、後者については特に学生との質疑応答の部分を大変興味深く読みました。余談ですが、当時の学生が三島由紀夫と対等なスタンスで、丁々発止のやり取りをしている情景には、ちょっとびっくりしました。今と違って当時の学生は真剣であったように思えます。一途(いちず)と言ったほうが適当かもしれません。近頃の学生は、多分こうではなく、丸く収めるような論議をするのだろうと思います。 この本には論文数編と学生を対象にした講演会の模様が収録されています。前者については私にとってやや難解でしたが、後者については特に学生との質疑応答の部分を大変興味深く読みました。余談ですが、当時の学生が三島由紀夫と対等なスタンスで、丁々発止のやり取りをしている情景には、ちょっとびっくりしました。今と違って当時の学生は真剣であったように思えます。一途(いちず)と言ったほうが適当かもしれません。近頃の学生は、多分こうではなく、丸く収めるような論議をするのだろうと思います。
この本を読みながら、今の政情に照らして強く感じたことがありました。 私には、実行に移す勇気は全く持ち合わせていませんが、納得はします。命とは何かを為すための手段、つまり、いうなれば搬送体であって、従って命を保つことが目的にはなりません。何を運ぶか(何をするか)が大事ということです。特攻隊がその良い例です。植物人間や尊厳死の問題もこれと通底しています。 こうして思い浮かぶのは、民主党政権のことです。もちろん自民党が優れていたというつもりはありませんが、今の民主党にぴったりのような気がします。 「出でよ、暗殺者」、と本当に思いますね。
| ||
|
22.7.30 |
週末陶芸のすすめ‥ほか/林寧彦/晶文社ほか | |
|
林寧彦氏の存在はネットで知っておりまして、一回だけメールをやりとりしたことがあります。 内容は、ふとした弾みで陶芸に足を踏み入れ、旺盛な探究心・向上心の故に自宅マンションのベランダで電動ろくろを運用し始めるという、第1段階の話。博多への転勤を契機に、単身赴任先のマンションに電機窯を据付け、有田の窯元で勉強しながら腕を磨く5年間についての第2段階。そして、単身赴任を終わって、千葉の自宅の近傍に専用の陶芸作業場を開くという第3段階。と、なっています。 私が、これらの本を読んで感銘を受けましたのは、次のようなことごとです。 2 審美眼について 3 美術と工芸の融合について 4 チャレンジの大切さについて 5 目標の設定について 大変、ためになる本でした。
| ||
|
22.3.23 |
田母神塾-これが誇りある日本の教科書だ/田母神俊雄/双葉社 | |
|
さて、この本のことですが、国民向けの教科書ということで、「1時限目;歴史」「2時限目;政治」「3時限目;国防」と、大きく3章に分けた構成になっています。細部は略しますが、1点だけ最近私も感じている点に触れたいと思います。 それは、「ミリタリー・リテラシィ」ということについてです。 でも、最近、私はこういう国会議員をのみ非難してもしようがないと思うようになりました。 この本でも、述べられていますが、大学をはじめ、日本の学校教育で軍事に触れられることがほとんどありません。それどころか、逆に軍事は触れるにも汚らわしいものであるとする教育が行なわれているのですから何をかいわんや、なのです。 問題の根は本当に深いということなのです。戦後64年が経過しましたが、状況は更に悪くなってきています。一体いつになったら、世界の普通の国のようなまっとうな教育が行なわれるようになるのでしょうか。私にはもう想像すらできません。 | ||
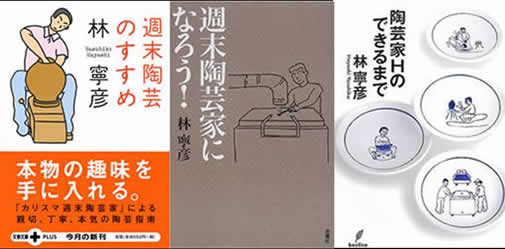
 大変よく纏められた本です。
大変よく纏められた本です。