| ���t���[����\���@�@���g�n�l�d�� |
|
|
20.8.1
|
�ݍ��n�߂̕���E�ǂ��܂ł킩�郄�}�^�C���^�O�k�i�݂܁j�M��E�O�D���^���؏��[ |
|
 �@�u�ݍ��n�߂̕���v�Ɓu�ǂ��܂ł킩�郄�}�^�C���v�̂Q���\���ɂȂ����{�ł��B�X�O�y�[�W���x�̔����{�ʼn��i�͂S�O�O�~�B�ł����A���e�͔��ɗǂ����̂ł���Ǝv���܂����B �@�u�ݍ��n�߂̕���v�Ɓu�ǂ��܂ł킩�郄�}�^�C���v�̂Q���\���ɂȂ����{�ł��B�X�O�y�[�W���x�̔����{�ʼn��i�͂S�O�O�~�B�ł����A���e�͔��ɗǂ����̂ł���Ǝv���܂����B
�@�u�ݍ��n�߂̕���v�́A���{�̍��̎n�܂�ł���_�b�̎���̂��Ƃ��q�������̊G�{�Ƃ��āA�܂����킹�Ă����ǂݕ������邨�ꂳ��̂��߂̉�����Ƃ����̍قɂȂ��Ă��܂��āA�����������z���܂��f���炵���Ǝv���܂����B�e�ɑ��鋳����s���K�v������A�Ƃ������ƂȂ̂ł��ˁB
�@�_�b�͂��Ƃ��A���j��̎����ł͂���܂��A�_�b�Ƃ��������i�^���ƌ����Ă��ǂ��Ǝv���܂��B�j�A���邢�͐̂̐l���������̂悤�ɍl���Ă����Ƃ��������Ȃ̂ł��B�Ȋw�I�ɂ͐^���Ƃ͂����Ȃ��̂ł��傤���A����Ƃ��Ă͐^���Ȃ̂ł��B���̂��Ƃ́A�T���^�N���[�X�͋���̂����Ȃ��̂��A�_�l�͋���̂����Ȃ��̂��Ƃ����_�c�Ɏ��Ă��܂��B�T���^�N���[�X��_�l�́A�����M����S�̒��Ɋm���ɑ��݂���Ƃ����Ӗ��ł́A�^���ł���ƌ����܂��B�Ȃɂ������������Ƃ����ƁA�Ȋw�I�ł���Ƃ����ۂɖڂŌ�����A��ŐG����Ƃ������̂ɂ����u�^���v�Ƃ�������^���邱�Ƃ͂ł����A����ȊO�̂��̂́u�^���v�Ƃ͌������A���ɑ���Ȃ����l�Ȃ����̂��A�Ƃ����l�����͂��������A�Ƃ������Ƃł��B
�@�Ⴆ�A�֏��ɂ͕֏��̐_�l������A������A�������ꂢ�ɂ��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ��A���͏��������ꂩ�狳�����܂����B�_�l�Ɍ����Ă�����A���ꂢ�ɂ��Ȃ��Ⴂ���Ȃ��A�Ƃ����킯�ł��B���̂Ƃ��A�֏��̐_�l�̑��݂́A���ɂƂ��Đ^���ł����B
�@�����悤�ɁA�]�ˎ���́u���V���l�����Ă���B�v�Ƃ����ی��������ł��B���̌��t�������̐��̒��̒����̈ێ��ɉʂ����������͑�ϑ傫���A���V���l�̑��݂́A�����^���ł�������ł��B
�@���́A�B���_�����łȂ��B�S�_�ɂ��d�������������̂̌����l���������ׂ����A�Ƃ��������̂ł��B
�@���̍l���́A�u���͕�i�ʂ��ǂ�������j�v�Ƃ����悤�ȉ��l�ςƑɂ��Ȃ����̂ł��B���̐��̒��ɂ��������l�������x�z���Ă���̂́A�q���̍��ɒm��ׂ��_�b���i�Ȋw�I�łȂ��Ƃ������R�Łj�ے肵�����Ă��邱�Ƃɒ[���Ă���Ǝ��͎v���܂��B�l�����������̓��{�́A�����������ɂ��Đ_�l�������n���Ă��ꂽ�̂��Ƃ����������悤�Ȗ����̃��}���ɐG��邩�ǂ����Ƃ����́A�Ǔ��{�l���`�������ł̑傫�ȕ�����ڂɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�����������Ƃ��A���̖{���犴���Ȃ���ǂ݂܂����B
�@�܂��A�G�{�Ƃ��Ă͂����������邭���ꂢ�ɂ��������ǂ��̂ł͂Ȃ����A�G�z�Ȃ���v���܂����B�ŋ߂͂��̂e�k�`�r�g�ō������ʔ����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����C���v���܂����B
�@��Q�҂́A鰎u�`�l�`�ɂ��ĖM��Ɖ�����������̂ł����A鰎u�`�l�`���ЂƂ��Ƃł����Ȃ�A�u鰁i�����j�̓s���Œ������������ɍ��グ������ΐ�`���ł����āA���ɑ���Ȃ����̂ł���v�Ƃ������Ƃł��B����Ȃ̂ɁA������܂�ŋ��ȋʏ��ɂ��ĉ䂪�����j�̎n�܂�������̂Ƃ��āA���j���ȏ��̖`���ɕK���o���Ă���̂͑S���������Ȃ��Ƃł���A�Ƃ�����ł��B
�@
�@鰎u�`�l�`�̓��e�́A���Ƃ����l���������ɂ���ēZ�߂����̂ŁA�ړI�͂����Ȃ�Β��؎v�z�̍��g�Ƃ������Ƃł��B���ǁA�����̂��������s�Ȃ��Ă���u��v�Ȃ̂ł��B�u�`�v�u�ږ�āv�Ƃ����p���ɂ��A�܂��L�q�̓��e�ɂ����{���������A�Ȃ߁A���ΓI�Ɏ����������グ��Ƃ����l�����݂��݂��ł��B
�@�v�́A����ȋ����������߂邱�Ƃ���ڊo�߁A�Î��L�A���{���I�Ƃ����V���Ɍւ���j����厖�ɂ��ׂ����Ƃ������ƂȂ̂ł��B
�@�����������Ď^�����܂��B
�@
|
|
|
20.7.15
|
�u���B���v�����L-���b�g�������c���s�L�^�n�C�����b�q�E�V���l�[�^�u�k�Њw�p���� |
|
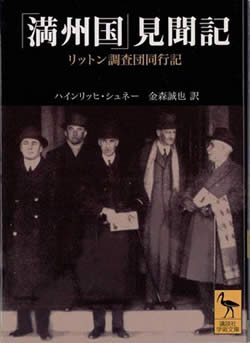 �@���҂̓h�C�c�l�����ƂŁA���b�g�������c�T���̂����̂P���ł��B
�@���҂̓h�C�c�l�����ƂŁA���b�g�������c�T���̂����̂P���ł��B
�@
�@1931�N�i���a�U�N�j�X���P�W����ɔ������������Ύ����ɂ��āA�X���Q�P���ɂ͒��ؖ����͍��ۘA���ɑ��āu���炩�̏��u�v�����悤�v�����A�������`�ŘA���͓����Ƃ̒�����}��Ȃ���A�P�Q���P�O�������c��h������Ƃ������c�����܂��B�����c�̔C���́A���n�ł�����������������Ԃ̕��a�����������Ƃ��Ă��鏔���������ۘA��������ɕ��邱�Ƃł����B
�@
�@����1932�N�i���a�V�N�j�X���ɏ������ꊮ�����܂����A�قړ������i�X���P�T���j�ɖ��B�������{�ɂ���ď��F����܂��B���{�́A����Ί�������������Ă��܂��A�����̈Ӗ���������Ă��܂���ł��B
�@���ۘA���ɂ����Ė��B���ɂ��Ă̘b����������������Ԃɂ��A���{�͐퓬�̏��M�͂܂Ŋg�債�܂��B���ǂ́A�A���͒����c�̕Ɋ�Â��āA�������ɍs�Ȃ�ꂽ���{�̌R���s���͎��q�s���Ƃ͔F�߂��Ȃ��|�̊����Ă��̑����A�u���B���v�̌����́A�����I�Ȑ^���̓Ɨ��^���ɂ����̂ł͂Ȃ��Ƃ̌������o���܂��B�܂��A���̊����Ăł́A���B�ɂ����钆���̎匠��F�߁A���{�R�����S�t���n��ȊO�̖��B�ɒ��Ԃ��邱�Ƃ͒����̎匠�Ƒ��e��Ȃ����Ƃ��m�F���A���̒n�悩����{���P�ނ��邱�Ƃ����߂܂��B
�@�����͂��̊���������܂����A���{�͎��̗��R�ɂ���ĘA����E�ނ���|�̈ӌ��������܂��B
�@�����u�����͑g�D�����ꂽ���Ƃł͂Ȃ��A�����̓�������⍑���̏��W�͋ɓx�ɍ������A���G�ɂȂ��Ă��邽�߈ُ�ȗ�O�I���i���`����Ă���B���������āA�����Ԃ̒ʏ�̊W���K�����鍑�ۖ@�̊��K�𒆍��ɓK�p����ꍇ�́A��������Ȃ�ό`���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ������Ƃł��B
�@���b�g�������c���ɑ�����{�̑Ή��͈̏ȏ�̂悤�ł����B
�@���āA�����c�͂P�X�R�Q�N�i���a�V�N�j�Q���ɓ����ɗ��āA���{�Ɋւ��钲������ɈȌ㒆���֓n��A���R�ł������B�𒆐S�Ɏ��@���A�k���ŕ��̍쐬���s�Ȃ��܂����B
�@�{���ł͂��̂P���ł���V���l�[�������Ō��������o�����������Ă���̂ł����A���̋L�q���e������ۂƂ��ẮA�������̃X�^���X�ł������悤�Ɋ������܂��B�����͐N�U����A���{�͐N�U�������ł���B���{�́A�L�F�l��́A�������V�Q�҂ł���̂ɐ��ӋC���A�Ƃ����悤�Ȋ���������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@���������A����ΐ���ςƗ����̒����c�ɑ���Ή��U����傫�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����́A���������ł����A���̂悤�ȏł̋��������ɂ��܂��Ƃ������Ƃ�����܂��B�����A���{�͕K�����������łȂ��A����̉��l�ςɍ��킹��Ƃ����ϔO�������A�����̉��l�ςɂ����̂��������ԂƂ����悤�ȂƂ炦�����������ł͂Ȃ��ł��傤���B�����A���{�̉��Ȃɔނ͂��s���������Ȃǂ̋L�ڂ�����܂����A���{�̐^�̕����ɐG�ꂳ�������Ƃ͎v���܂���B����̒����ł́A��O�̐����̒Ⴓ�ɋ����Ȃ�����A����N�̗��j�E�����̑��݂��^�����A�����l�͂�����p�������D�ꂽ�����ł���Ƃ̔F�����������肵�Ă��܂��B�����͂����ł͂Ȃ��̂ł����A��_�����܂��B���A�t�̔F�����������邱�Ƃɐ������Ă���̂ł��B�����l�̐����͂����ɗǂ���������Ă���悤�Ɏv���܂��B
�@�k���ɂ����ĕ����쐬���ꂽ�Ƃ������Ƃɂ��Ă��A�Ȃ�炩�̒����̉e���͂����������܂��B�_��ȊO�̈ȏ�̂悤�ȓ_�ɂ��Ă����{�͕����Ă����悤�Ɏv���܂��B
�@
�@�܂��A���̌����L�ł́A���̃C�U�x���o�[�h�̗��s�L�̂悤�ȍׂ₩�Ȋώ@�͂œ����̖��B�̏��`����Ă��邱�Ƃ����҂����̂ł����A���̈Ӗ��ł͂��������L�q�����Ȃ��A�����Ƃ������肵�Ă��܂��܂����B
|
|
|
20.7.1
|
�y�V��z���q�^������\���^�o�g�o |
|
 �@�u���q�Ƃ͂Ȃɂ��v�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A���q�ɏ����ꂽ�������̋L�q��������������s���A�K�v�ɉ����ĉ������Ƃ����`�Ԃ̒���ł��B�܂蕺�����̖|�ł��B �@�u���q�Ƃ͂Ȃɂ��v�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A���q�ɏ����ꂽ�������̋L�q��������������s���A�K�v�ɉ����ĉ������Ƃ����`�Ԃ̒���ł��B�܂蕺�����̖|�ł��B
�@�����ɏ�����Ă���A�������̐킢�̌��������X�͊w�ю����̂�����A���ꂪ�A�T�u�^�C�g���Ƃ��Čf���Ă���܂��u�|�X�g��펞������������P�R�т̌ÓT���@�v�Ƃ��������ƂȂ̂ł��傤���A���l�Ƃ��Ă̓t���t���Ɛ[�����ȂÂ���悤�Ȃ��̂��܂肠��܂���ł����B
������A�Ȃ�قǂ˂��Ǝv�����̂́A���̂�����ł����B����́A�͂������ɏ����Ă��������̂悤�Ȃ��̂ł��B
�����p�n��
�@�Ñ�V�i�̕����́A���Ȃ킿�_�z�ł����B
�@�_�z�������W�߂��������A�M���̏��R�������āA�����̐��͔͈͊O�ɘA��o�������푈���A�{���́u�v�сv�ł�����u���v�ł��B
���̉����푈�̖ړI�́A�V���Ȕ_�z���ł��邾�������A�l�����邱�Ƃł����B������̕��y�ɔ����āA�l�肳������ΊJ���\�ƂȂ�y�n�́A���肠�܂��Ă����̂ł��B
�@�Ƃ��낪�A�_�z���ɂ́A�����S�⒉���S��E�C�́A�������������܂���B
�@�������|���̂ŁA���₢��Ȃ���]�R���܂�����ǂ��A���S�ł́A�����ɑӂ��A�y�����A����������ɁA���S�Ⓤ�~�◠������Ăł������c��A�Ƒ��̂��ƂɋA��邩�ƁA���ꂾ�������A�l���Ă��܂���B
����ȗ���ɂȂ�ʕ��������ɁA�ǂ�����ă����C���o�����āA�G�����Ɛ����������������������邱�ƂȂǂ��A�\�ɂȂ�̂ł��傤���H
�����́u��n�сv�Ő�����Ă���̂ł��傤�B
�@�w�����́A�ނ���x���āA�m�炸�m�炸�̂����Ɂu���n�v�ɓ�����悢�����ł��B���n�Ƃ͋��n�̂��Ƃł͂Ȃ��A��O�𑩂˂�ӎ��I���[�_�[�ɂƂ��Ă̗��z�I�ȃV�`���G�[�V�����̂��ƂȂ̂ł��B
���̂悤�Ȕ�p�X�Ƌ�����e�L�X�g���A�V�i�ł́A�Ñォ�猻��܂ŁA�S���̗L�͐����Ƃ����ɂ���āA���d����Ă����B�Ȃ�Ƃ����낵��������i���ł��傤���B
�@�V�i�ł́A�����Ƃ́A�W�c���A�����S�̂��A���n�ɓ�������@��m���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B���̑�O���c�p�́A��펞��̊j�}�~�헪�ɂ��傢�ɗL���ł������A�|�X�g��펞��̑A�����J�O���ł��L���Ȃ̂ł��B��ׂČ��āA�䂪���{�̌��㐭���Ƃ͂ǂ��ł��傤���H
�@��O�̒��������}���獡���̒������Y�}�܂łЂ��Â��Ă��锽������┽����`�́A�܂��ɁA�����S�̂Ȃ��V�i��O���u���n�v�ɓ����Ďx�z�͂��ł߂邽�߂̍H��̈�ł��B�w���q�x������Ă��Ȃ���A���{�l�Ɠ��{�����{�́A�Ђ�����ނ�̉��d�ɖ|�M����邾���ƂȂ�ł��傤�B
�@�w���q�x�́A��O����̍������A�ēǂ���鉿�l������R���O���}�j���A���ł���Ƃ����܂��B
�����p�I��
�@��L�̂��Ƃ��A���q���q�ׂ��ӏ����u���v�тɂ���܂��B���̕����̕������ł��B
�����p�n��
�@����́A�p�Y����������w��������l�Ŏ��q���v���ď��Ă���̂ł͂Ȃ��A�����S�̂̐��������܂���ׂ��ď��̂��������Ȃ��A���_���Ȃ��A�����̋����̂��v���܂��B
�@���̂悤�ȕ����w�����ł�����̂������A����̎i�ߊ��Ƃ��ĔC���܂��傤�B���W�����_������Ȃ镔���ɐ��������č��킳����̂́A���傤�ǁA�����Ă��Ȃ��ޖ��]������ƂƎ��Ă��܂��B
�@�ޖ����A�Ⴂ�Ƃ���ɒu���ꂽ�܂܂ł͓����܂��A�����Ƃ���ł����ނ��Ă��A�����ɓ����܂��B
�@�`��n�ʂ��]�����̂ɕs�K���Ȃ�A�����~�܂��Ă��܂��܂��B�t�ɁA�ʒu����U����������ނ̑e�������܂��K�����Ă���A�ꉺ�̕����͂ǂ��܂ł��~�܂�܂���B
�@����̂��܂��w�����́A���������~���������R���炱�낪�����Ƃ��悤�ɂ��āA�ꉺ�̕����ɐ�����������̂ł��B
�����p�I��
�@���̂悤�Ȃ��Ƃ��A����N�ɂ킽���āA�����č����s���Ă���̂������Ȃ̂ł��B�V�i�嗤�̎w���ҒB�́A�܂�ō��̂悤�ɁA�����Ă������Ă��w�̌��Ԃ��瓦���Ă����Ă��܂��A�����ēZ�܂邱�Ƃ̂Ȃ����O�䂷�邱�Ƃɕ��S�������A�����̃m�E�n�E��~�ς��Ă���̂������Ȃ̂ł��B
�@�܂�A�ǂ������͕ʂɂ��āA�l�̈����ɑ����̋�J�����Ă����ł��B
�@���̓_�A��X�͂�������w�Ȃ���Ȃ�܂���B
|
|
|
20.6.15
|
���s�Ɍ����𓊉�����^�g�c��j�^�p�쏑�X |
|
 �@��̑�풆�A���s����P����Ƃꂽ�̂́A�č��̕��������d�Ƃ����f���炵���l�������������炾�A�Ƃ�������������܂��B�������̖{��ǂނ܂ł́A�����l���Ă���܂����B�Ƃ��낪�A�����͂����ł͂Ȃ��悤�ł��B���҂ɂ�鎑�����@���܂߂Đ��X�̃f�[�^�������āA���̂��Ƃ����R�Ɣے肵���̂����̖{�ł��B �@��̑�풆�A���s����P����Ƃꂽ�̂́A�č��̕��������d�Ƃ����f���炵���l�������������炾�A�Ƃ�������������܂��B�������̖{��ǂނ܂ł́A�����l���Ă���܂����B�Ƃ��낪�A�����͂����ł͂Ȃ��悤�ł��B���҂ɂ�鎑�����@���܂߂Đ��X�̃f�[�^�������āA���̂��Ƃ����R�Ɣے肵���̂����̖{�ł��B
�@
�@���_�I�ɂ����ƁA���s�́A�č��̍�簂Ȏv�z�ɂ���ď��������̂ł͂Ȃ��A�����̌��ʂ�c�����₷���悤�ɋ��T�����i"reserave"����j�Ă���A�����𓊉����钼�O�ɏI��ɂȂ��Ă��܂��������̂��Ƃł���A�Ƃ������ƂȂ̂ł��B
�@�`���̂悤�Ȍ�������ꂽ�̂́A���̓s�s����P���钆�A���s�A�ޗǂȂǂ���P���Ȃ����Ƃ̗��R�ɂ��āA�e���I�Ɩڂ���Ă����č��l���m���p�����Ƃ̃E�H�[�i�[���m���A���s�A�ޗǂȂǂ̌Ós�s�̋�P���~��ē��ǂɐ��肵�A���ꂪ����t�����Ƃ��������ĂȎv�����݂����̔��[�ł����B���A�m�Ȃł��������{�l���A����𗠕t����悤�ȕ����@���A�������肵�����͂������Ɏv�����݂ł����ǂ݊ԈႢ�A�E�H�[�i�[���m�̌��тł���ƌ��`���܂��B�{�l�͂Ƃ����Ɨ�����������ɁA���̎���ɑ��āA�ϋɓI�Ȕے�������A���̂��Ƃ��܂����䂩�����Ɠ��{�l������Ɏv�����݁A�܂��܂��^���ł���ƁA������Œ艻���Ă����܂��B���A���{���̂����f�g�p���܂��A����K���ƁA���̂��Ƃɕ֏悵�A�t�ɂ����������̂ł��B
�@�������ċ��s�͕č��̗ǎ��̑�\�E�H�[�i�[���m�ɂ���ċ~��ꂽ�Ƃ������ƂɂȂ�A�S���U�����ɔނ���������L�O�肪��������A�����ɂ͈ԗ�i���Ӂj�̖@�v�Ȃǂ��s���Ă���A���̂��Ƃ͏펯���̏펯�ɂȂ��Ă��܂����̂ł��B
�@
�@���{�l�������Ă���C�����i�������͎��ׂ����j�͐��E�ł����ʂł���Ƃ����v�����݁A�����Đ��E�͎��͂��̋t�ɎE���Ƃ��Ă���Ƃ������Ƃ�m��Ȃ��A���Ԃł��l�悵�̖������������ɏo�Ă���̂ł��B
�@�A�����J�́A�����̓����ɂ����蓊�����ׂ��s�s�̑I����s���ɂ�����A�ڕW�I��ψ���Ȃ��c���P�X�S�T�D�S�D�Q�V�ȗ��A�����ɂ킽���ĊJ�Â���������̂ł����A���̍ۂ̓����ڕW�̑I�������̂悤�ɂ��܂��B
�P���a3�}�C����������傫�ȓs�s�n��ɂ���d�v�ڕW�ł��邱�ƁB
�Q�����ɂ���Č��ʓI�ɔj������̂ł��邱�ƁB
�R���锪���܂łɍU������Ȃ��܂܂ł��肻���Ȃ��́B
�@�����ɂ́A�����s�s�����O����Ȃǂ̍l���͈����܂���B���������A�����̌��ʂ��ł��āA���̌��ʂ����Ƃŕ]���ł��邱�Ƃ��l���p���ł������̂ł��B
�@�������đI�ꂽ�̂��A
�@���s�A�A�L���A�B���l�A�C���q�A�i�̂��D�V���A�E����j
�ł����B
�@���̂����A���s�͎��̓_�ōŗǂł���Ƃ���܂����B�i�ڕW�I��ψ���j
�P�@�S���̐l��������s�s
�Q�@�펞���Ŝ�ЍH�Ƃ����̓s�s�ɗ��ꍞ��ł��Ă���A�R���ڕW������
�R�@�s�X�n�̍L���������Q�D�T�}�C���A��k�S�}�C������A�l�����W�n���L��
�S�@���{�l�ɂƂ��ď@���I�Ӌ`�����d�v�s�s�ł���A���̔j���{�l�ɍő�̐S���I�V���b�N��^���邱�Ƃ��o���A���̍R��ӗ~�����܂�����̂ɖ𗧂�
�T�@�O�����R�Ɉ͂܂ꂽ�~�n�ł���A�������ő�̌��ʂ�������n�`�������Ă���
�U�@�m���l�������A�����̂Ȃ邩��F�������ނ炪���{�ɑ����~������������҂����Ă�
�V�@�܂������ɂ���Q�������ނ��Ă��Ȃ�
�@�܂�A�������ی�ǂ��납�����ň�؍�������������ƌv�悵�Ă����̂ł��B
�@����͓������ɏオ���Ă��܂���ł����B����͒��肪�ג�������2�̎R�ɋ��܂�Ă��邽�߂ɔ�������k�Ɋg�U���Ă��܂��A�����̌��ʂ����܂������ł��Ȃ��Ƃ������R�ł���������ł����B
�@�Ȍ�ŏI�I�ȂQ���̌��������܂łɁA���l����₩��͂���V�������ɕ��サ�A���s���͂��꒷�肪���シ��Ȃǂ̕ϑJ������܂������A���̊Ԃ͂�������ϋɓI�ȋ͍T�����reserve���ꂽ�킯�ł��B
�@�����čŏI�I�ɂ́A�L���ƒ���i���q�̗\���j�Ɍ�������������A���s�͂͂�����܂��B
�@
�@���̗��R�͂Ȃɂ��B
�@���҂̒����ł́A���R�����X�`���\���̐i���ɂ��Ƃ���ł���A�Ƃ����Ă��܂��B
�@����ɂ��ƁA�v�͋��s�ł̓C���p�N�g���傫������Ƃ������Ƃł��B
�@�ނ�́A���R�Ȃ�����ɂ����鍑�ێЉ�̗͊W��ǂ�ł��܂����B���̓��{�́A�Γ��Q��������\�A�ɕt���������𓊉������A�����J�ɕt�����A�厖�ȂƂ��낾�A�Ƃ�����ł��B�����Ƃ����ł��邪�A�������x�̗ǂ����ɂƂǂ߂�ׂ����A�Ƃ������ƂȂ̂ł��B�P�O�O���s�s�̋��s��j�s����������{�l��G�ɉĂ��܂��Ƃ����v�Z�Ȃ̂ł��B����ŁA���s���p�X����A�Q���ڂ�����ɉ���čs���܂����B
�@�Ȃ��A�ޗǂ⊙�q(*)����P���Ȃ������͔̂ނ�̔�����ł���s�s�Ƃ��Ă̑傫���A�R���H��̗L���Ȃǂ̓_�ʼn��ʂɂ����������̘b�ł����āA�푈���������Ă���Ώ��X�ɂ��̑Ώۂɓ����Ă����^���ł������̂ł��B
�@
�@�܂��A���s�͑�R���ڂ̌��������ڕW�Ƃ���reserve���ꑱ���A�I��܂ł��ɖ����ł���܂����B�܂�A�I�킪�x��A��R���ڂ̌����������Ԃɍ����Ό����̎S�Ђɍ����\��������܂����B���Ȃ݂ɑ�R���ڈȍ~�̐����́A�V���Q�R�����_�ł̌��ʂ��ł́A��R���ڂ͂W���Q�S������A�X���ɂ͐V���ȂR���A�P�Q���ɂ͂V���`�A�Ƃ������Ƃ������悤�ł��B�W���P�O���̎��_�ł́A���ꂪ����ɑ��܂�A�u�W���P�V�����P�W���ȍ~�̍ŏ��̍D�V�ɓ��ɓ����ł���v�Ƃ�����Ԃł������悤�ł��B
�@���̕����͗]���Șb�����m��܂��A���肬��܂ŋ��s�ɂ͂��̉\�����������Ƃ��������ƂŁA����������낤�ȂǂƂ����Â�����낢���͈̂�Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�@
�@�{���ɐ��E�͕������A���{�l�͂悭�����₳�������ʂɌ����ƁA�ǂ����悤���Ȃ����Ԃł��l�悵�Ƃ������Ƃł��B�͂₭�ڊo�߂Ȃ���Ȃ�܂���B
(*)JR���q�w�O�̋L�O��i29p�j
�@���̋L�O��́A���q�s���̐��E���E�l�A�����l�A�s����̊�t�ɂ���āA�u�E�H�[�i�[���m�̋L�O������Ă��v�̖��O�Ō������ꂽ�B����́A�P�X�W�U�i���a�U�P�j�N���Ós�ۑ��@�{�s�Q�O���N�ɂ����邱�Ƃɂ��Ȃ�Ōv�悳��A���̗��N�̂P�X�W�V�N�S���Ɍ������ꂽ���̂ł���B
�@�L�O��́A���q�����̏����ȍL��ɗ��B�Q���قǂ̌�e�ɃE�H�[�i�[�̊�̕������肪�ق��Ă���B�E�H�[�i�[�̈⓿����������蕶�̏�ɂ́A�u�����͐푈�ɗD�悷��v�Ƃ����X���[�K���i�H�j�܂ō��܂�Ă���B�܂��A�U���X���̖����O��ɂ́A��O�Ŗ��N�@�v���s���Ă���Ƃ����B
|
|
|
20.6.1
|
���a�V�c�̌����^�R�{�����^�˓`�� |
|
 �@�P�Ɉ̑�ȓV�c�ł������A�Ƃ������u�l���Č���ΑS���H�L�i�����j�̑��݂ł���B�v�i���҂܂������j�ƌ����܂��B�����āA�u�l�ގj�エ���炭�O�Ⴊ�Ȃ��A������Ăт��̂悤�Ȑ��U��������l���͌���܂��A�Ǝv����̂����a�V�c�ł���B�v�i���j
�@�P�Ɉ̑�ȓV�c�ł������A�Ƃ������u�l���Č���ΑS���H�L�i�����j�̑��݂ł���B�v�i���҂܂������j�ƌ����܂��B�����āA�u�l�ގj�エ���炭�O�Ⴊ�Ȃ��A������Ăт��̂悤�Ȑ��U��������l���͌���܂��A�Ǝv����̂����a�V�c�ł���B�v�i���j
�@���̏��a�V�c�́A�ǂ̂悤�Ȑl�ł��������A���R�{�������͌��n�߂܂��B���a�V�c�����邱�ƂȂ���A���̎R�{�����܂��A�Ï��X�̓X��ł���Ȃ���A���X�̒���𐢂ɖ₤�Ă���A���̂���������ǂ݉����̂�����e�ɂȂ��Ă���܂��āA���̖{���܂����̗�ɂ��ꂸ�A���a�V�c�̓��S���킩�����Ɗ�����������̂ɂȂ��Ă��܂��B�R�{���Ƃ����̂́A�Ï��X�̃I���W���{�������Ă���Ƃ����̂ł͂Ȃ��A���j�Ƃ��邢�͎Љ�w�҂����܂��܌Ï��X�̃I���W������Ă����A�Ƃ������Ƃ��낤�Ǝv���܂��B
�@���̖{�ł́A�u�V�c�͋������Ȃɂ��Ă̋K������Ă�����v�Ƃ����̂���̃e�[�}�ɂȂ��Ă��܂��B
�@���̋K��̓��e�Ƃ́A�����V�c����߂�ꂽ�u�����N�吧�v�̉��ł̌N��ł���A�Ƃ������ƂŁA�������E����悤�Ȃ��Ƃ͔��o�����l���ɂȂ��Ă���܂���ł����B���̂ЂƂ̏؍����A�����g�̌��t�u�Q�D�Q�U�̎��ƏI��̎��ƁA���̂Q���A�����͗����N��Ƃ��Ă̓��݊ԈႦ���d�i���]���]���ɂ��L�^�j�v�ɕ\��Ă��܂��B�������A�����̂��Ƃ����́A���̂��Â��������ΐ��{���@�\���Ȃ��Ȃ�����펞�ɍۂ��Ă̂��Ƃł����āA�V�c�̈ӎv��������Ȃ��Ǝ��E�ł��Ȃ��悤�Ȏ��Ԃ���������Ȃ̂ł����A�É��͂��ꂳ�����u���݊Ԉ�����v�Ƃ���������Ă����ł��āA���̎����̋�����������܂��B
�@���̂悤�ȁA���l�����������悤�ɂȂ����̂́A�f�n���������ł��傤������ɂ��Ƃ��낪���ɑ傫���悤�ł��B�É��́A�w�K�@�����Ȃ������ƌ�́A�{���̌�w�⏊�łV�N�ԁA���l�̂��w�F�ƂƂ��Ɋw�Ƃ�ς܂�܂��B���̍ۂɑ傫�ȉe����^�����搶�̈�l�����Y�d���i���������j�Ƃ����ϗ���S���������w�҂ł���܂��āA�ނ́u�������Ύ����A�Ȋw���d��v�Ƃ���������j�ŕÉ��̋���ɂ������������ł��B
�@
�@���j�̋���ɂ��Ă͔����ɋg���m�B
�@�����̐l���A�V�c�̂��肩���u�����N��v���`����Ă������̂ł��B
�@���a�V�c�̂����i�ɂ��Ē��҂́u�ȒP�ɂ����ΓV�c�́A�������n���ɂ����Ɛςݏグ�Ă����A���̍ہA��_�������낻���ɂ��Ȃ���������ފw�ҁv�I�ȃ^�C�v�ł���B�����ď�Ɍ����ɒ����ŁA��̂��Ƃ��͂��߂��猈���Ă�߂Ȃ��B���X�����ׂ������͂������Ă���B�v�ƌ����Ă���܂����A���̂��Ƃ��S�҂ɂ킽���ĕ`����Ă��܂��B
�@�V�c�͂��������ƍَ҂ł��邩�̂悤�Ȉ�ۂ������Ă���l�����܂��B�ŋ߂ł́A�����h��Ƃ������Еs���̐l���u�������͓V�c�̂悤�Ȃ��́v�Ƃ������������Ă��܂������A����Ȃǂ͂��̓T�^�ł��傤�B���̑������ׂ��ƍَ҂Ɣ�r���邱�Ǝ��̂��s�h�Ȃ̂ł����A�V�c�ɑ��ĂȂ�ƂȂ��I�[���}�C�e�B�̈�ۂ������Ă��邩��Ȃ̂ł��傤�B�������A�䂪�V�c�͌��@�̉��̌N��ł������킯�ŁA�����g������U�������ꂽ�̂ł��B
�@���ӌ��₲��]�ɗނ��邱�Ƃ��k�炳��邱�Ƃ͂����Ă��A�����킹�邱�Ƃ͑S������܂���ł������A���t�̌��莖���ƂȂ������̂ɂ��ẮA�K����ى���Ă��܂��B���ɁA�����푈���~�߂�ꂽ�͂����A�ƌ�����ꍇ������܂����A����͏o���Ȃ����A�Ȃ���Ȃ��킯�ł��B�܂��A�푈�i���ρj�̊J�n�ɂ������ČR���̓Ƒ��ł������Ɣ���邱�Ƃ�����܂����A��������肦�Ȃ��̂ł��B���̖{������p���܂��i332p�j�B
�����p��
�@���ɂȂ�ƁA�u�R���Ƒ������v�u�R���������v�u�������͓Ɨ����Ă��邩��A��������������Ȃ������V�c�̐ӔC���v�Ƃ������ƂɂȂ�B�����A�u�R�̓Ƒ��v�ȂǂƂ������Ƃ͌����ɂ͂��蓾�Ȃ��B
�@�����g�A�R�̉������Z�ŁA�����{���ɂ�������悭�m���Ă��邪�A�u�\�Z�v���Ȃ���Ή����o���Ȃ��̂͑��̊����ƕς��͂Ȃ��B�R���܂��c��Ȋ����@�\�ł���B�ȒP�Ɍ����ΎO�x�̐H�������A���K�́u�H���`�[�v���˂Ύx������Ȃ��B�핞�E����E�e��E���q�͂������A���Ԃ̌R���Y�Ƃ���̍w���ł���A�ړ��ɂ͑S�ĉ^�����Ă���A�c��ȋ������x�����Ă���B���̈�劯���@�\���u�\�Z�v�Ȃ��ɓ������ȂǂƂ������Ƃ́A���Ƃ��s�\�ł���A���̗\�Z�́A���t�ƒ鍑�c������Ă���A�R�������Ă���킯�ł͂Ȃ��B
�@�u�Ƒ��v�Ƃ������A�R�Ɠ��t���u�썇�v���Ă��u�鍑�c��v�̏��F���Ȃ���A�R�͓������Ȃ��B���͂��̎��o���������̂��R�ł���A���̎��o���Ȃ������̂������ƂŁA���̓T�^���A�u�s�g����j�v�𐺖����Ȃ���u�g��\�Z�v��g��ł����߉q�i�����j�ł���B
�d
���t�͋c��̐M�C�ɂ���Đ������Ă���̂�����A���̌�����i�V�c���j���ۂ��邱�Ƃ́u�^�e�}�G�v���猾���A�V�c�ƍ����Ƃ̐��ʏՓ˂Ƃ������ƂɂȂ�d�B
�����p�I��
�@�V�c�́A�`���ɋL�����悤�ɁA�܂��Ɂu�H�L�̐l�v�ł��B
�@���{���A���{�����̂����̂ݔO���ɂ����āA������ɂ߂钆����ɗ�ÂȊώ@�Ɣ��f������A�Ō�ɂ́A�����̐g�������o���ꂽ�̂ł��B
�@�u�����v�ł��邱�Ƃ̐����������ɕ\��Ă���Ǝv���܂��B����́A�V�c�łȂ���ΐ�ɏo���Ȃ����Ƃł��傤�B
�@�܂��Ɂu�H�L�̐l�v�ł��B
|
|
|
20.5.15
|
��ׂ����a�V�c�^���{����^�����V���� |
|
 �@���{�ɂ��čl����ہA�V�c�̑��݂��͂������Ƃ͂ł��܂���B�ߋ��ɂ����Ă��܂����݂ɂ����Ă���ɓ��{���̒��S�Ƃ��đ��݂���A���ƂƂ��Ă̑傫�ȕ����]�������߂���ǖʂȂǂŏd��Ȍ��f�����A�䍑�̈��ׂ�����Ă����Ă����ł��B
�@���{�ɂ��čl����ہA�V�c�̑��݂��͂������Ƃ͂ł��܂���B�ߋ��ɂ����Ă��܂����݂ɂ����Ă���ɓ��{���̒��S�Ƃ��đ��݂���A���ƂƂ��Ă̑傫�ȕ����]�������߂���ǖʂȂǂŏd��Ȍ��f�����A�䍑�̈��ׂ�����Ă����Ă����ł��B
�@���m�e���a���̂����t�Ɂu�V�c�Ƃ����̂͑傫�ȐU��q�̎��̂悤�Ȃ��̂ŁA���̒������E�ɐU��Ă��A��ɓ������ɐ��̒��̒����Ɉʒu���Ă���B�����Ď��ł��邩��A�U��q�����ɖ߂錴�_�ɂȂ��Ă���B�v�Ƃ����̂�����܂������A�܂��ɂ��̒ʂ肾�Ǝv���܂��B
�@��O�A���a�V�c�͐_�i������u�ꑽ���v���݂Ƃ���Ă��܂������A���͓V�c�����g�͋ɂ߂č����I�ȍl�������������ŁA���̂��Ƃ��i���t���v�������т܂��j�a�܂����v���Ă���ꂽ�悤�ł��B�X�ɂ́A���ɍ����o�����X���o�ƐӔC�����������ŁA�哌���푈�Ɋւ��č��S�̂�������q�ɂȂ��Ă�����̂Ȃ��A������l��Âɂ��̐��ڂ����Ă����܂����B
�@�܂��A�i���R��������܂��j���������������Ă����A�A�����J�ւ̂����s�̍ہA�}�b�J�[�T�[�̕�̋߂��܂ōs���ꂽ�ۂɁA�⑰����̏��ق��������̂ł����A����ɉ������Ȃ����������ł��B�I�펞�A���Ƃƍ����̂��߂ɂ�ނȂ��}�b�J�[�T�[�����̂��Ƃɂ����łɂȂ�܂������A���̎��̋��J�I�Ȏv���������Ă������ꂽ�̂ł��傤���B�i�l�Ƃ��Ă̋��J���Ƃ�����荑�ƍ������\����V�c�Ƃ��Ă̋��J�Ƃ����������Ǝv���܂��B���Ƃ��A�V�c�ɂ́u���v�͂���܂���B�j���������_�ɑ�ϋ����ӎv�̗͂����������܂��B
�@���̑��A���a�V�c�̐����i��ׂ����j�����炽�߂Ēm�邱�Ƃ��ł��܂����B���̍���̎���ɂ�����ׂ�����������ꂽ���ƂɊ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B
�@���āA��L�̂��Ƃ���ɂ��܂��������肵�Ă���̂����̖{�Ȃ̂ł����A��_�A���������Ȃ��_������܂��B���̂��߂ɂ��̖{�́A���ɂƂ��ẮA�S�̂̉��l�������������̂ɂȂ��Ă��܂��܂����B
����́A2006�N7���ɓ��{�o�ϐV�����X�N�[�v�����u�x�c�����v�ɑ��邱�̒��҂̕]������ϓK�������_�ł��B
�@ �u�`����Ƃ̍��J�v�ɓV�c���u�s�����v�������A���̂��߂Ɂu�����Q�q���Ȍ㒆�~�v����A�u���ꂪ���̐S���v�Ƃ��ꂽ�̂��Ƃ����A���̎��Ăł��B
�@���҂́A���̕x�c�������u�^���v�ł���Ƃ��āA�����_���Ƃ��Ę_��i�߂Ă��܂��B�������A���̘_���ƂȂ��Ă���̂͐V������ɔ��\���ꂽ�����̃����i�蒠�̈ꕔ�j�ł��B�O���������Ȃ����A�����̎蒠�́A���̐V���Ђ��ۊǂ��Ă���A������ׂ����I�Ȓ���������Ă����ł͂���܂���B���̂悤�ȁA����ӂ�Ȃ��̂��������ɂ��āA�V�c�́u�S�v��f�肳��Ă���Ƃ������Ɏ��ɂ͌����܂��B�w�҂Ƃ��Ă������Ȃ��̂ł��傤�B�܂��A���ɂ�����`����Ƃ̈ꕔ�ɑ��ĕs���������Ă����Ă��A���ꂾ���łQ�O�O�����ɋy�ԉp��B�ɂ����Ƃ������Ƃ�����̂ł��傤���B
�@���̓_�A���҂͊Ԉ���Ă���A�Ǝ��͎v���܂��ˁB
|
|
|
20.5.1
|
�哌���푈�̓A�����J�������^��ؕq���^�ɓV�� |
|
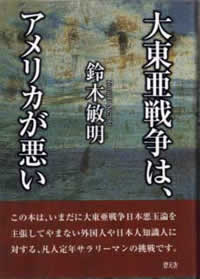 �@�V�R�T�y�[�W�̑咘�ł��B �@�V�R�T�y�[�W�̑咘�ł��B
�@�哌���푈�Ɏ�����j���A�����s���Ă��鎩�s�j�ρ^�����ٔ��j�ς̔��Α��̗��ꂩ��A���ؒ��J�ɋL�q���Ă���܂��B
�@�����āA�����ׂ����ƂɁA���̒��҂͂�������j�ƂȂǂł͂Ȃ��A���{�l�̌��t�ł́u���̒�N�T�����[�}���v�Ȃ̂ł��B��x���{�ȂǏ��������Ƃ͂Ȃ����������ł����A�T�X�̂Ƃ��i1997�j�Ɖi�ٔ��i���ȏ����j�̍ō��ٔ������V���ɍڂ��Đ��Ԃ𑛂����Ă������߁A�ނ̒�����ǂ����ł��B�����āA���̂��܂�ɂ��Ђǂ����{���̓��e�ɓ{��������A�{���������Ƃ����S���������ł��B
�@���d���͏��ЊW�ł������悤�ŁA���O���ɑ��銴�o�͍��ۓI�Ȃ��̂������Ă���ꂽ�킯�ł����A���̏�ɁA���������S�ƁA�X�ɋ����ӎu�̗͂���������Ă����Ƃ������Ƃł��B���҂͔��ɑ����̖{�����ǂ݂ɂȂ��Ă���A�����𒀎��Q�Ƃ��Ȃ���A�ǎ҂ɑ��đ哌���푈�̉ߒ�����₷���������Ă���Ă��܂��B
�@���b���̃e�[�}�́A�������q���̒��ōu�������Ē����Ă�����̂ƑS�������ł���܂����A���Â��̌��݂��啪�Ⴂ�܂��B
�@���̃e�[�}�́A�v�����ĒZ��������ƁA
�u���\���ςȔ��l�v�Ɓu���Ԃł��l�悵�̓��{�l�v�A�ڊo�߂���{�l�B
�Ƃ������Ƃł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�i���҂́A�u���ԂŃo�J�ł��l�悵�̓��{�l�v�ƔO�������Ă��܂��B�j
�@�������ɂ��̂Ƃ���ł����A�u���\���ςȔ��l�v�������ς��Ȃ��Ɠ����悤�Ɂu���Ԃł��l�悵�̓��{�l�v���A�؋��������Ă��܂��B���������C���̂悤�Ȃ��͍̂�����݂ɂȂ��Ă��āA�Ȃ��Ȃ��ς��Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���܂��B�������A������Ƃ����āA�Ȃɂ��{���Ȃ���Ȃ����P�͓����Ȃ��킯�ł��āA����ɖڊo�߂�l����l�ł��������Ƃ����w�͂��K�v�ƂȂ�܂��B�G�́A���̋C���s���Ă��ɂ������䂭�������킯�ł����A��X�͂���������ł��ς��Ȃ���Ό�ނ������ɂȂ��Ă��܂���ł��B
�@
�@���̖{�́A���̓_�������ӎ����ꂽ�J��ł��āA���̓_���܂��⊶�Ȃ���������Ă���܂��B
�@���Ȃ݂ɁA���̖{�͒m�l����ؗp���ēǂ̂ł����A���ɐ�łɂȂ��Ă��܂��āi�o�ŎЂ��p�ƁH�j��ɓ���邱�Ƃ��ł��܂���B�A�}�]���̒��Âׂ��琔���~�̒l�����Ă���܂����B�Ȃ�Ƃ��A�~�����{�ł��B
�@���̖{�̓��e�Ɋւ��āA�S�ғ��ӂ�����̂ł����A�P�_������a���������܂����B
�@����́A���҂����ӏ����ŏq�ׂ��Ă���u���{�l�̋C���̍���ɂ���̂��A�w�吨�}����`�ł���x�Ƃ����_�ł��B���̌ꊴ�����̂́A�ڋ��ɂȂ��Č��͂ɂ����˂�Ƃ����p�ł��B�m���ɂ������������ɂ��Ȃ�Ǝv���̂ł����A���͂����ł͂Ȃ��A���R�ɋt���Ȃ��A���邢�͎��R�ɂ͋t�炦�Ȃ��Ƃ������ς̂悤�Ȃ��̂����{�l�ɂ����āA��������A�傫�ȗ���ɂ͂��Ƃ���ɋt���Ȃ��������A�a���d�����鐶�����ɂȂ��Ă���A�Ƃ������Ƃł͂Ȃ����A�Ǝv���̂ł��B�������Ƃł��傤���A�ڋ��ȓ��{�l�Ƃ�����̂Ă�悤�Ȍ����́A�������Ȃ��Ǝv���܂��B
�@�������A������ɂ���A���̍l�����́A���l�D�ʎv�z�ŗ���ł܂������ێЉ�ɗ����������ɂ͑S���s�K�ł�����A���̓_���ӎ����v���Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����_�Œ��҂Ǝ��͈�v������̂ł��ˁB
|
|
|
20.4.15
|
�e�ƈ��̕���^�����{�܊�v�q�^�������� |
|
 �@��v�q�ܓa���͍Ō�̏��R����c��̂Б��ɓ�����܂��B�c���̎��Ɍc��ɕ����ꂽ�ʐ^������܂����A��{�l�ɂ͌c��̋�̓I�Ȏv���o�͂Ȃ������ł��B�P�W�ō����{�a���Ƃ������B �@��v�q�ܓa���͍Ō�̏��R����c��̂Б��ɓ�����܂��B�c���̎��Ɍc��ɕ����ꂽ�ʐ^������܂����A��{�l�ɂ͌c��̋�̓I�Ȏv���o�͂Ȃ������ł��B�P�W�ō����{�a���Ƃ������B
�@���̖{�ł́A����Ȍ�̐F�X�Șb�肪����Ă��܂��B�����ǂނƁA�c���̕��X�̐����Ƃ����̂͑S���_�̏�̂��Ƃł͂Ȃ��A������O�̂��Ƃ�������܂��A���I�ȕ����ł͉�X�Ɠ����ȂȂ��Ƃ��������������܂����B
�@�펞���͐H���̊m�ۂ���ςŁA��������Ă����܂����B�����܂ł��Ȃ��Ƃ��ǂ������̂����m��܂��A�����B�������ʂƂ����C�����ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ�������ɂȂ����Ƃ������Ƃł��B����ɂ��āA���̂悤�Ȉ�ۓI�ȃG�s�\�[�h��������Ă��܂��B
�@�푈���I���ɋ߂Â��A�T���Q�Q���̋�P�ŋ{�����{�䏊�������{�@���S���ۏĂ��ƂȂ�A�����{�@�݂̂����������B�{����S���Ă����Ƃ����̂Ŋ�v�q�܂��}篁A�c���@�i�喾�c�@�j�̂Ƃ���֎Q�サ����A�h�̒��ɂ����āu����Ŏ��������Ɠ����ɂȂ����v�Ƃ���ꂽ�����ł��B����ɑ��āA��v�q�l�͂��̂Ƃ��A�u���������c���Ă��܂��Đ\����Ȃ��A�Ƃ����z�����������̂ŁA�����������ďĂ��Ă��܂������A�����v�����̂��͂�����o���Ă��܂��B�v�Ƃ������Ƃ������������ł��B
�@���̑��A���̂悤�ȃG�s�\�[�h����������̂ł����A�����̎��I�ȕ����͓���ł͂����Ă����ʂł͂Ȃ��Ƃ����ƂŁA����A���I�Ȗʂł́u�����炩�ɖ�������v�ɓO���Ă�����Ƃ������Ƃł��傤���B
�@���������A���͍����{�a���̂����t������������܂���B��������܂���A�ȂǂƂ����������͑�ώ���Șb�ł����A�厖�Ȃ����h�Ȃ��ƂȂ̂ɂǂ����ǂ��o���Ă��Ȃ��̂ł��B���m�q�C�ɏo������O�ɁA��X�V�ĂR�т́A�o���O�̂����A�̂��߂ɍc���ɎQ�シ��̂ł����A���̍ۂɂǂ����̂���Ńp�[�e�B�����Ă��������܂����B���̃p�[�e�B�ŁA�a���̋߂��Ƃ���ɋ������͊m���ł����A�����ڕ������悤�ȕ����Ă��Ȃ��悤�ȁA����Ȋ����Ȃ̂ł��B
�@�p�������Ȃ���A�S���̎�C�̎���ŁA�c���ɂ��Ă̗��������Ă��Ȃ������̂ŁA�L�����肩�łȂ��̂ł��B�܂�A�قƂ�Njْ����Ă��Ȃ������̂��Ǝv���܂��B���l����Ɩ{���ɐԖʂ̎���ł��B
|
|
|
20.3.30
|
���s�̒����ߑ�j�^�ʋ{�g�N�^���؏��[ |
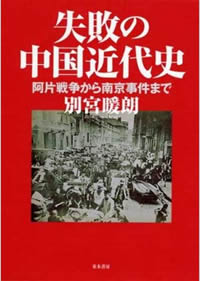 �@�����ߑ�j�͎��s�̘A���ł������A�Ƃ������Ƃ҂͏q�ׂĂ����̂ł����A�ǂ����Ăǂ����ē��{������ɗ�炸�O��ʂł̐ٗ��ڗ����܂��B�����Ȃ�A�V�i�͍�������̈��i���j�ŁA���{�͂ǂ����悤���Ȃ����l�悵�Ƃ������Ƃł��傤���B �@�����ߑ�j�͎��s�̘A���ł������A�Ƃ������Ƃ҂͏q�ׂĂ����̂ł����A�ǂ����Ăǂ����ē��{������ɗ�炸�O��ʂł̐ٗ��ڗ����܂��B�����Ȃ�A�V�i�͍�������̈��i���j�ŁA���{�͂ǂ����悤���Ȃ����l�悵�Ƃ������Ƃł��傤���B
�@�����̍s���̌��_�͒��؎v�z�ɂ���Ǝv���܂����A���������̓I�ɉ�������̂��A�u�܂������v�ɂ��鎟�̂悤�ȕ��͂ł��B
�����p�J�n��
�@���{�ƒ����Ƃ͍��̂�������S������Ă����B�d�d�]�ˎ�����O�A���{�ɂ����銯���́A�l���̂T���ȉ��ɂ����Ȃ����m���Ɛ肵�Ă���A�����P�ł������B�����ł́u�ȋ��v�ƌĂ��������C�������Ŋ����͑I�����ꂽ�B�d�d�ȋ��̎������e�́A�l���܌o���玞�����ɂ��Ẳ�������A���ҕ��i�͂����Ԃ�j�Ƃ����C���ɏ]���ď����グ����Ƃ������̂ł������B
�@���̓��e�ɂ��Ă̒����A�����ɂ������������݂�̂ł͂Ȃ��A�Ñ�̌��_�Ɍ�����������߂�K�v���������B�}���N�X��[�j���̒��삩���������A�R�[�������猋�_���o�����肷��A���Y��`��C�X����������`�ɂ悭���Ă���B���������ɍ��i���������́A�������e�ɔ����鐢�E�ςɂ͓O��I�ɔ��R����A�㉺�W�����Ȃ���������o��ꂸ�A�L�����E�ɏo�邱�Ƃ�������A���z��蛁i����낤�j�̍l�����ɂƂ���A�l���ɂ����������������A�`����芯�E��D���܂��Ƃ���B
�@�D�D�����������ƌR�����܂߂đS���E�I�Ȑl�̈ړ����n�܂����B�ȋ������͂��̐��E�ς���A���������O���l�Ƃ̑Γ��̌��ۂ��ł��Ȃ������B�O�����̂��̂����ۂ����̂ł���B�d�d�����͂��������̑Γ��O�������ۂ����B���R�͒P���ŁA�l���܌o�ɂ͊O�̍v��ɂ��Ă̋K�肵���Ȃ��A�c����ȋ��������ΐl�ƑΓ��̌��ۂ��������ŖS����Ǝv���Ă��Ă��܂����̂��B
�@���������̓������@�Ƃ́u��y�v�ł���B�u��v�Ƃ͓��{��̈Ӗ��ƈقȂ�V����ʂł���A�u�y�v�Ƃ͉��y�ł������B�d�@�d
�@�����l���炷��A�u�����n��v�̍��ɁA���{�l�Ɖ��Đl�����������A����Ȃ��Ƃ������̂ŁA�ӔC�͑S�ĊO���l�ɂ���Ƃ݂���̂ł���B�����āA���������ł��邽�߂ɂ́A�����l�́A�����ƕx�T�łȂ���Ȃ炸�A���������������x�T�Ȑl�X�͎��i�˂��j�܂����B�d�@�d
�@����A�C�f�A�������l�̔]���ɑM�����B����́A�u�������ߑ㉻�ł��Ȃ��̂͊O���l�̂������v�Ƃ����ӔC�]�łł������B���{�͔r�O��`��`���s���A���������̎����͊O���l�̂������Ǝq���ɋ������B�����l�ɂƂ��ĂQ�O���I�́A�O���l�̔��W���������i�ŖW�Q��������ɂȂ����B���{�l�Ɖ��Đl�͒����ɂ����Ď�噂̂悤�Ɍ����邱�ƂɂȂ����B
�����p�I�聄
�@����ɂ��̈��ʂ�T�邱�Ƃ��ł���ł��傤���A����ŏ\���Ǝv���܂��B
�@���������l�����A�܂��ɂS��N�Ƃ��������Ԃ������č��̐��܂ŐZ�����Ă����ł�����A�����I�ɘb�������ŕ������������܂��傤�ȂǂƂ������Ƃ́A���ƂQ��N�Ԃ��炢�͖����ł��傤�B
�@���̖{�ɂ́A�A�w���푈�`�싞�����܂ł𑨂��āA����ȃV�i������Ă��܂������s�̓^�����`����Ă��܂��B
�@�����������Ǝv���܂����A�u�V�i�͈�l�̍c��ƍ��̂悤�Ȑl������Ȃ��Ă���v�Ƃ������t������܂����A�`�̎n�c�邠���肩�璆���̌Ӌџ��Ɏ���܂ŁA���̃g�b�v�ɂ������l�����́A�l�����������x�ɂ����v��Ȃ����ɂ̗��ȓI���݂Ƃ��Ă̍c���ڎw�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�i�l�������l�����ŁA��������Ƃ������Ƃ̂Ȃ����ɊÂ������̂ł��B�j
�@������Ӊ�͓��{�Ƃ������[�������悤�ŁA���{�l�̃V���p�������̎x����ɂ��܂Ȃ������̂ł����A���ǂ͎��ɂ�������Ɨ����Ă��܂��B����A�ނ��뒆���l�Ƃ͂��������l��Ȃ̂��Ƃ������Ƃ��A���l�悵�̓��{�l�ɂ͌����Ȃ������Ƃ������Ƃ�������܂���B
�@���ɁA�ǂ������A�̐S�̊O���Ȗ�l�ɂ��̕ӂ̔F�����������l�������y�o���Ă���͎̂c�O�Ȃ��Ƃł��B������d�Y��L�c�O�B�ȂNJO�������オ��̊O����b���A���v��������������ɏ�������ȂǑ傫�Ȏ��s���d�˂܂����B�O�Ɂu�����R��v�Ƃ����{��ǂƂ��A���̖{�ɂ͍L�c������Έ̐l�Ƃ��ĕ`���Ă��邱�ƂɈ�a�����o�����̂ł����A��͂肻�����������Ƃ��̖{��ǂ�ō��_���s���܂����B�����A����Ɉ����ʂ��A���c�A�����A�R��Ȃǂ̋c��������ɋ߂��̂�������܂���i����ȏ�H�j�B�O�������o�g�̉����h��Ȃǂ����̍ʼnE���ł��傤�B����������ƁA�����̗l�q��������x�����ł��܂��B�ނ�̌������炷��Ζ��B���ϓ����̊֓��R�̍s���₻����x�����������̍����̑��݂��킩��܂��B
�@���̖{�́A���Ɛ��I�ŁA�����̃V�i�Ɋ��������R�����x���̌�����t�c���x���̌R�̓��������`���Ă���A���ꂾ���ɕt���čs���̑�ςł��āA���S�ɗ����o���܂���ł����B
������x�ǂނ��Ƃ��g���C�������Ǝv���܂��B
�@
|
|
|
20.3.15
|
�_�͖ϑz�ł���|�@���Ƃ̌��ʁ^���`���[�h�E�h�[�L���X�^���쏑�[ |
|
 �@�Ȃɂ��̏��]��ǂ�Ŏ�ɂ����{�ł��B
�@�Ȃɂ��̏��]��ǂ�Ŏ�ɂ����{�ł��B
�@���͐}���ق𗘗p����̂��قƂ�ǂł��āA���̖{�͂��̐}���قŗ\������Ď�ɂ����̂ł����A�\������Ă����ɂ���܂ł��Ȃ�̊��Ԃ�������܂����B����قǓǂ܂�Ă���Ƃ������Ƃł��B
�@�������A���͂P�O���̂P�قǂ�ǂ�Ŏ~�߂Ă��܂��܂����B�O�]���̊��ɂ͋������o���Ȃ���������ł��B�����A���̑O�ɂ��̖{��ǂ������������悤�Ȋ��z���������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�Ƃ��낪�A���̖{�̐�`����ɂ́A�u����������S�ăx�X�g�Z���[�ƂȂ������b���v�Ƃ���܂��B
�@�ʔ����Ȃ��{�����b���H�@
�@
�@�Ȃ����Ƃ����ƁA�A�����J�l�ɂƂ��ẮA���̖{�͈ӕ\�����悤�Ȗʔ���������̂ł����A��X���{�l�ɂƂ��ẮA�܂�ʂ��Ƃ�傰���Ɍ�������Ă���Ƃ����v���Ȃ�����Ȃ̂ł��B
�@
�@���̖{�̃e�[�}�́A�����������u�@���͎̂Ă���A�������K�v�͖����A�Ȃ��Ȃ�_�͂��Ȃ����炾�v�Ƃ������̂Ȃ̂ł��B
�@�{���̂P�O���̂P�Ɩڎ������ǂ�ł��Ȃ��̂ł����A�����Ȃ��Ƃ��l���������܂����B
�@��{�I�ɂ܂��v���̂́A�u�@�����̂Ă�v�Ƃ����_�ɑ���^��ł��B��͂�A���ꂪ�ǂ̂悤�Ȃ��̂ł���ɂ���A�l�Ԃz����Ȃɂ��̂��̑��݂ɑ���u��v�Ƃ������̂��Ȃ��ƁA�܂����̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃł��B���̐l�ԊE�A�l�q�̋y�Ȃ����̂��Ƃ┒���t�����Ȃ��O���[�̕����▵�����炯�̂��Ƃ╡�G�����ĉ����ł��Ȃ����ȂǂȂǂŖ��������Ă��܂��B�Ƃ��낪�������꓁���f�������Ă����̂��@�����낤�Ǝv���̂ł��B���ꂪ�Ȃ��ẮA�ꂵ���ċꂵ���Ă��܂�Ȃ��Ǝv���̂ł����ǂ��ł��傤�B
�@���Ɏv���̂��u�L���X�g���ł����_�͒m�炸�A��X���{�l�������Ă���J�~�͗ǂ��Ȃ��v�Ƃ������Ƃł��B�i�t�Ɍ����ƃL���X�g���k�͉������B�j
�@���_�������C�X�������������ł����A������u�B���ΐ_�v�Ȗ�ł�����A���ꂵ���đ����l�܂肻���ȕ��͋C������܂��B���ꂪ�ɒ[�ɑ���ƁA�����錴����`�Ƃ����킯�ł��āA��Ɏ����B�͐������Ă��̂ق��̂��̂͐�ɋ����Ȃ��B���������āA���ɂɂ͑����r���i�E�j���Ă��܂�Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����Ƃ���ɍs���B����̍l���⑶�݂�F�߂�Ƃ��������炩���̕��������Ȃ菟���ȌX��������悤�Ɍ����܂��ˁB
�@���̓_�A���_���Ƃ����̂͗ǂ��Ǝv���܂��ˁB�����Ȑ_�l�������ȏꏊ�ɋ��ĉ�X�l�Ԃ����Ă���A�Ƃ����l���ł��B�������������A�֏��ɂ��_�l������i�֏��̐_�l�j�A�����牘���Ă͂����Ȃ��Ȃǂƕ�e���猾��ꂽ���Ƃ�����܂��B���v���A�q���Ȃ���Ɂu��v�������܂����B���炭�́A�֏��ɍs���ƁA�ǂ��ɐ_�l������̂��낤�ƁA�֏��̋��X��ڂ��Â炵�Ă݂����̂ł����B
�@����͏����ȗ�ł����A�����������Ƃ�ʂ��āA��̂��玄�B�͎����B�̐����𗥂��Ă����킯�ł��B�i�u���V���l�����Ă���v�Ƃ����̂́A���̑�\�ł��B�j
�@�P���ł����A�|�C���g�͉��������Ă���悤�Ɏv���܂��B�Ȃɂ��������炩�ȓ_�����i�B�j�ɂ͂҂�����ł��B
�@�Ƃ��낪�A��_���ł͗B���̐_�Ƃ̌_��̉��Ɏ����B�����݂���A�Ƃ����������肵�����������āA��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B������A�A�����J�l�́u�_�v�ɔ����Ă��邱�Ƃł����Ă��܂�Ȃ��̂ł��ˁB���_���ȂǂƐl���猾����̂́A�����z����₷�邱�ƂȂ̂ł��B�����ŁA���̂悤�Ȗ{���u���b���v�́u�x�X�g�Z���[�v�ɂȂ��ł��B�ǂ�������A�_�̑������瓦�����邩�A�ƁB
�@�ŋߓ��{�̕����͂�A�o���ׂ����Ƃ����n�i�V������܂��B����́A�����A�j���A���������Ȃ����_�A���Ȃǂł����A���̑��_�������E�ɍL�܂�����ǂ��Ƃ������܂��ˁB
�@����ɂ��Ă��A���̓_�ɂ��ẮA���{�ɐ��܂�Ė{���ɗǂ������Ǝv���܂��B
|
|
|
20.3.1
|
�����ƍ]�˕���-�����̓�-�^�}��r��^�Y�R�t�o�� |
 �@�Ȃ��Ƃ������H
�@�Ȃ��Ƃ������H
�@�����Ă���̂́A�@�l�i���i�Q�~�W���P�U���j�A�A�z������i�����W���A�Ȃ��Q���j�ł����A���ɋL�����R����킩��܂��悤�ɁA�����Ƃ��Ɋ��S�ł͂���܂���B
�@�@�̒l�i���ɂ��Ăł����A�����Ƃ������t���g����悤�ɂȂ����̂͋��۔N�ԁi1725���j�ł����A���̍��ȍ~�̒l�i�͂W�����x�łP�U���ɒl�グ�ɂȂ�O�ł��P�Q���ł����������ł��B�P�U���ɂȂ�͕̂����̌㔼�i1811���`�j�������ł��āA�c�����N�i1865�j�ɂ͍X�ɒl�オ�肵�ĂP�U���ł͂Ȃ��Ȃ邻���ł��B���������āA�������H���ꂽ�P�S�O�N�̒��ŊY������̂͂T�O�N���x�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B����āA�l�i���́u�H�v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�@���ɇA�̔z������ł����A���������Ȃ�A����Ƃ����ׂ��ł��낤�̂ɂ����Ȃ��Ă��Ȃ����A����I�Ȃ͓̂��ǂ�A��Z���ǂ�ȂǂƂ������t������A�Ƃ������Ƃł��B���ǂ�ɔz����͂���܂���A�A�̔z��������u�H�v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�@�����ŁA���҂͎��̂悤�ȉ����𗧂ĂĂ��̗������݂܂��B���ǁA����I�ȏ؋����Ȃ��T�̗Ƃ������ƂɂȂ�̂ł����A���Ƃ��Ă͑傢�ɔ[�����܂����B�؋��ƂȂ镶�����Ȃ��̂́A����������������������O�߂��Ă���������Đ�������Ƃ����K�v���Ȃ���������ł��B�u�Ȃ��w��ł��x�Ƃ������v�Ƃ�����Ɏ��Ă��܂��B
�@���āA���҂����Ă������́u�Q�t�łP�W���Ƃ������ƂŁA�P�O���ȗ�����āA�ƌ���ꂽ�B�v�Ƃ������̂ł��B
�u�Q�t�Łv�ɂ��ẮA�Q�t��H�ׂ�Ƃ����̂��ʏ�̎p�ł��������Ƃ��A�����̂Ȃ�킵�A����A�G�ȂǂŐ�������Ă��܂��B���Ƃ��ƂP�t�Ƃ����̂͊��ނׂ����Ƃł����B���l�̖��сi�܂���߂��j���P�t����A�o���̑O�ɋߐe�҂��H�ׂ�o���сi�ł����߂��j���P�t����d�B����i�������낤�j�ł������A�Q�t�͓�����O�łR�t�ڂ������Əo�����킯�ł��B
�@
�@�ŁA��t���X���ł�����A�Q�t�łP�W���B
�@�ł͂Ȃ��P�O�̈ʂ��ȗ����Ă���̂��A�ɂ��ẮA�������邱�Ƃ������͋ɁX������O����������ł��B�ڋ߂ȗႪ�N������ŁA�u�������ł����H�v�u�Q�ɂȂ�܂��v�Ɠ�����T�Q���U�Q���͌��ĕ����邩�猾��Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B���̏ȗ��͐����Ɍ��炸�A�F�X�ȂƂ���ōs���Ă��܂��B�u���킸�ƒm�ꂽ�d�v�Ƃ������ƂȂ̂ł��B
�@���̌�A�����̏㏸�ɔ����A���Ɉ�t���P�U���̎���ɂȂ�A���̍ۂɂ́A�E�\�Z�̊|���Z�̎g�����ɂȂ�܂��B�����Č���́A�����ς�z����̓ɂȂ����A�Ƃ�����ł��B
�@�������e�[�}�̖{�ł����A�]�˂̐l�����̍l�����A�l���ς̂悤�Ȃ��̂�������܂����B���ɏȗ��̔��w�B�l�̌܂̂����������킸�ɁA�X�p�b�Ɨ����āA������y���ށd�B
���̖{�̃v�����[�O�Ɏ��̋L�q������܂��B
�@�u�]�˕����̃L�[���[�h�̂ЂƂ́A���i�����j�i�ӋC�j�B���́u�V�с\�V�ѐS�v�ɍ炢���������ԂƂ������܂��B�l�X�͖L���ȗV�ѐS�ɐ����܂����B
�@���͂܂��A������������Ƃ�S�ł�����܂����B
�@�u����i�C�L�j�Ƃ��ӎ��́A���ɂ��������Ђ��Ƃ��Ӌ`��v�i���i�W�N�w��ʖ@��x�j
�@����́A�����炳�܂łȂ��A��Ђ˂����Ђ˂������������ƋC�̗������V�ъ��o�ł��B����̌��t�ɂ��Ă��A����Z���X�A�V�ъ��o�����̑�ȕ����ł����B���t�̂Ȃ��ŁA�u���v�̃p�Y������E�V�ъ��o�͍]�ˎ���A�傢�ɉ₩�Ő���ł����B�v
�@�Ȃ��A�T�^�I�ȗ�Ƃ��Ắu�����\�L�v���ʔ����̂ňȉ��ɋL���܂��B
�@�u����̎��Ԃ̊�_�̌ߑO�뎞����c�ŁA�閾���������Z�c�A���v�����Z�c�ƂȂ�悤�Ɋ���t���܂��B��c���ߑO�뎞�ŁA���c�A���c�A�Z�c�A�܃c�A�l�c�܂Ői�݁A��������܂���c�ɖ߂��āA���c�A���c�Ǝl�c�܂Ői�݂܂��B���Ԃ����ɂ�Đ������������Ȃ�A�Ǝv���Ă���������قƂ�ǂł��傤���A����ȏ��Z�@�łȂ����Ԃ̐������ȂǁA���E���ɑ��݂��܂���B
�@�锼�i�^�钆�j�Ɛ��߂����ꂼ���c�ŃX�^�[�g����̂́A�Ղ̎v�z�ŋ�c�����ɂ̗z��������ł��B
��c�i�ߑO�뎞�E�ߌ�뎞�j�͋ォ�����ŋ�c�B���ꂩ��z���̋�ɂ����鐔�����A��A�O�A�l�A�܁A�Z�Ə��������Ȃ��Ă����܂��B
���c�i�ߑO�E�ߌ�j�́A�ォ�����ŏ\���B���̏\�͂킩�肫���Ă��邱�ƂȂ̂Ŗ��_�J�b�g���܂�����A���c�B
���c�i�ߑO�l���E�ߌ�l���j�́A�ォ����O�œ�\���B���̓�\�͂킩�肫���Ă��邱�ƂȂ̂Ŗ��_�J�b�g���܂�����A���c�B
�i�ȉ����B�l�c�܂Łj�v
�@�킩�肫���Ă���̂ŁA�����܂ŗ����Ă��܂���ł��B�����Ȃ�Ƃ����z������ł��Ȃ����E�ł��ˁB
�@
|
|
|
20.2.20
|
���� �]�˂̐H�����^�}��r�\�^��g���X |

�@�y�����E�Ƃ����̂́A���������{�������̂ł��傤���B����ł��āA���肰�Ȃ���������ׂ��Ƃ���͉������Ă���A���҂̒m���̕��Ɛ[�����悭������܂��B�����ƂȂ��Ă�������̐���ɑ����݂̐[���ƒf���������������͑�ύD�������Ă܂��B�������������́A���͍D���ł��ˁB
�@�����͍]�ˎ���㔼�ɔ����I�Ȕ��W�𐋂���̂ł����A���̔������������q��łȂ��Ƃ������Ƃ��悭������܂��B�����A�[�厛�Ȃǂ̎��ɋ��������̋Z�p���傢�ɔ��B���A���܂�����������A���ꂪ�]�˒��̐l�����ɑ傢�Ɏx������܂����B�����ŋ�����ł��A�����Ŗ�������葡���Ɏg�����肷�邱�Ƃ́A�����͂������ʂ̎p�ł������悤�ł��B
�@ �����ł���Ă݂�ƁA���܂�������łƂ����̂́A�Ȃ��Ȃ�����A�����̋Z�p���K�v�ł��i�����炱���A�ʔ����Ƃ����ʂ�����܂��j�B�������̐��N�A�����ł�����Ƃ��Ă���Ă��܂����A��S�̈�ł��Ƃ����̂��Ȃ��Ȃ��ł��܂���B
�@�����͍��ƈ���Đ����Z�p���Ⴉ�����ł��傤����A�����̋Z�p��p���đł����͂��ł��B
�@�����̋��������l���̍\���ɂ��āA���̖{��ʂ��ē������̃C���[�W�́A�̉��@��������[�厛�Ȃǂ̖V�������A�A�}�`���A�Ƃ��ċZ�p�̒Nj����Ƃ��Ƃ�s���A���x�̋Z�p�����グ�A���ꂪ�s��ɍL�܂�A���Ƃ⒬�l�̉ƒ�ł܂ł����ʂɑł����悤�ɂȂ����Ƃ������Ƃ̂悤�ł��B
�@���A���́u�Ȃ��w��ł��x�Ƃ����̂��v�A�u�w�R�V�x�Ƃ͂Ȃɂ��w���̂��v�Ƃ������ƂɊS�������Ă���܂��āA����Ɋւ���L�q���������܂��B
�@�u�łv�Ƃ������t�ɂ��Ă̒��҂̎g�������i3p�j
�@�u�����������˂đł��Đ��������������ƌ����A�₪�ċ����Ɨ������悤�ɂȂ�܂��B�v
�@�����҂́A�����ł���Ƃ��u���˂�v�u�łv�u��v�Ƃ����敪�ő����Ă��܂��B�܂�u�ʂ̏�ԂɂȂ����������������i�K�v�̂��Ƃ��u�łv�Ƃ����Ă����ł��B���̌������́A����̂��鍂���ȋ���������ɂ�鋼���k�`�̍ۂɂ��A�o�Ă������Ƃ�����܂����B�Ȃ��A�u�����v�̍�Ƃ̒i�K�����̂悤�Ɂu�łv�Ƃ������Ƃ����ƁA�˖_���W���Ă���ɈႢ�Ȃ��A�P���ł����A�_���g������u�łv�ƌ������̂ł��傤�B�]�˂��q�B�̂�����Ƃ������t�̗V�т��Ǝv���܂��B
�@�܂��A���҂́A�ʂ̂Ƃ���Ŗ˖_�̂��Ƃ��u�ł��_�v�ƕ\���i176p)���Ă���܂��āA���̐̂��炻���������������s���Ă����Ƃ������Ƃ��낤�Ǝv���܂��B
�@���łɁu��ł��v�ɂ���(117p)
�@�u�c�������Ɖ]�ւ邠��B���̎��ɂċ�������ɖ��Б��ɏ���A�c�����菊�X�ɂ���ł̐������������ҁA�ƍ����Έ��ƌĂԎ��ɂ͂Ȃ�ʁB�߂����ƂȂ�ǂ��A���̕��̗��s��肻�̖��̎n�܂�Ƃ͂Ȃ�ʁv�i���ґ����āj�Ȃ��A�����́u�������v�͌��݂ł͊������łȂ��E�G�b�g�ȃi�}�\�o�ƂƂ�ꂩ�˂܂��A�̂悤�ɂȂ������Ȃ��A�������S���́u�����i�����j�ł��v�̋����̂��Ƃł��B�v
�@���������͓����̂��ΐ�̍ō���ł���܂����B���̖��O�ɂ��₩���āA��ł��i�㓙�̂��j��łĂ�X�ł���Ƃ����Ӗ������߂Ĉ��Ƃ������O��������ł��B
�@�R�V�ɂ��Ă̋L�q�i215p�j
�@�u�]�ˋ����͏�����̋������A���U�i������j�̏�ɂ�����Ɣ����u���A�{�e�{�e�d�˂�͖̂��Ƃ��܂����B�����Ƃ��A�q��́w���̖��x�ɂ��A�w�]�˒��̋������͈�ƕ��ׂŁA�d�˂�̂�s���Ƃ����x�̂́A�V�ۈȍ~�Ƃ��Ă��܂����c�B
�@������d���グ�����A�O�{�����������Ă���Ȃǘ_�O�ł����A����Ȃ�Ɛ���d�˂�̂ł͂Ȃ��A���ʂȂ��狼���Ƌ����̊Ԃ��A����������邭�炢�̌��Ԃ�����悤�ɂ�◧�̋C���ɐ���܂����B�����Ĉ��炬��������̂́A�t�Ɨt�̊ԂɖؘR�����ʂ����Ԃ��������邩��ł����A���������̐�����̐▭�Ȍ��Ԃ��A���Ȃ₷�炬�A���났�������������̂ł��B
�@�����āA���̂悤�ȋ����̐��Ȑ���t���́A������������Ɛ����Ă��邩�̂悤�ɑR��ׂ��������܂��āA��������d�オ�肾���炱���\�Ȃ̂ł��B�v
�@���R�V�Ƃ������t�́A�ʏ�́A�ˎ��̂̌ł����̂��̂��w�����t�Ƃ��Ďg�p����Ă��܂��B��������������Ƃ��R���R����������Ƃ����Ƃ����g�����ł��ˁB���́A�Ȃ�ƂȂ��f���ɔ[���ł��܂���B�˂͌�����Ηǂ��Ƃ������̂ł͂Ȃ��A�Ǝv������ł��B���́A�u�R�V�����v�Ƃ������t���g���Ă���_�ɒ��ڂ�v����Ǝv���܂��B��ɂ�������Ă���ʂ�A�u����Ȃ�Ɛ���d�ˁv��ꂽ�����͂��܂�����܂���B�˂��K���ȁu�����v�������Ă���A���́u����v�̗͂Ŗ˂��ւ����Ă��Ȃ���Ԃ̂��Ƃ���������i�����j�Ƃ����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����Ă��́u����v������������̂́A�ˎ��̂̌ł��ɉ����Ė˂̓K�x�ȑ����ł���A�Ƃ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�˂��ׂ��ƁA���̍��i�����j�����������A�܂�ł������̂悤�ɂ��ɂႮ�ɂ�ɂȂ��Ă��܂��āA�S��������������܂���B�܂�A�R�V�Ƃ́A�K�x�Ȍ����ƓK�x�ȑ����ɂ�钣��i���́j�̂��Ƃł͂Ȃ����Ǝv���̂ł��B
�@
�@�u�łv�̂����ɂ��Ă͂��ꂱ��l�������Ƃ�����܂������A�P���ȉ��߂ŗǂ��悤�Ɏv���܂��B�܂��A�R�V�ɂ��ẮA�n�G����s���Ēʉ߉\�ȃ����O���ł���悤�ȁu���́v�̂��鋼���Ƃ������Ƃł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@
|
|
|
20.2.10
|
�]�˂��q�͂Ȃ������Ȃ̂��H�^���M��^�����АV�� |
 �@�ȑO�A���ҁu���M��v���̍u�����@�����܂��āA���̖{����ɂ��܂����B �@�ȑO�A���ҁu���M��v���̍u�����@�����܂��āA���̖{����ɂ��܂����B
�@
�@�{�̓��e�́A���̎��̍u���Ɠ������A�P�ɋ����̗��j��R�����Ƃ������̂ł͂Ȃ��]�˕����̒S����ł������]�˂��q�����̐����Ԃ�A�l�����Ȃǂɏœ_�ĂāA���������Ƃ̌W��荇����������₷���������Ă��܂��B���͂̎d���������i��ɕ����j���������Ȃ���A�������瓥�ݏo�����ƂȂ��s�Ȃ��Ă���܂��āA��ύD�������Ă܂��B���̑����̎Q�ƕ����̂Ȃ��ŁA���ʂ���̂�����ł��āA�����̐����Ɩ��������������������������Ƒh���点���Ă��܂��B
�@
�@���ɓ`��鋼������̕������˂ɂ��Ăł����A���ꂪ�`����A�������ꂽ�͈̂ӊO�ƍŋ߂̂��ƂŁA�]�ˎ���㔼�̕����������疋���ɂ����Ăł������悤�ł��B�]�˂͐V���̒n�ł���܂��āA����ƍN�������̒��S�Ƃ��Č��݂���킯�ł����A�ڏZ���Ă������Ƃ������x���邽�߂ɋߍ݂��炢���钬�l�����̗����������ď��X�ɔɉh�̓������ǂ��Ă����܂��B
�@���̖{�̃e�[�}�ł��鋼�������̔��˂ɂ��Č����ƁA�����́A����قǒ��ڂ����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�]�˂ł����ǂ�̂ł������悤�ł��B�܂��A���ǂ�Ɍ��炸����ݖ����̑����X�̂��̂��A�����牺�i�����j���ė������̂ł�����A�V���Ȃ��琭���̒��S�s�s�̏Z���Ƃ��ẮA�����̃R���v���b�N�X���������悤�ŁA���ꂪ�A�t�Ƀo�l�ƂȂ��āA���ǂ�ɑR������̂Ƃ��ċ�������Ă��Ă����܂����B���������̔��W�ɂ͂��̂悤�ȐV���s�s�Z���̔������_�����{�̗v���Ƃ��Ă���悤�Ɏv���܂��B
�@���̂悤�ɂ��āA���}�H�ł����Ȃ��A�������Ĕ��������Ȃ����̂ł������������A��̕����Ƃ��Ĉ�Ă��Ă����A���������i�P�W�O�S�`�j�ɂ��̍Ő����ނ����邱�ƂɂȂ�܂��B�ق�Ƃɍŋ߂̂��Ƃł��B���̌�A�����ېV�ɂȂ�A�����͕s���̎�����}���邱�ƂɂȂ�܂��B�����͍]�˕����ɖ������Ă������̂ł��邪�̂ɉ��ĉ���j�Q������̂ł���Ƃ��āA�������܂��B���ۂ̓X�܂̐�����������Ȃǂ̂��Ƃ�����A�X�ɂ͋@�B�ɂ�鐻�����s�Ȃ���ȂǁA�����������p���ɂȂ��Ă����܂��B
�@�����āA���͂ǂ����H
�@�ꕔ�̘V�܂�C�T���鋼���E�l�A�����ĉ�X�A�}�`���A�����ł��̎�ɂ���Ă��̓`���������������Ă���ƌ����Ă悢�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�i���Ȃ��d�j
�@���ɂ܂��߂ɂ��ߍׂ��������ꂽ�{�ŁA�����W�҂̕K�ǂ̏��Ƃ����Ă悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�S���������L�q�����ӏ������������܂��B
�P�u�w��ł��x�Ƃ́w�㓙�́x�Ƃ����Ӗ��ŁA�����ȂǂƂ̍��ʉ��̂��߂ɍ��ꂽ���t�ł���B�v�ɂ����i100���j
�@�u�Ƃ���ŁA�w�����S���x�i�����l�N�E1751�j�ɂ��A�����͂܂����������Ă��Ă��u���ǂv�Ɩ����X�������������A�����ɁA�����̐l�C�����܂�ɂ�Ċ̐S�̂��̕i���ɖ��̂���X�������Ă����悤�ŁA���낢��Ƌꌾ��悵�Ă���B�v����ɁA�Ȃ��̏������̔z�������̖�肾�B�Ђǂ��̂ɂȂ�ƁA�ʗ�͂��Ε��S�ɏ������P�̂Ƃ�����R��1�ɂ��Ă���ȂǂƎ������邻�Ή����炠�����B���҂̓��V�F���q���������Ɂu���ꂽ�v�Ə����Ă���B�d�i�����j�d�������A�F���q�͂��Ƃ̂ق����̕i���ɂ��Č��i�Ȑl�ł���A�肸����㓙�̂��Ε��݂̂ł���ł��Ă����Ƃ�������A���̔ᔻ�͌��������錙�������邩������Ȃ��B�d�i�����j�d����������ɂ����Ă̍��i1748�`64�j�͂܂������A���̌�A���́u�ʂ��v�̑㖼���ɂȂ��Ă��܂����Ƃ����B���������ɗ��ꏟ������������̕����̂Ȃ��ŊŔɌf����ꂽ�̂��u��ł��v�Ƃ������ڂł������B������ˋ@�ȂǑz������ł��Ȃ���������̂��Ƃł���A���͎�őłɌ��܂��Ă���B����ł������āu��ł��v�Ə̂����̂́A���Ή��ɑ��鍷�ʉ��̈ӎv�\���ȊO�̂Ȃɂ��̂ł��Ȃ����낤�B�d�i�����j�d
�w���攍e�x�i�V�ۂ���Éi���E1830�`54�j�́A�����̂��Ή��̏����̂悤�ɋL���Ă���B
�]���A��ɓ�\�l���̕������ӂ��A�ʋ����Ɖ]�B�ʂ͑y�i���ׁj�đe���]�̑����B�ʂɂ��A�s�����ɂ͎�łƋL���ǂ��A���͎�łƉ]�́A�ʂɐ��������ӓX����B�^�̎�ŋ������ɂ́A�̑ʂ��͂��炸�B�v
�Q�u������v�Ƃ������t�ɂ����i73���j
�@�u���̏ꍇ�͈Ӗ��̍��ׂƂ������オ�퍑����܂ő����B�����č]�ˎ���ɓ����Ă悤�₭�A�A�˂̏ꍇ�͖��m�Ɂu���ΐ�v�ƕ\�L�����悤�ɂȂ�̂ł���B���̂��߁A�����j�ł́u���ΐ�v�Ƃ����\�L���Ȃ��ꂦ�����ꍇ�Ɍ����āA�˂Ƃ��Ă̂��ƔF�߂�Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B�d�i�����j�d���݂̂Ƃ���˂Ƃ��Ă̏����Ƃ����̂́A�u���ΐ�v�Ƃ������t�����߂Č��������w�菟���i���傤���傤���j�����x�ł���B�d�i�����j�d�i����͂Ƃ������A�j�퍑����ɂȂ��ĂȂ��A�u���ΐ�v�Ƃ������̂��Ɨ����Ďg����悤�ɂȂ����̂��B���̋^��ɑ��ẮA�]���́u���v�Ƃ͖��炩�ɈႤ�H�i�A�܂�˂Ƃ��Ă̂����������ꂽ���߂Ƃ������߂����藧�B���̖˂���肷��K�v����V���Ɂu���ΐ�v�Ƃ������t���ł����A�Ƃ������߂��B�v
�R�@���肻�̐H���ɂ��āi�Ȃ�ł�������Ηǂ��Ƃ����킯�ł͂Ȃ��j�i265���j
�@�u����䥂łĐ���Ă���ЂƐ��ꂽ�Ƃ��낪�H���ŁA�����H���Ă���悤�Ȃ��ł͂���̂�Ȃ��B�v
|
|
|
20.1.30
|
�_�Ђ̌n���|�Ȃ������ɂ��邩�^�{�������^�����АV�� |
 �@���{�l�͕����k�ł���Ƃ����܂��B���̏ꍇ���A���Ȃ��̏@���͂Ȃɂ��Ɩ����u�����ł��B�@�h�͏�y�^�@�ł��B�v�Ɠ����邱�Ƃɂ��Ă��܂��B�������A����I�ɂ��o��O���������Ă���Ƃ������Ƃ͂���܂��A���l�ɂ��F�������ȂǂƂ������Ƃz���邱�Ƃ��炠��܂���B �@���{�l�͕����k�ł���Ƃ����܂��B���̏ꍇ���A���Ȃ��̏@���͂Ȃɂ��Ɩ����u�����ł��B�@�h�͏�y�^�@�ł��B�v�Ɠ����邱�Ƃɂ��Ă��܂��B�������A����I�ɂ��o��O���������Ă���Ƃ������Ƃ͂���܂��A���l�ɂ��F�������ȂǂƂ������Ƃz���邱�Ƃ��炠��܂���B
�@�����̎��ɔO���������Ă���ł��傤�H�ƌ����邩������܂��A�悭�悭�l���Ă݂�Ƃ���͕��l�ɂ��F�肵�Ă���̂ł͂Ȃ��A���̈ӎ��͖S���Ȃ����l�Ɍ������Ă��܂��B�����܂ŁA���ɂȂ�ꂽ���̐l�ł����Ă�����ݕ��l�ł͂Ȃ��̂ł��B���d�����邨��ł́A���X���F������Ă���ƌ����邩������܂��A���ۂ́A�S���Ȃ�ꂽ���e�Ȃǂ����̑ΏۂɂȂ��Ă���悤�Ɏv���܂��B
�@�܂�A���́A�Ƃ��������������{�l�͖{���̎p�̕����k�ł͂Ȃ��A�ƌ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@
�@�ł́A�������̏@���͂Ȃɂ��B
�@����́u�c�搒�q�v�ł���ƌ������ق������ۂɋ߂��̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł��B�����A��������������t�������āA���́u�c�搒�q�v�Ɂu�_���v�����킳�������̂ƌ��������ǂ��Ǝv���܂��B
�@���B�̓`���I�Ȋ��o�ɂ́A�l���S���Ȃ�ƃJ�~�ɂȂ��Ăǂ����R�̌��������Ƃ��A�_�̏ォ�ȂɏZ�ނ��ƂɂȂ�A���X��X�����̐l�Ԃ��������猩�Ă���B�����āA�~����ɂ́A��叼��ڈ�ɂ��Ă��ƏZ��ł����ƂɋA���Ă���B�ƁA�������������ł��B�i�J�~�Ə������̂͐_�iGod�j�ł͂Ȃ��A���B�́w��x�ɘA�Ȃ��Ă��邲��c�l�Ƃ������o����������A�����\�������ق����K���Ǝv���܂��B�j
�@�ȑO�A�����_�ЂɎQ�q�������Ƌ{�i����̂����A���@��������̂ł����A�Ō�ɂ������߂������܂����B
�@�u�d�F�l�ɁA�p��̂����삪����܂��悤�ɁB�v
�@����ɂ́A�т����肵�܂����B
�@���́A�p��ւ̊��ӂƒ����A�������������Ԃ߁A�̂��߂ɖ����_�ЂɎQ�����킯�ł����A�t�ɉp�삪���B������Ă����Ƃ����̂ł��B�ł��A�l���Ă݂�A�J���Ă�����X�͐_�l�ɂȂ��Ă����ł�����A�����̗͂������Ďq���ǂ�������Ă���������Ƃ����̂͂���Γ�����O�̂��ƂȂ̂ł��ˁB
�@�����A��ʂɂ́A�_�Ђɂ͂��̃R�~���j�e�B���ő��h����ɒl����l���J���Ă����ł��āA�F���F�J���Ă���킯�ł͂���܂���B�������A���B��������킹��Ƃ��ɂ́A���̓���̂��_�̂��܂߂Ď��B�ɂȂ��邲��c�l�����S�̂�O���ɒu���Ă���悤�ȋC�����܂��B
����Ȃ��Ƃ��v���Ă��܂��̂ŁA�Ђ���Ɩڂɕt�������̖{��ǂ�ł݂��킯�ł��B
�@���̖{�ɂ��ƁA�_�Ђ̈ʒu�Ƃ����̂ɂ͑傫�ȈӖ�������A�Ƃ����̂ł��B���̊��o�ł́A�y�n���Ă��āA�y�n�オ�������炻���Ɍ��Ă悤�Ƃ������z�ɂȂ�Ǝv���̂ł����A�����ł͂Ȃ��A�Ȃɂ��낻�̐̂͗��Ă�ꏊ�͂�����ł��������킯�ł�����A�����Ɍ��Ă�ɂ͂�����ׂ����R�������āA���ꂪ�D�悳���킯�ł��B
�@
�@���̖{�̑O�i�́A������̎�ˁA�_�c���_���̑��̊֘A�_�Ђ̂��Ƃɂ��Ă̘b��ł��B
������́A���������J���������V�c�̂V��ڂ̑��ɂ�����c���ł���֓���т�̒n�Ƃ��鍋���ł������A�X�R�X�N�A������u�V�c�v�Ə̂��ċ������܂��B�������A�s�ނ����ǎ���Ƃ��Ă��܂��܂��B���̌�A���s�����͌��ł��炵��ɂ���܂����A���̎�͂R����Ɋ֓��ɔ��ōs���܂��B���n�_�͕������L���S�č葺�i���̑�蒬�t�߂Ǝv���܂��j�B���ۂ̂Ƃ���́A�u��Ɠ����ꏏ�ɂ��Ȃ����M�肪����v�Ƃ��ĉƐb�̗v���őm�����^�Ƃ������Ƃ̂悤�ł��B��˂ɔ[�߂�ꂽ���Ƃ��M�葱���A�r�Ԃ�_�ł������悤�ł��B
�@�]�˖��{���J�����ƍN�́A���傪���G�ł���Ƃ������Ƃ����܂��Ă��A����֘A�̂��_�̂��]�˂̗v���v���ɔz�u���č]�˂̈��J���v�����Ƃ������Ƃ̂悤�ł��B
�@��͎�˂ɖ��߂�����̋߂��ɁA��͐���t�߂̒��z�_�Ђɔ[�߉��B���̎��_�Ƃ��āA�܂����͐_�c�_�Ђ̂��_�̂Ƃ���ē������ɑΉ��A���͒��哹�̏o������ɓ����鋍����̘e�̒}�y�����_�ЂɁA�b�B���ɂ͎l�J��̕t�߂̊Z�_�ЂɁA���C���͌Ճm��̊��_�Ёd�Ƃ������ł��B�܂�A�]�˂Ɍq����X���ɐ_�Ђ����ĂāA�����ɍr�Ԃ�_�ł��鏫������_�̂Ƃ��Ă��܂肵���A�Ƃ�����ł��B���Ȃ킿�A�_�Ђ̈ʒu�ɂ͈Ӗ�������Ƃ�����̗�ł��B
�@���̖{�̌�i�ɂ́A���{�e�n�̐_�Ђ̒n���I�ʒu���Ȃ��ƁA�Ď��~���̍ۂ̓��o�v�̕��ʐ��ɍ��v����Ƃ����b���q�ׂ��Ă��܂��B�Ď���~�����A���z�̗͂��������Ȃ�A���邢�͑傫���Ȃ�Ƃ����������������āA���̕��ʐ��ɑ傫�ȈӖ������o�����Ƃ������Ƃ̂悤�ł��B�������Ƃɂ͑��z���q�Ƃ����̂�����̂ł��傤�B�����A���̖{�ł͂��������ʒu�W�����o�����Ƃ��ł��A����͋��R�ł͂Ȃ��A�Ƃ����������Ɏ~�܂��Ă��܂��B���ꂾ���̎��Ⴊ������̂��Ƃ����������������肻���Ɏv���܂����A���̂��Ƃ͒�������Ă��Ȃ��悤�ł��B��ϋ����[�����e�ŁA�傢�ɂ��ȂÂ���̂ł����A���܂����̊����ۂ߂܂���B�ɂ����B
|
|
���t���[����\���@�@���g�n�l�d��
|
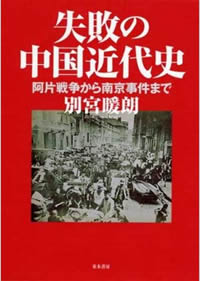 �@�����ߑ�j�͎��s�̘A���ł������A�Ƃ������Ƃ҂͏q�ׂĂ����̂ł����A�ǂ����Ăǂ����ē��{������ɗ�炸�O��ʂł̐ٗ��ڗ����܂��B�����Ȃ�A�V�i�͍�������̈��i���j�ŁA���{�͂ǂ����悤���Ȃ����l�悵�Ƃ������Ƃł��傤���B
�@�����ߑ�j�͎��s�̘A���ł������A�Ƃ������Ƃ҂͏q�ׂĂ����̂ł����A�ǂ����Ăǂ����ē��{������ɗ�炸�O��ʂł̐ٗ��ڗ����܂��B�����Ȃ�A�V�i�͍�������̈��i���j�ŁA���{�͂ǂ����悤���Ȃ����l�悵�Ƃ������Ƃł��傤���B �@�Ȃ��Ƃ������H
�@�Ȃ��Ƃ������H
 �@�ȑO�A���ҁu���M��v���̍u�����@�����܂��āA���̖{����ɂ��܂����B
�@�ȑO�A���ҁu���M��v���̍u�����@�����܂��āA���̖{����ɂ��܂����B �@���{�l�͕����k�ł���Ƃ����܂��B���̏ꍇ���A���Ȃ��̏@���͂Ȃɂ��Ɩ����u�����ł��B�@�h�͏�y�^�@�ł��B�v�Ɠ����邱�Ƃɂ��Ă��܂��B�������A����I�ɂ��o��O���������Ă���Ƃ������Ƃ͂���܂��A���l�ɂ��F�������ȂǂƂ������Ƃz���邱�Ƃ��炠��܂���B
�@���{�l�͕����k�ł���Ƃ����܂��B���̏ꍇ���A���Ȃ��̏@���͂Ȃɂ��Ɩ����u�����ł��B�@�h�͏�y�^�@�ł��B�v�Ɠ����邱�Ƃɂ��Ă��܂��B�������A����I�ɂ��o��O���������Ă���Ƃ������Ƃ͂���܂��A���l�ɂ��F�������ȂǂƂ������Ƃz���邱�Ƃ��炠��܂���B �@�u�ݍ��n�߂̕���v�Ɓu�ǂ��܂ł킩�郄�}�^�C���v�̂Q���\���ɂȂ����{�ł��B�X�O�y�[�W���x�̔����{�ʼn��i�͂S�O�O�~�B�ł����A���e�͔��ɗǂ����̂ł���Ǝv���܂����B
�@�u�ݍ��n�߂̕���v�Ɓu�ǂ��܂ł킩�郄�}�^�C���v�̂Q���\���ɂȂ����{�ł��B�X�O�y�[�W���x�̔����{�ʼn��i�͂S�O�O�~�B�ł����A���e�͔��ɗǂ����̂ł���Ǝv���܂����B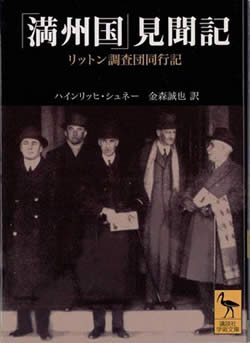 �@���҂̓h�C�c�l�����ƂŁA���b�g�������c�T���̂����̂P���ł��B
�@���҂̓h�C�c�l�����ƂŁA���b�g�������c�T���̂����̂P���ł��B �@�u���q�Ƃ͂Ȃɂ��v�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A���q�ɏ����ꂽ�������̋L�q��������������s���A�K�v�ɉ����ĉ������Ƃ����`�Ԃ̒���ł��B�܂蕺�����̖|�ł��B
�@�u���q�Ƃ͂Ȃɂ��v�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A���q�ɏ����ꂽ�������̋L�q��������������s���A�K�v�ɉ����ĉ������Ƃ����`�Ԃ̒���ł��B�܂蕺�����̖|�ł��B �@��̑�풆�A���s����P����Ƃꂽ�̂́A�č��̕��������d�Ƃ����f���炵���l�������������炾�A�Ƃ�������������܂��B�������̖{��ǂނ܂ł́A�����l���Ă���܂����B�Ƃ��낪�A�����͂����ł͂Ȃ��悤�ł��B���҂ɂ�鎑�����@���܂߂Đ��X�̃f�[�^�������āA���̂��Ƃ����R�Ɣے肵���̂����̖{�ł��B
�@��̑�풆�A���s����P����Ƃꂽ�̂́A�č��̕��������d�Ƃ����f���炵���l�������������炾�A�Ƃ�������������܂��B�������̖{��ǂނ܂ł́A�����l���Ă���܂����B�Ƃ��낪�A�����͂����ł͂Ȃ��悤�ł��B���҂ɂ�鎑�����@���܂߂Đ��X�̃f�[�^�������āA���̂��Ƃ����R�Ɣے肵���̂����̖{�ł��B �@�P�Ɉ̑�ȓV�c�ł������A�Ƃ������u�l���Č���ΑS���H�L�i�����j�̑��݂ł���B�v�i���҂܂������j�ƌ����܂��B�����āA�u�l�ގj�エ���炭�O�Ⴊ�Ȃ��A������Ăт��̂悤�Ȑ��U��������l���͌���܂��A�Ǝv����̂����a�V�c�ł���B�v�i���j
�@�P�Ɉ̑�ȓV�c�ł������A�Ƃ������u�l���Č���ΑS���H�L�i�����j�̑��݂ł���B�v�i���҂܂������j�ƌ����܂��B�����āA�u�l�ގj�エ���炭�O�Ⴊ�Ȃ��A������Ăт��̂悤�Ȑ��U��������l���͌���܂��A�Ǝv����̂����a�V�c�ł���B�v�i���j �@���{�ɂ��čl����ہA�V�c�̑��݂��͂������Ƃ͂ł��܂���B�ߋ��ɂ����Ă��܂����݂ɂ����Ă���ɓ��{���̒��S�Ƃ��đ��݂���A���ƂƂ��Ă̑傫�ȕ����]�������߂���ǖʂȂǂŏd��Ȍ��f�����A�䍑�̈��ׂ�����Ă����Ă����ł��B
�@���{�ɂ��čl����ہA�V�c�̑��݂��͂������Ƃ͂ł��܂���B�ߋ��ɂ����Ă��܂����݂ɂ����Ă���ɓ��{���̒��S�Ƃ��đ��݂���A���ƂƂ��Ă̑傫�ȕ����]�������߂���ǖʂȂǂŏd��Ȍ��f�����A�䍑�̈��ׂ�����Ă����Ă����ł��B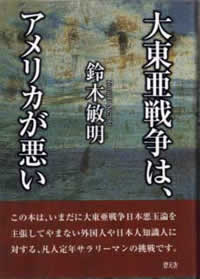 �@�V�R�T�y�[�W�̑咘�ł��B
�@�V�R�T�y�[�W�̑咘�ł��B �@��v�q�ܓa���͍Ō�̏��R����c��̂Б��ɓ�����܂��B�c���̎��Ɍc��ɕ����ꂽ�ʐ^������܂����A��{�l�ɂ͌c��̋�̓I�Ȏv���o�͂Ȃ������ł��B�P�W�ō����{�a���Ƃ������B
�@��v�q�ܓa���͍Ō�̏��R����c��̂Б��ɓ�����܂��B�c���̎��Ɍc��ɕ����ꂽ�ʐ^������܂����A��{�l�ɂ͌c��̋�̓I�Ȏv���o�͂Ȃ������ł��B�P�W�ō����{�a���Ƃ������B �@�Ȃɂ��̏��]��ǂ�Ŏ�ɂ����{�ł��B
�@�Ȃɂ��̏��]��ǂ�Ŏ�ɂ����{�ł��B